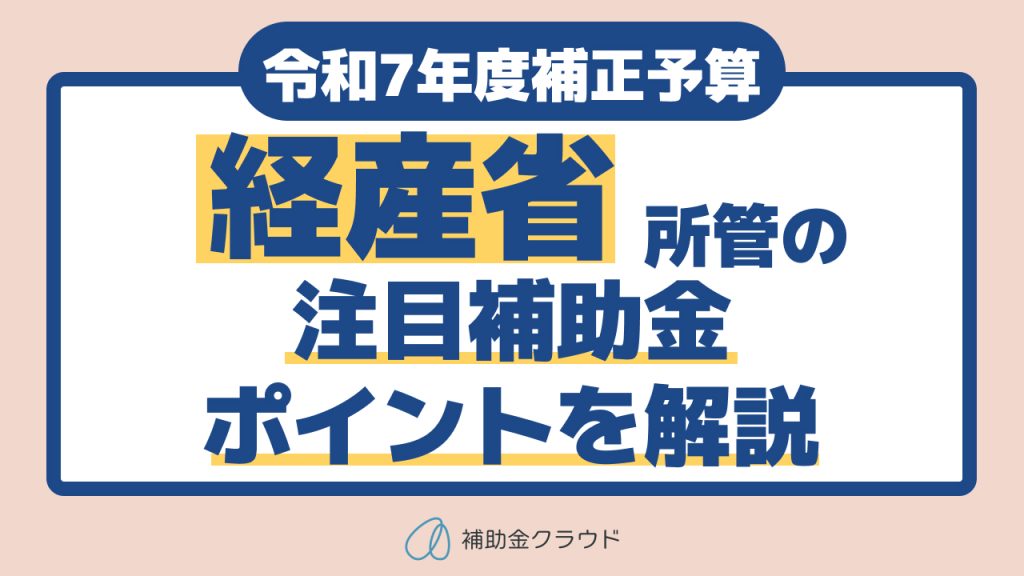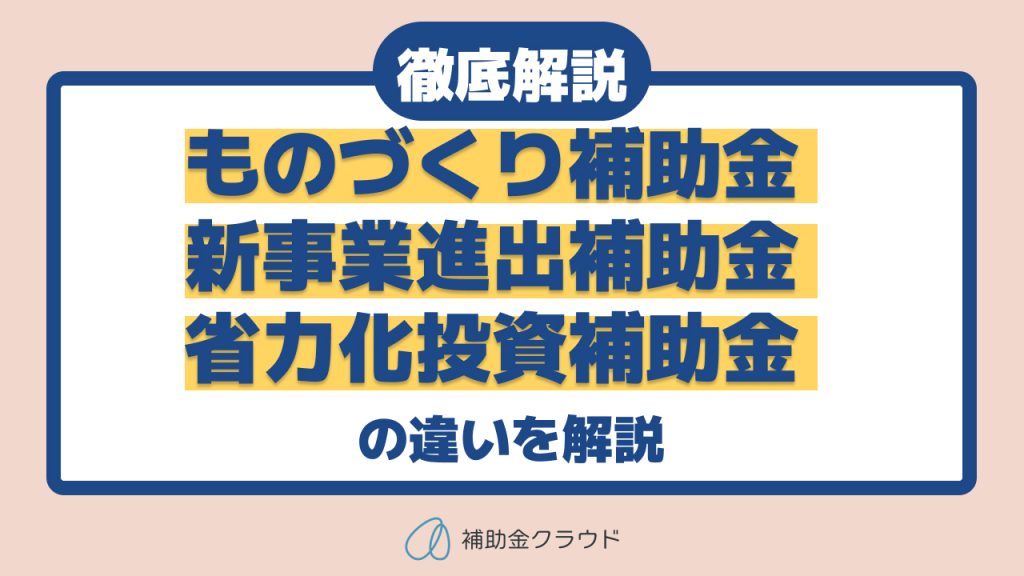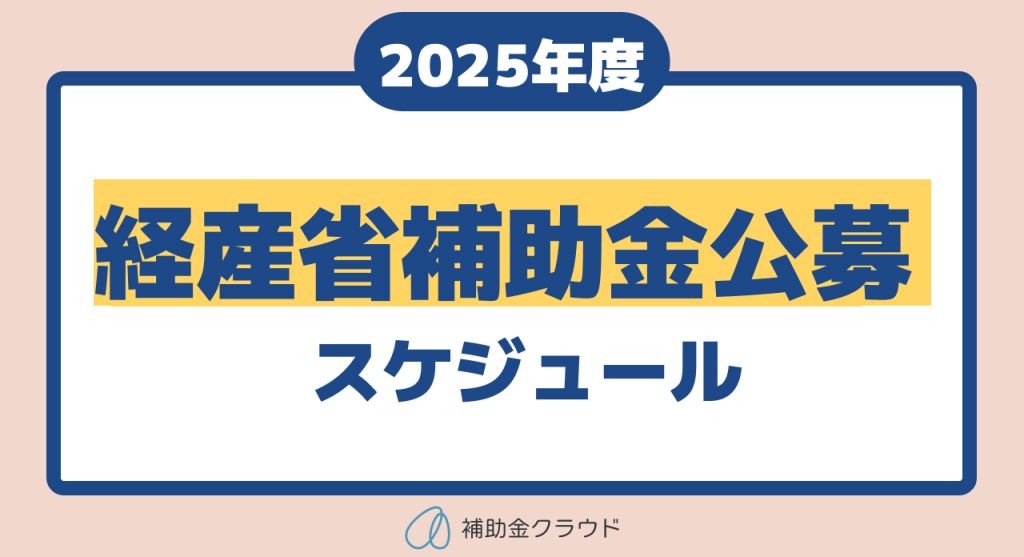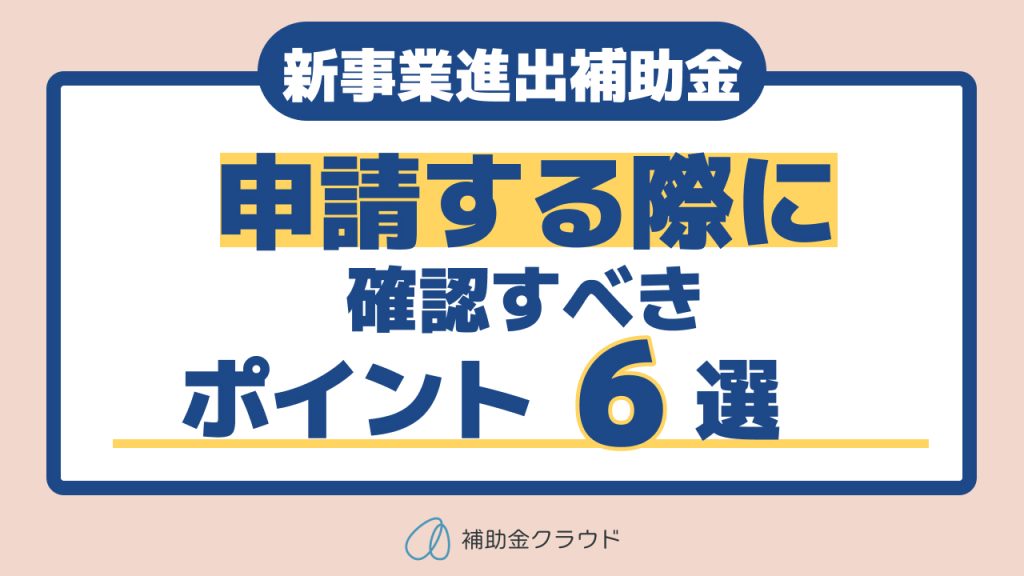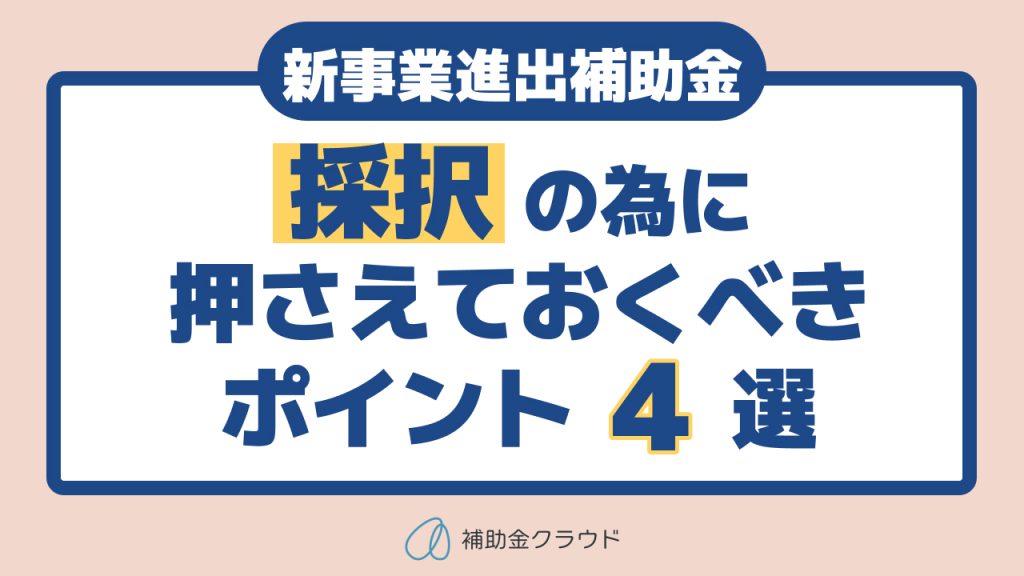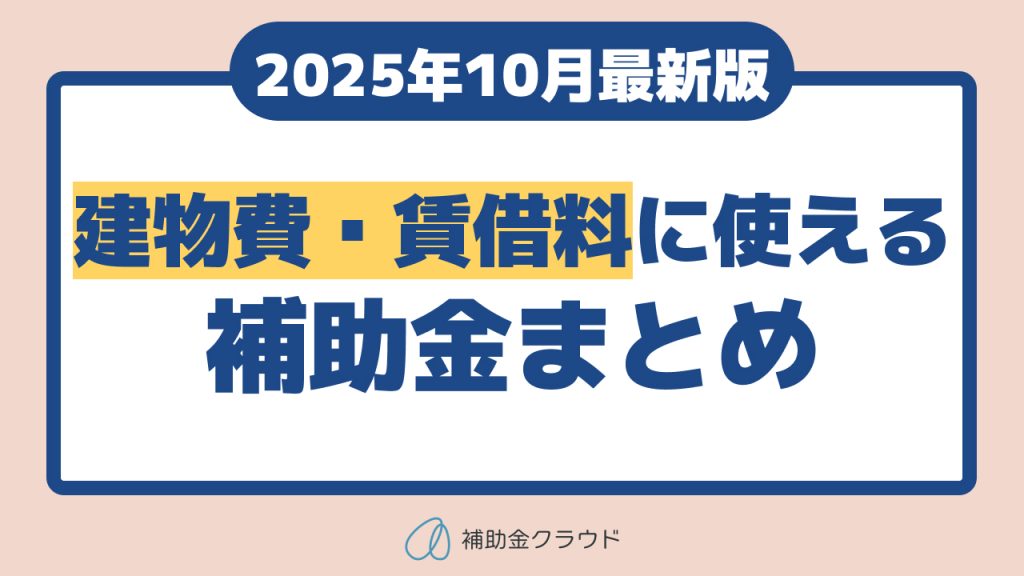本事業は、我が国の国際獣疫事務局(以下、「WOAH」という。)が認定するリファレンスセンター等における、国際的な診断技術水準の向上への取組等の活動強化の推進及び診断・検査体制への信頼性の向上の取組等を支援することを目的とするものです。
全国の補助金・助成金・支援金の一覧
1171〜1180 件を表示/全2443件
高品質なコンテンツ(映像、ゲーム等)の本制作に向け、多様な資金調達やパートナー獲得、クオリティの高い企画・脚本等の開発、契約交渉・資金調達における権利処理を行う取組を支援します。
倉敷市では 観光客誘致につながる市内での映画撮影を誘致するため、倉敷市が舞台となる映画を制作するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
国の地方創生応援税制である企業版ふるさと納税を活用しながら、「一般補助金」と「企業版ふるさと納税活用型補助金」の2種類の補助金を交付します。
補助金額
ア 一般補助金 補助対象経費の実支出額から他の補助金等を控除した額(補助対象額)に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て) 限度額100万円(自己負担額100万円)
イ 企業版ふるさと納税活用型補助金 寄附額に応じて決定(上限額「補助対象額-200万円」(千円未満切り捨て))
多核種除去設備等処理水(以下、「ALPS処理水」という。)の海洋放出に伴い、仮に風評影響が生じた場合でも、水産物需要減少への対応を機動的・効率的に実施する取組に要する経費に対して、国からの補助金を受けて基金を造成し、当該基金から当該経費の一部を補助することにより、漁業者の方々が安心して漁業を続けていくことができるようにすることを目的とし、水産物の販路拡大等の取組、水産物の一時的買取り・保管の取組及び養殖水産物の出荷調整への取組を支援いたします。
非常事態において必要な医療機器、又は本邦の医療提供の維持に必要な医療機器について、国内生産体制を構築し、将来にわたって維持していくことを目標とし、事業終了時において、検証的試験を終えて薬事承認申請の目途が立っていること、提案医療機器の国内生産体制を構築する目途が立っていることを成果とし、「医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靭化事業(医療機器開発体制強靱化)」に係る公募を行います。
本公募の補助金の規模・事業実施期間・新規採択課題予定数等について、下表に示します。
| # | 分野、領域、テーマ等 | 補助金額 (間接経費を含まず) |
研究開発実施 予定期間 |
新規採択課題 予定数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 供給途絶リスク等がある医療機器(医療機器本体)の開発・改良 | 1課題当たり年間 82,000千円(上限) |
令和6年5月(予定)
~ 令和8年度末
|
0~1課題程度 |
| 2 | 供給途絶リスク等がある医療機器(医療機器本体以外)の開発・改良 | 1課題当たり年間 36,000千円(上限) |
0~1課題程度 |
日本医療研究開発機構では、希少疾病用医薬品の製造販売承認取得を目指す研究開発型企業等における開発を推進するため、一定の開発費用を補助する希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業を行っています。
本事業において、創薬ブースターで支援したシーズの実用化を推進するため、創薬ブースターと連携して希少疾病用医薬品の開発を支援します。
創薬ブースターの支援テーマの導出先候補企業に選定されている、又は導出先企業に決定された製薬企業等のうち、希少疾病用医薬品指定前実用化支援事業による支援を希望する企業等を募集します。
交通に関する知見、交通に関するデータ活用のノウハウ、多様な関係者とのコーディネートを推進するスキル等を活用しながら、地域の交通が目指すべき姿の実現に向けて、主体的かつ継続的に取り組む人材を育成する事業を対象とします。
本公募は、令和7年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
-----
米の需要減少が継続する中で、米を利用した新たな商品の開発等・ニーズに基づく播種前契約のための取組により、米の需要を拡大・創出を図るとともに、実需者のニーズを播種前契約を通じて生産に反映させ、主食用米の需給ギャップ縮小に貢献することを目的として実施します。
経済産業省は、荷主を含む複数企業が連携した物流施設の自動化・機械化に資する機器・システムの導入等の取組を補助する持続可能な物流効率化実証事業費補助金の公募を開始しました。
本補助金によって、幅広い物流効率化の取組など、持続的な物流の実現に向けた取組を支援します。
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)では、令和7年度「新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業-ヘルステック・チャレンジ-」に係る公募を行います。
本事業では、ヘルスケア分野の社会課題の解決に資する研究開発支援策として、新たなマイルストーン型の研究開発支援「ヘルステック・チャレンジ」を行います。本事業における新たなマイルストーン型の研究開発支援「ヘルステック・チャレンジ」では、従来の少数の課題への集中的な支援とは対照的に、スタートアップ企業及び起業する意思のあるアカデミアにおける以下の課題を対象とした研究開発の初期フェーズにある多数の課題に対して分散的な支援を行ったのち、マイルストーン型の段階的な選抜と集中による支援を行います。
- 1. 薬剤耐性(AMR)を含む感染症に対応する診断・治療・予防法で、革新性の高い、インパクトのある研究開発課題
- 2. 感染症における平時、有事における社会課題の解決につながる広範な研究開発課題
本事業では、革新性の高い、インパクトのある、ヘルステック(メドテックを含む)開発を行うスタートアップ企業を創出及び支援し、イノベーションを加速して、開発リスクが高く着手が難しいとされる課題の開発を促進することにより、ヘルスケア分野の社会課題を解決することを目指します。
新規採択課題予定数:0~20課題程度
- エリア
から検索 - 利用目的
から検索 - 業種
から検索