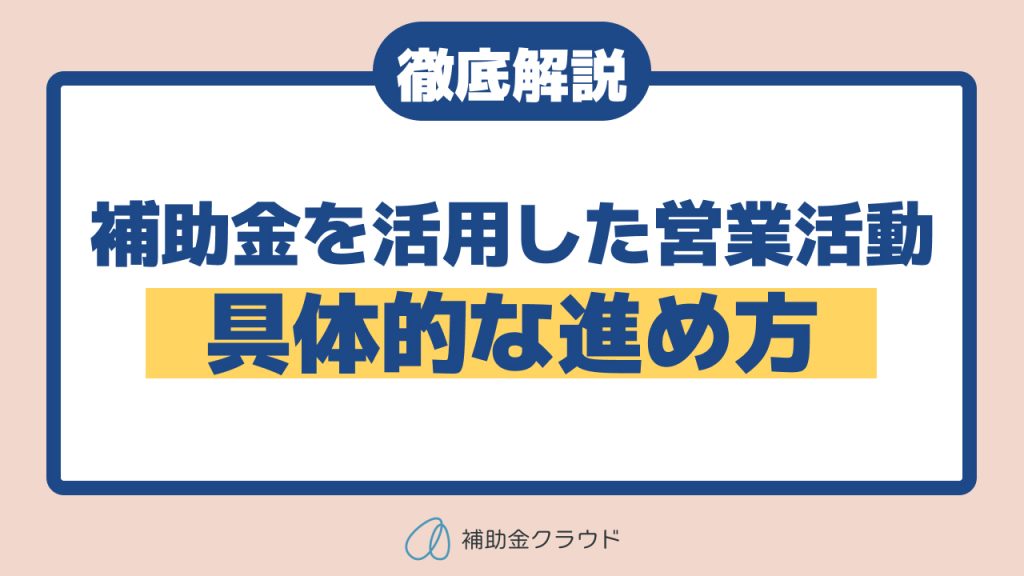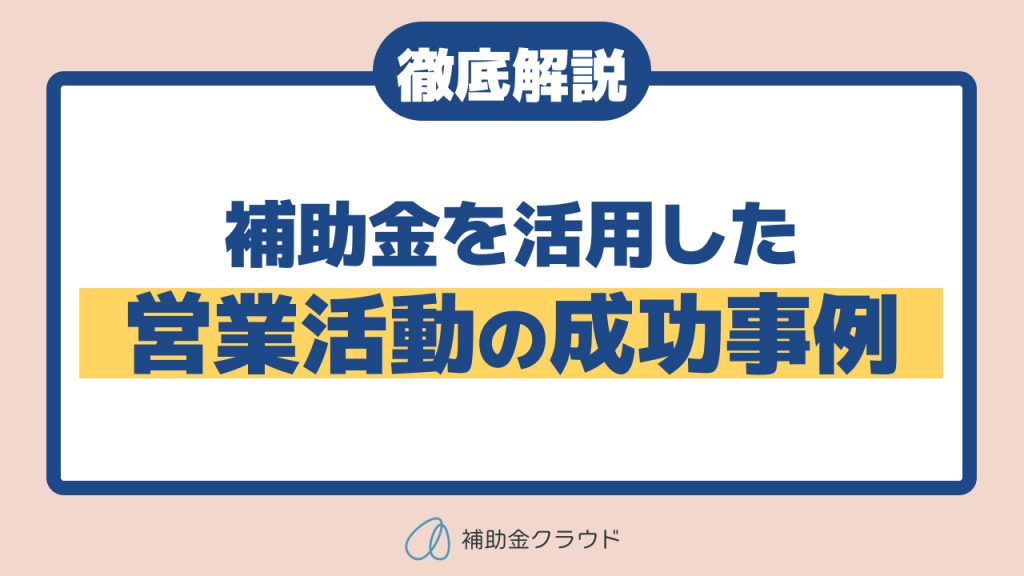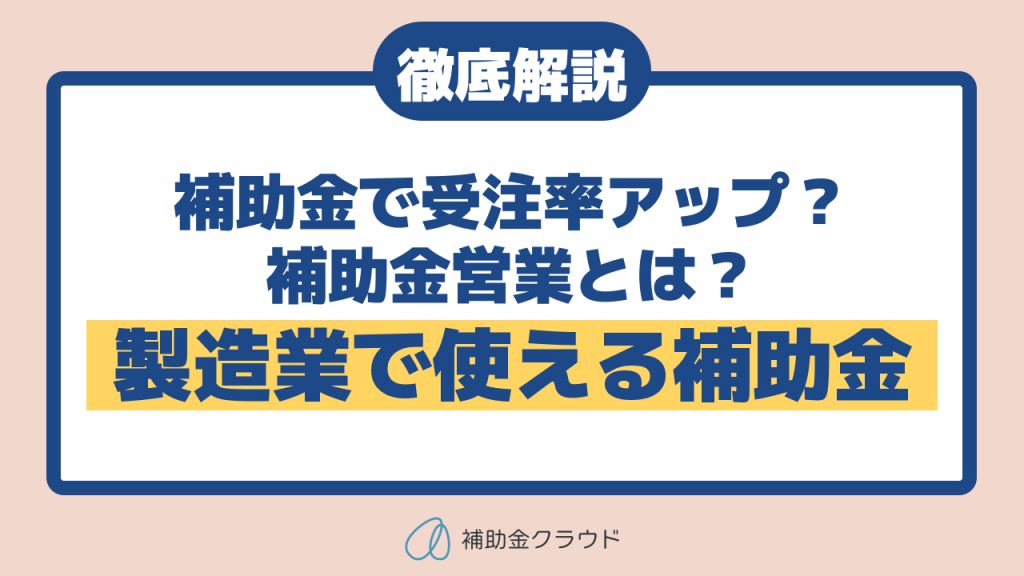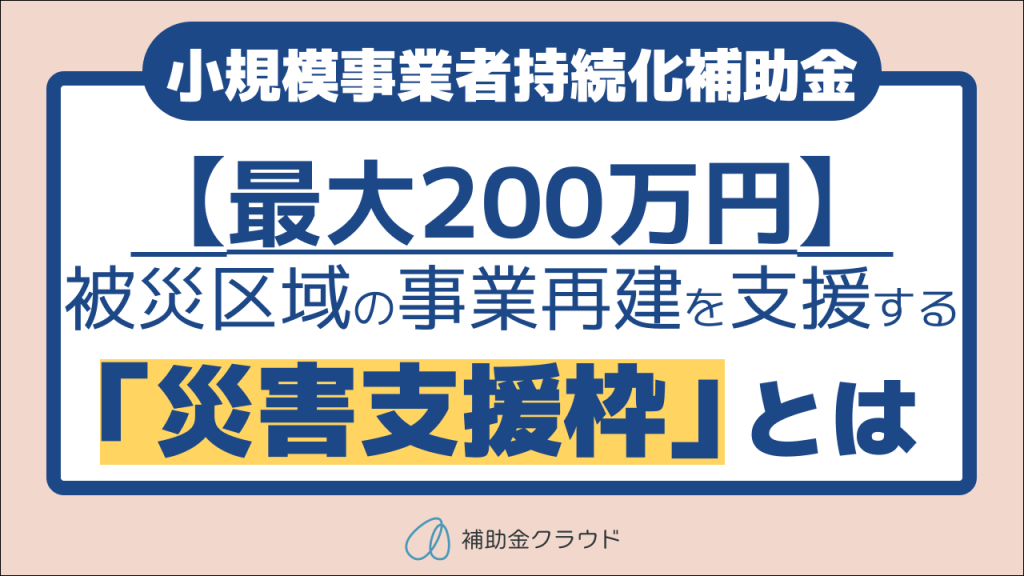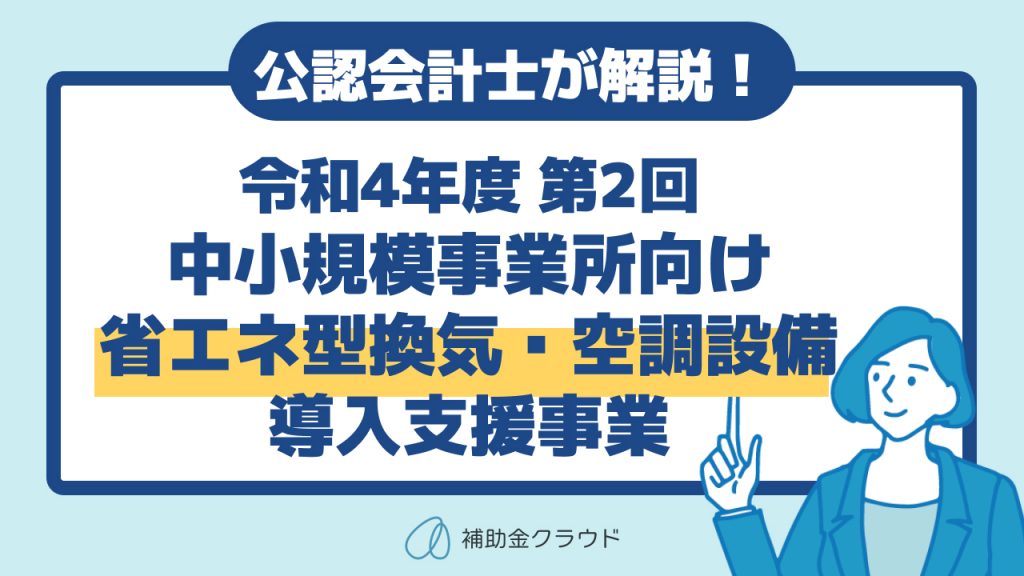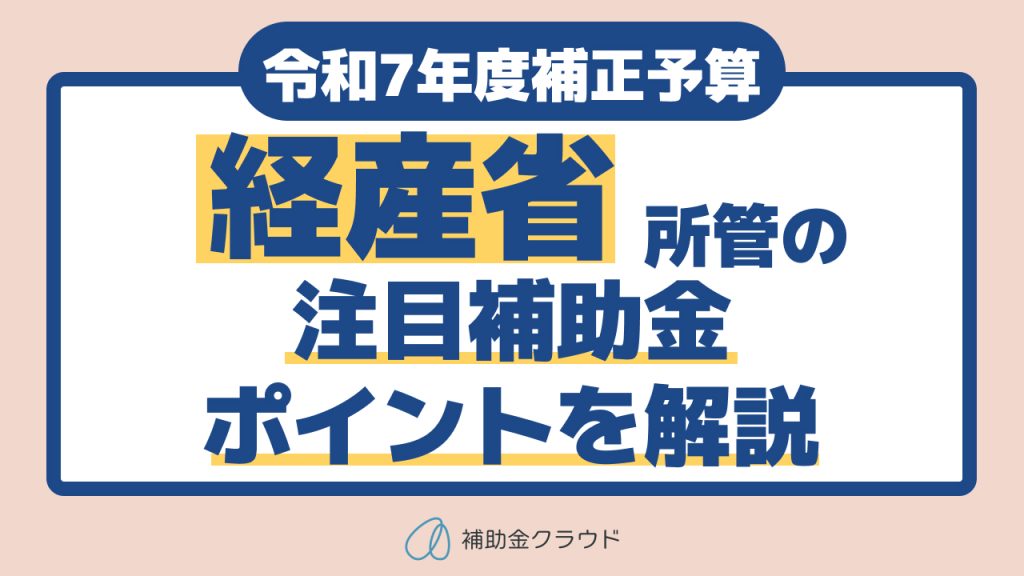中小企業大学校(人吉校)で開催される研修に参加する費用を一部助成します。
全国の補助金・助成金・支援金の一覧
15021〜15030 件を表示/全27044件
日向市では、日南市内で創業を予定されている方に対して、創業に必要な費用の一部を助成します。
都城市では、市内の中小企業者で、M&Aや役員・従業員承継を予定している人に対して、事業承継の着手段階にかかる費用の一部を補助します。
都城市では、「日本一の肉と焼酎のふるさと都城」で、本物の肉と焼酎を味わい、その魅力を体感できる旅行を企画、実施した旅行業者を支援します。
令和8年度事業については、令和8年度当初予算案に盛り込まれているものであり、予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため成立前に公募するものです。
------------------------------
総務省では、被災情報や避難情報など、国民の生命・財産の確保に不可欠な情報を確実に提供することを目的に、「放送ネットワーク整備支援事業(地上基幹放送ネットワーク整備等事業)」を実施します。これは、予備送信設備、災害対策補完送信所、緊急地震速報設備等の整備を行う地方公共団体、民間テレビ・ラジオ放送事業者等に対し、整備費用の一部補助を行うものです。
延岡市では、農林業者及び農林業者団体に対し、生産工程での無理・無駄の解消や、食の安全・安心、環境保全、農作業安全等の農業経営の改善を図る取組である『GAP』の取得に必要な経費等を補助するため、「環境にやさしい農業等普及支援事業」を実施しています。
自宅等の塀を撤去する場合、費用の一部を川崎市が負担します。
令和6年能登半島地震で被災した家屋等について、生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、申請により費用を償還します。
令和6年能登半島地震により被災した家屋等について、生活環境保全上の支障の除去、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図るため、所有者等の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)です。
また、所有者自ら被災家屋等を解体・撤去した場合は、その費用を基準に基づき償還します。
令和6年能登半島地震により倒壊したブロック塀等に関して生活環境の保全上の支障を除去するため、早期の安全確保を目的とし、自らの費用負担により収集運搬を行った方に対し、当該収集運搬に要した費用の償還を行います。
- エリア
から検索 - 利用目的
から検索 - 業種
から検索