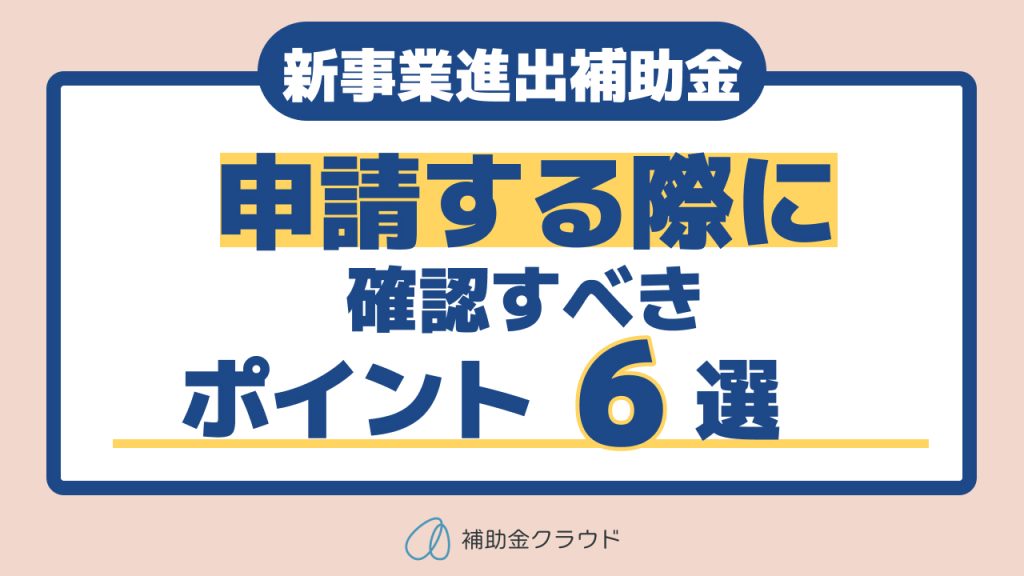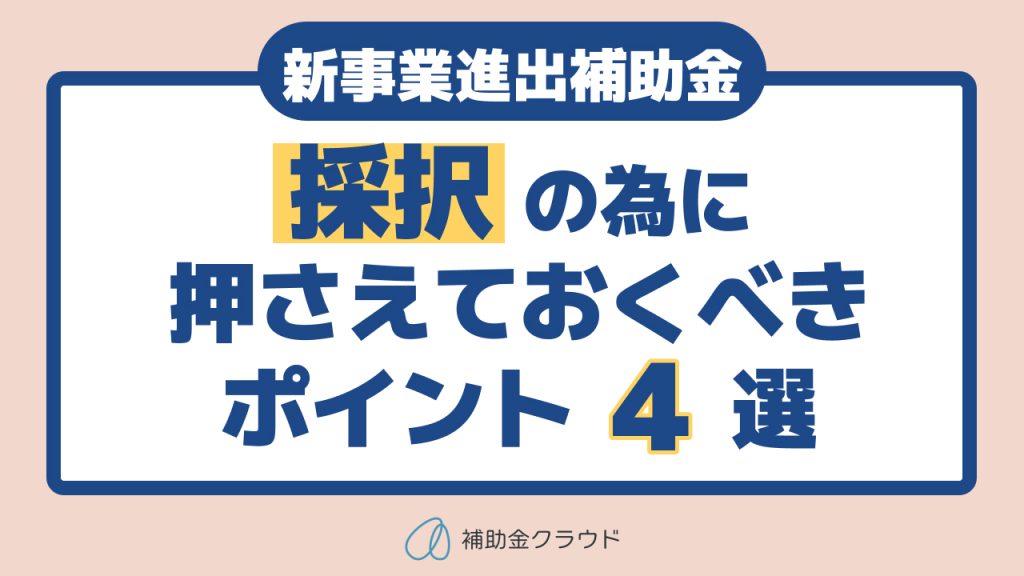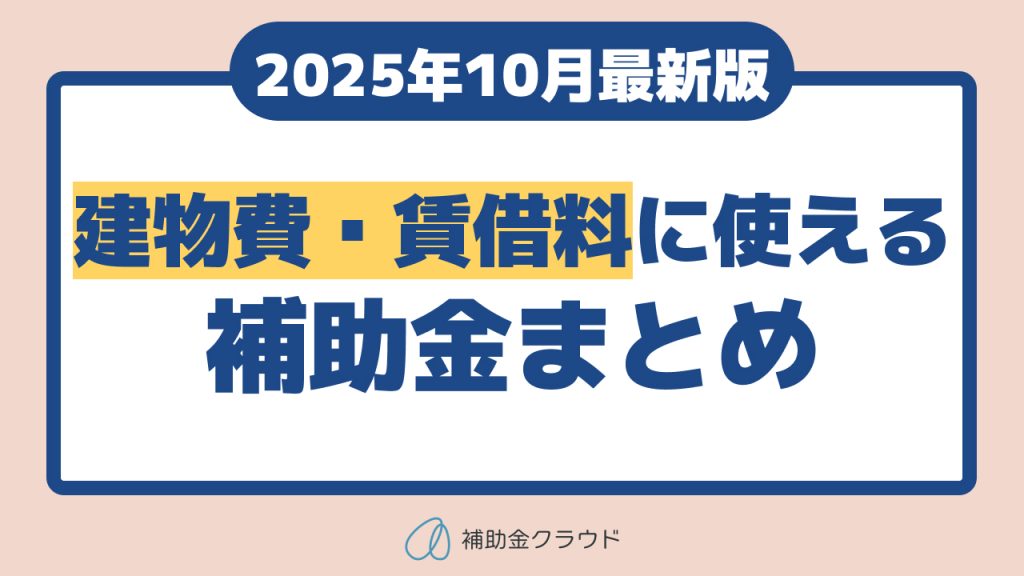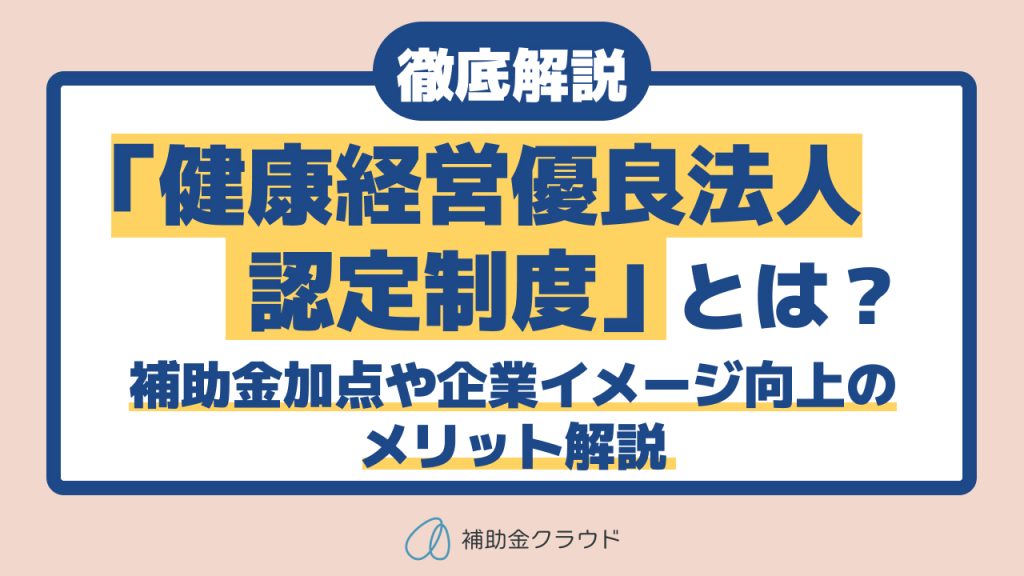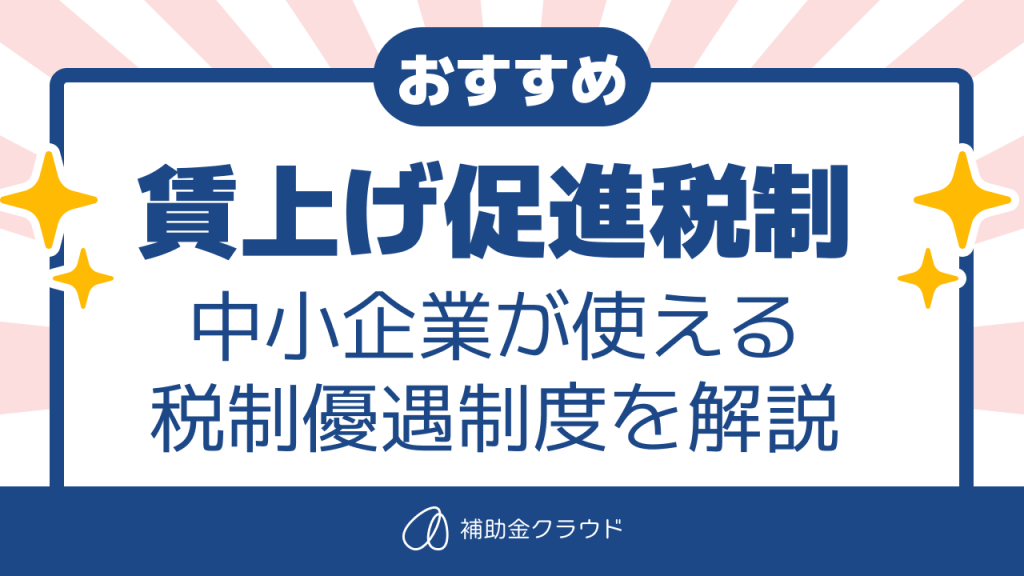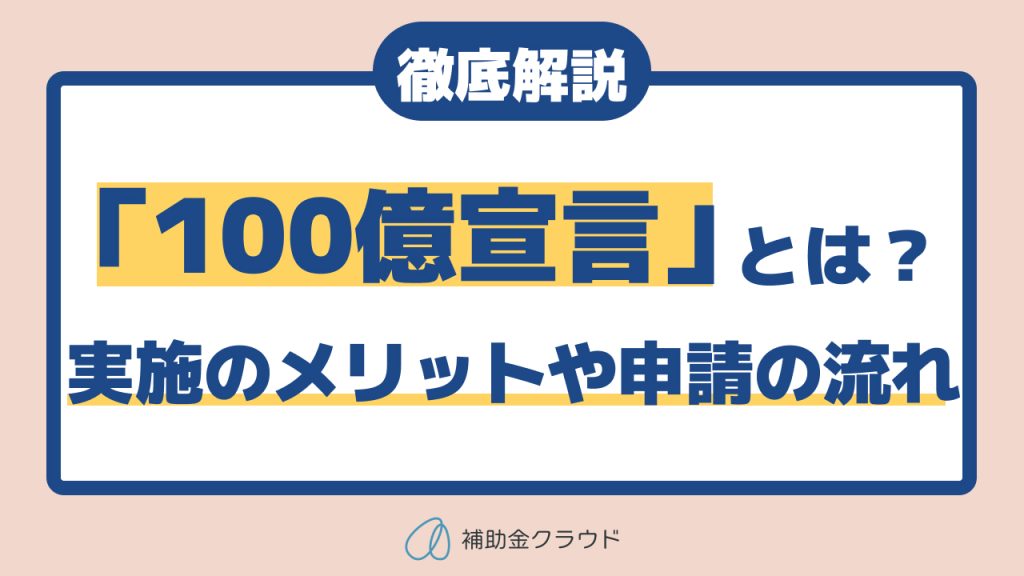全国の補助金・助成金・支援金の一覧
321〜330 件を表示/全2300件
本事業では、国が定める重点感染症に対して、感染症有事にいち早く、安全で有効な、国際的に貢献できるワクチンを国内外に届けることを目標としており、(1)感染症ワクチンの開発、(2)ワクチン開発に資する新規モダリティの研究開発を実施します。
また、長期的・安定的に、産学官・臨床現場の連携による総合的な研究開発推進体制により戦略的に支援することとしており、その一環として、ワクチン開発の研究代表者が進める研究開発等について、より優れたワクチン等の速やかな実用化に資するよう、現時点で、以下の支援ユニットを設けており、今後も適宜増設することとしています。
※新規採択課題予定数:0~1課題程度
「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業」(以下「本事業」という。)は、我が国の放送コンテンツの海外流通の促進を目的として、国内の放送事業者又は番組製作会社等に対し、海外での放送・配信を前提とした実写コンテンツの制作において、4K、VFX、3DCG、AI技術等の先進的な設備又は放送機材(以下「先進的設備等」という。)を取得又は使用に要する経費、先進的設備等を活用する制作に要する経費の一部を支援(間接補助金交付)するものです。
この度、本事業に係る間接補助事業者の公募を、執行管理団体である株式会社電通(以下「事務局」という。)を通じて実施します。
採択予定件数: 1件
管理者等が利用する届出システム等の見直し・改善による届出エラーの減少により牛個体識別情報の精度向上と監視業務の効率化を図るため、令和6年度に改修する届出システムの利便性の向上や、これまでのエラー発生状況を踏まえたエラーチェック条件の見直しを支援します。
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所では、厚生労働大臣から特定用途医薬品、特定用途医療機器、特定用途再生医療等製品の指定を受けた品目であって、かつ、その対象者数が 5 万人未満の品目を開発する開発企業に対し、その開発に必要な経費に充てるための助成金(「特定用途医薬品等試験研究助成金」という。)を交付する事業を行っています。なお、事業内容の詳細は、「助成金交付の手引き」等をご参照ください。
https://www.nibn.go.jp/activities/promote/tokutei_support.html
- エリア
から検索 - 利用目的
から検索 - 業種
から検索