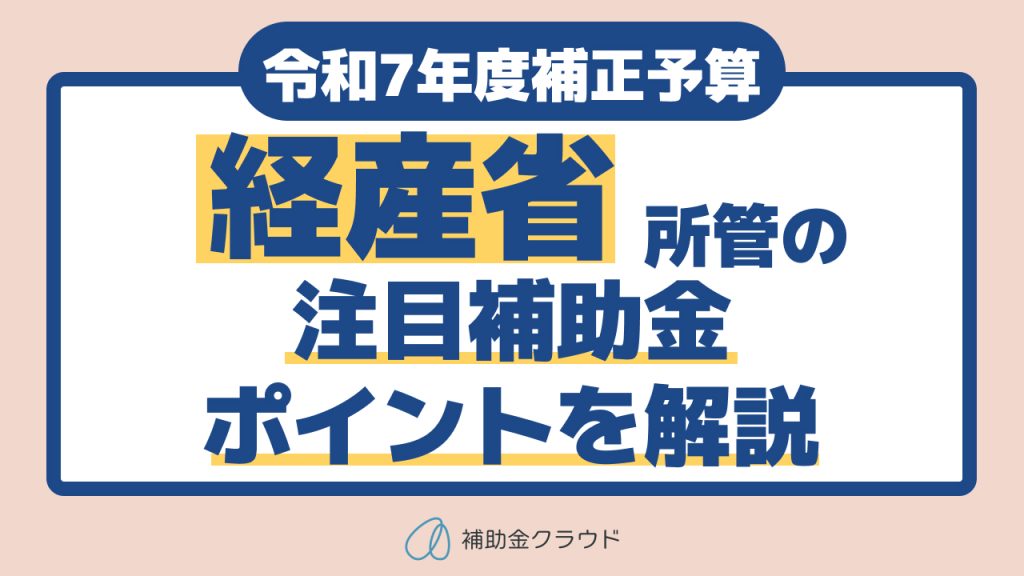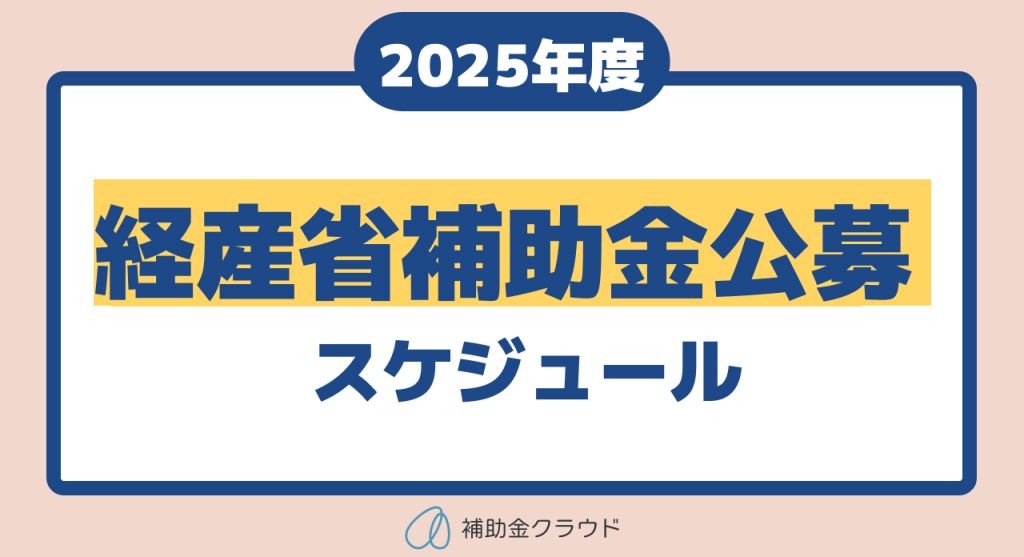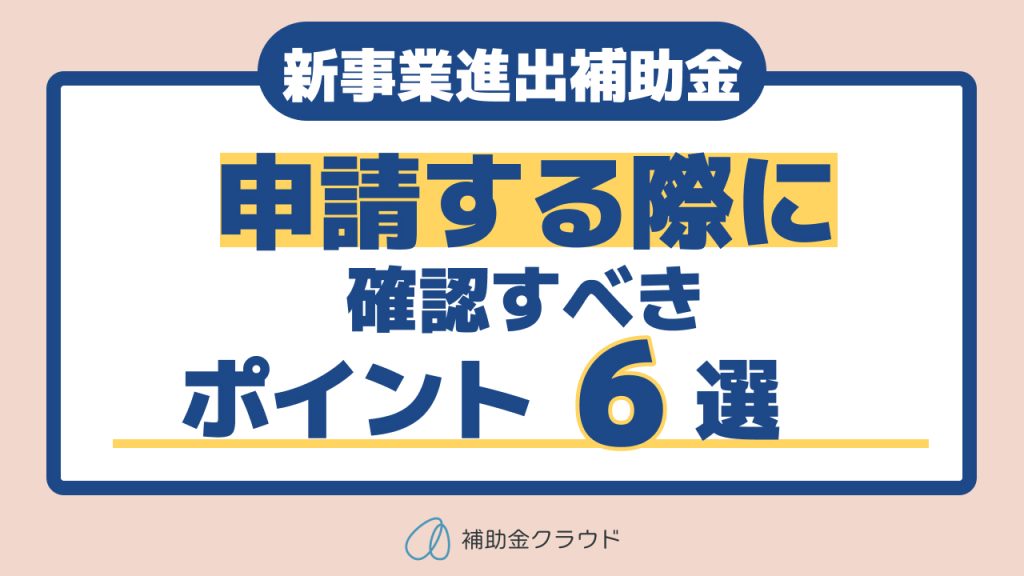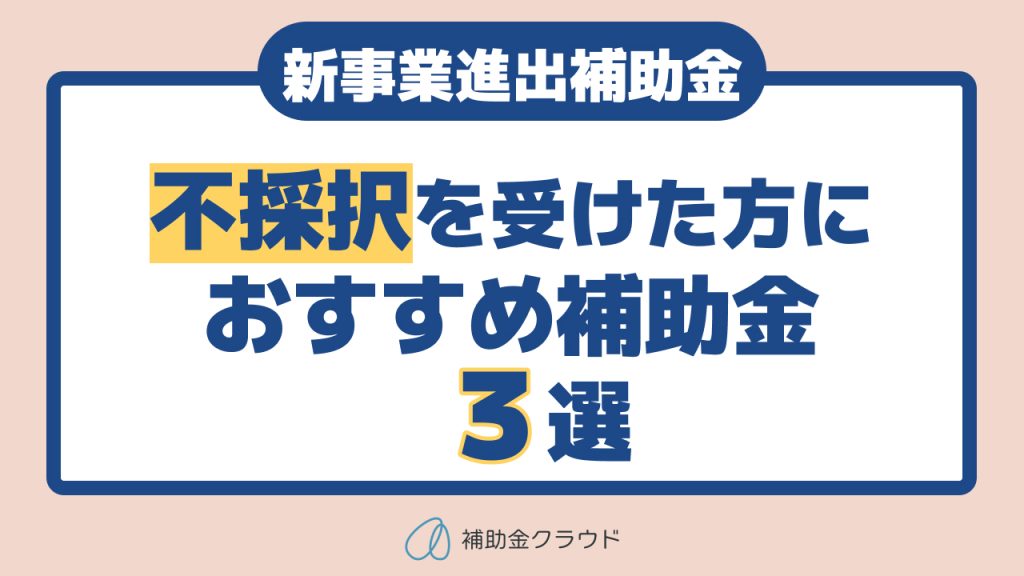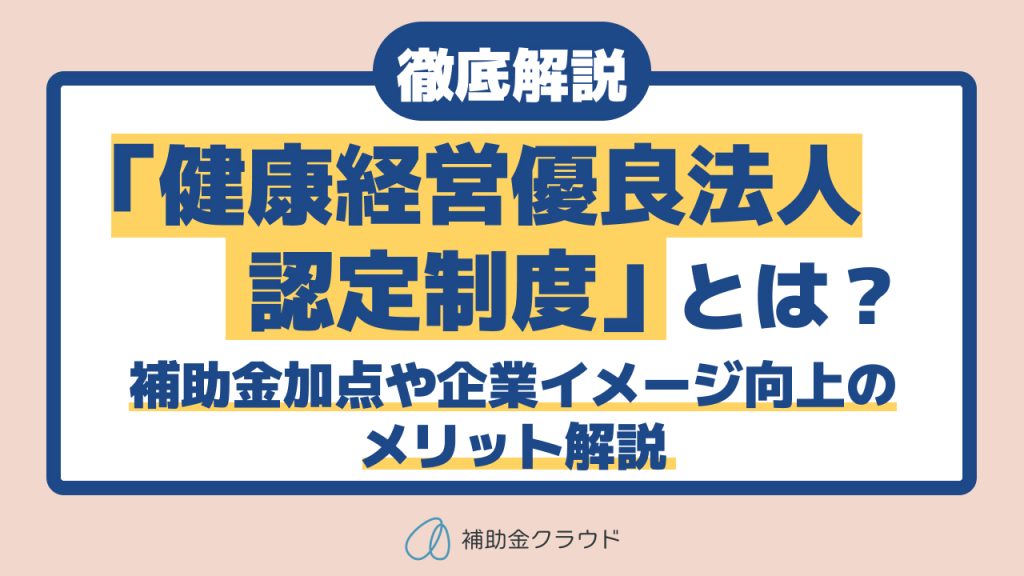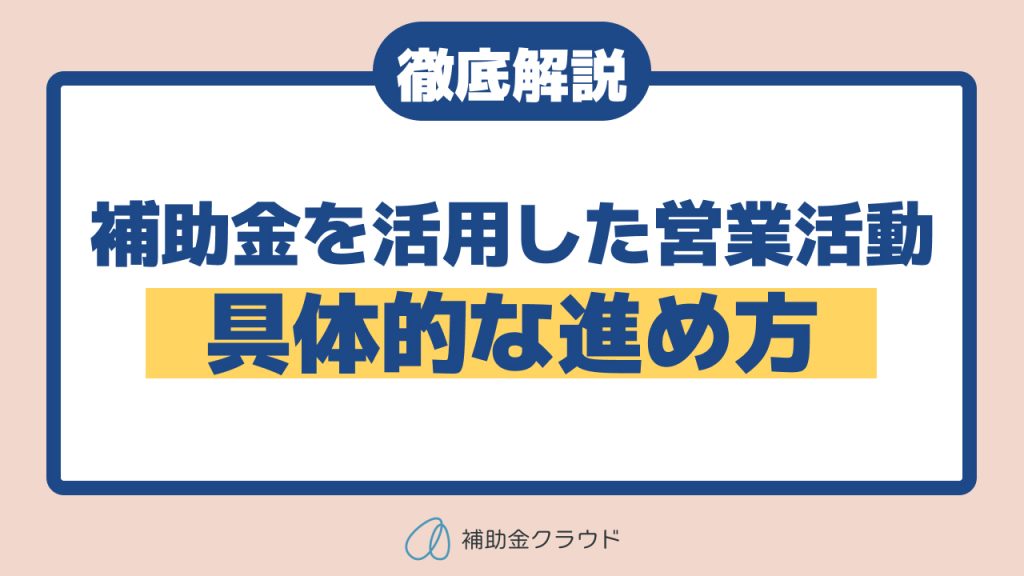公募期間:2025/11/04~2026/01/16
愛知県清須市:首都圏人材確保支援事業補助金
上限金額・助成額
0万円
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から清須市へ移住し、移住支援金対象求人に就職した方等に、国・県・清須市が共同で移住支援金を支給する制度です。
全業種
ほか