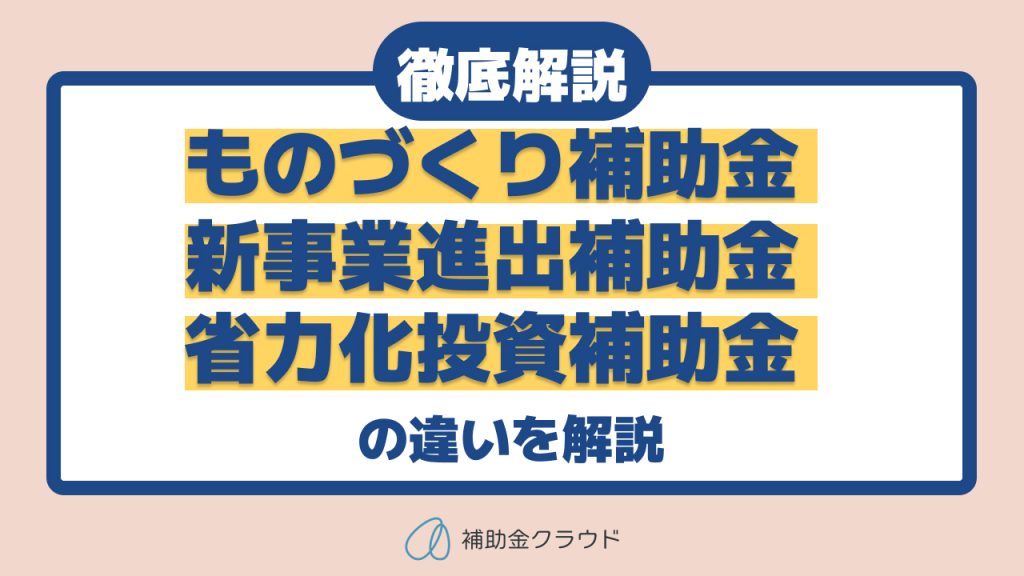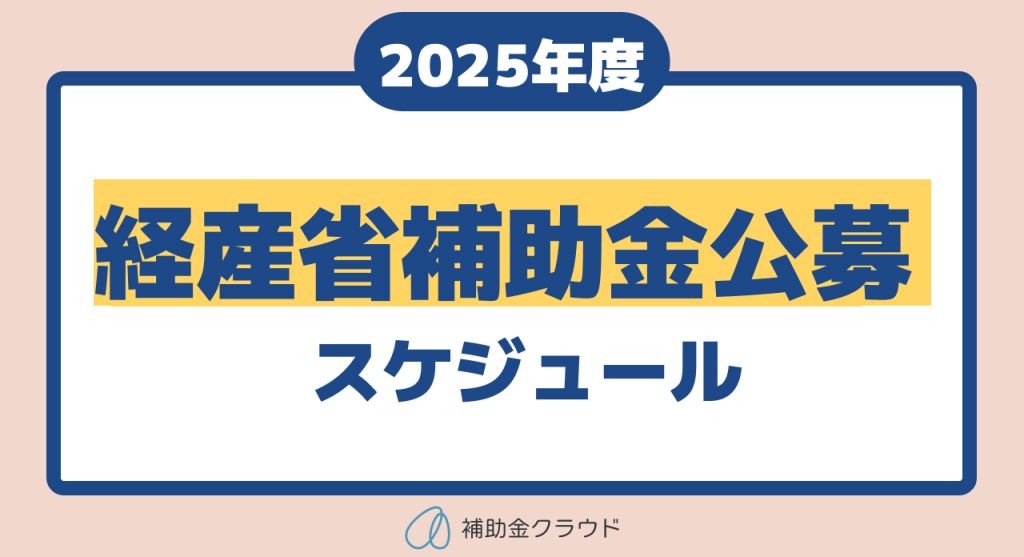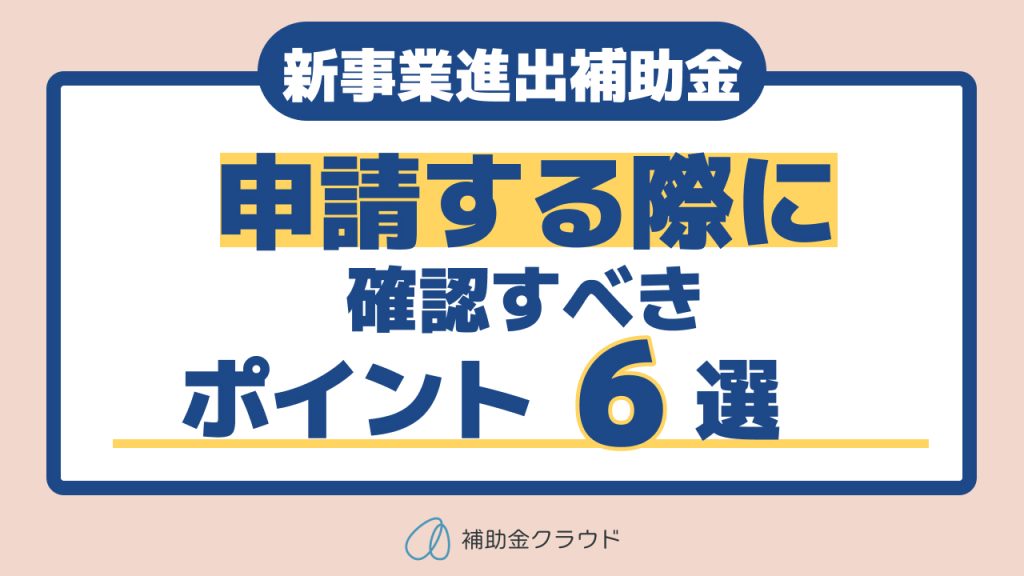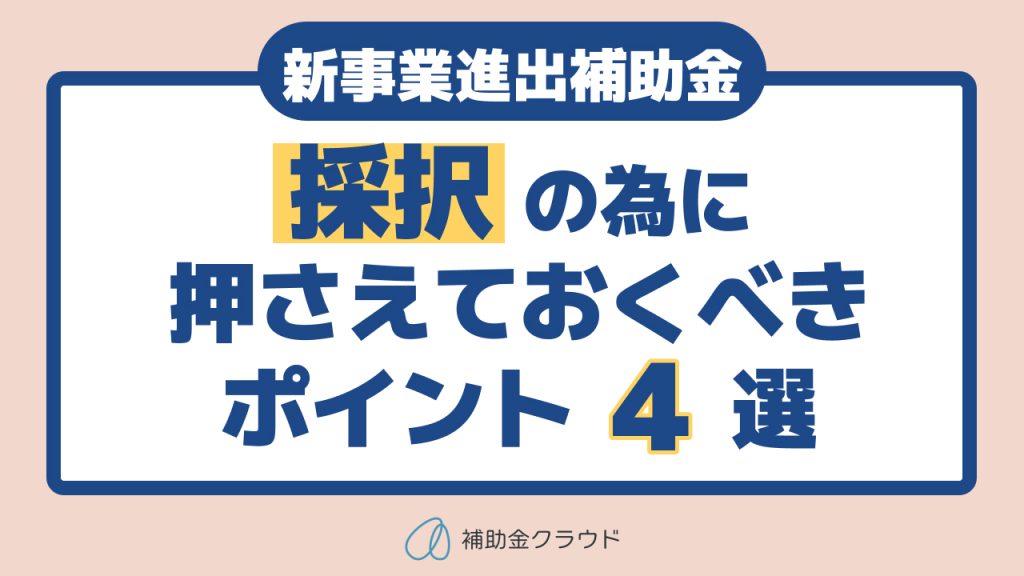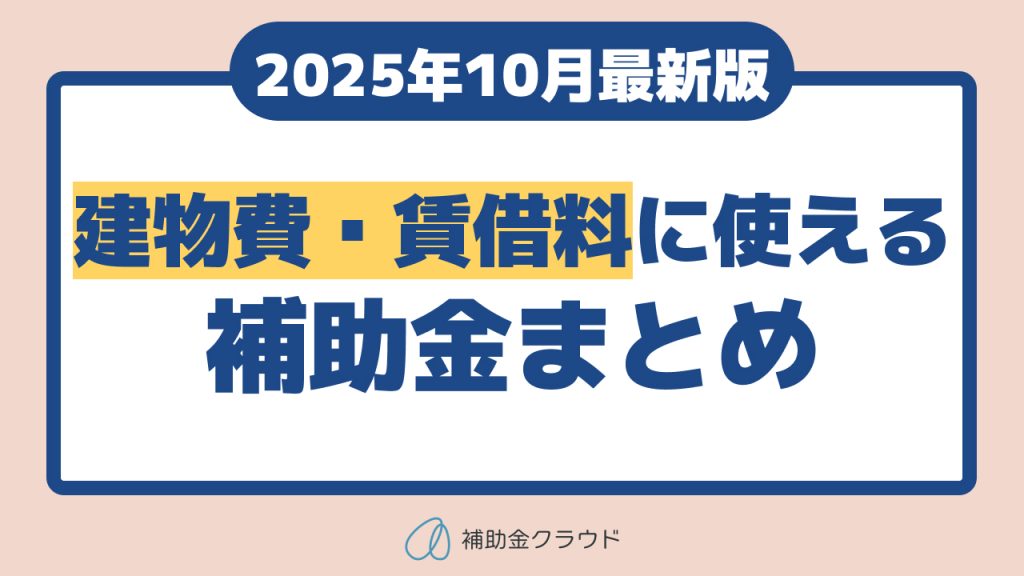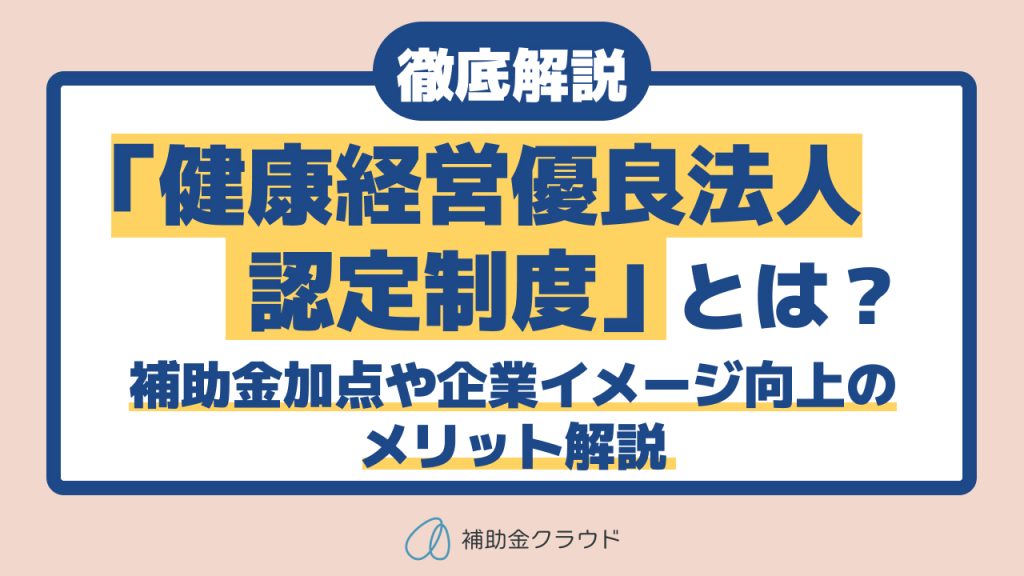米に次ぐ主要な食糧である麦については、安定供給を図る観点から国が一元的に輸入していますが、世界の麦の需給動向は、今後、ひっ迫傾向で推移することが予想されています。
このため、国全体として輸入麦の適正な備蓄水準を確保することが必要であり、農林水産省において本事業を実施することにより、食糧用輸入小麦の買受資格者による備蓄を促し、不測の事態が生じた場合においても、食糧用輸入小麦の安定供給を確保します。
全国の補助金・助成金・支援金の一覧
1641〜1650 件を表示/全2302件
本事業は、生産現場のデータを川下事業者(卸売業、食品製造業、小売業及び外食産業等)に提供する、又は川下事業者のデータを生産現場において取得するなどのデータ連携による付加価値の創出や環境に配慮した取組の見える化、輸出におけるトレーサビリティの確保等について、ukabis(SIP 第2期で開発された生産から加工、流通、販売、消費までデータの相互活用が可能なデータ連携プラットフォーム)を活用した実証の取組を支援する。
※本公募は、令和7年度政府予算案に基づくものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
※本公募は令和7年度政府予算案に基づいて行うものであるため、成立後の予算の内容により、事業内容、予算額等に変更があり得ることをあらかじめご了承の上、御応募ください。
-----
農林水産省では、大豆、麦及び飼料用米、加工用米、米粉用米その他地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下同じ。)が認める土地利用型作物 (以下「飼料用米等」という。)の生産性向上を図るため、新たな品種、作付体系、栽培技術等(以下「新技術等」という。)の導入又は大豆極多収品種の奨励品種決定調査の取組等を支援します。
本公募は、令和7年度予算により実施する事業に係るものですが、予算の成立後速やかに当該事業を実施するため、予算の成立前に行っているものです。このため、成立した予算の内容に応じて、事業内容等の変更が有り得ることに御留意ください。
-----
本事業は、土地改良事業の円滑な推進を図るとともに担い手への農地集積等に取り組む地域に対し、土地改良事業の農家の負担金の軽減と計画的償還の一層の推進に資することを目的とします。
土地改良区等への支援資金の貸付け及び助成のための計画に対し、審査委員会を開催し審査・認定を行います。
また、認定した土地改良区等に対する助成金の交付並びに支援資金の貸付け及び償還金の徴収を行います。
農林水産省では、品種育成者又は実需者が中心となり、ニーズのある輸出用米、中食・外 食向けの米、加工用米、麦・大豆等の品種の供給拡大に向けて、複数の種子場におい て種子生産の拡大を図る場合に必要となる経費や、これらに取り組む種子場が新たに 原種生産に取り組む場合に必要な機械の導入を支援します。
補助率2分の1・定額
※第1弾は既に終了しており、第2弾以降の実施については、後日国交省のHPにて公表予定です。
我が国では、商用車については、8トン以下の小型の車について、2030年までに、新車販売で電動車20~30%、2040年までに、新車販売で、電動車と合成燃料等の脱炭素燃料の利用に適した車両で合わせて100%を目指すこととしております。
国土交通省では、当該目標の達成に向け、製品のラインナップが揃い、普及段階にある事業用の電動車(ハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車)について普及段階と車両価格に応じ、購入補助を行うことにより導入を集中的な支援を実施するため、今回、下記補助対象車両等を導入する者の公募を開始します。
| 補助対象車両等 | 補助率 |
| ・電気バス | 車両本体価格の1/3 |
| ・電気タクシー、電気トラック(バン) | 車両本体価格の1/4 |
| ・燃料電池トラック | 車両本体価格の2/3 |
| ・ハイブリッドバス ・ハイブリッドトラック |
通常車両価格との差額の1/3 |
| ・電気自動車用充電設備等 | 導入費用の1/2(充電設備の工事費については実額又は上限額) ※ただし、充電装置のみの導入の場合、1/4 |
本事業は、国が建築基準の整備を促進する上で必要となる調査事項を提示し、これに基づき、基礎的なデータ・技術的知見の収集・蓄積等の調査及び技術基準の原案作成に向けた基礎資料の作成を行う民間事業者等を公募し、最も適切な調査内容、実施体制等の計画を提案した者に対して、国が支援するものです。
・一事業あたりの補助金の額は、3.1の直接経費と3.2の間接経費の合計額以内の額とし、一事業につき単年度当たり 60,000 千円を限度とします(ただし、実大実験等の大がかりな実験を必要とするテーマについては、国土交通省住宅局に設置する建築基準整備促進事業評価委員会(以下「事業評価委員会」という。)に諮り、その妥当性が了承さ
れたものに限り、補助限度額を超えて補助金を交付することができるものとします)。
東日本大震災では、広範囲にわたり停電が発生し、大規模電源に集中して依存する従来型の電力供給におけるリスクが顕在化しました。世界水準のビジネス機能・居住機能を集積し、国際的な投資と人材を呼び込むためには、我が国の大都市の弱みである災害に対する脆弱性を克服していくことが必要です。
本事業は、都市機能が集積しエネルギーを高密度で消費する地域において、災害時の業務継続の確保に資するエネルギーの面的ネットワークの整備に必要な事業費の一部に補助を行うことにより、エネルギーの自立化・多重化を図り、大都市の防災性向上の促進による国際競争力の強化を目的としています。
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、鉄道分野においてもカーボンニュートラルに関する取組を加速化させる必要があります。
令和4年8月の「鉄道分野におけるカーボンニュートラル加速化検討会」における中間とりまとめを踏まえ、鉄軌道事業等によるカーボンニュートラル実現に向けた取組を推進するため、「鉄道脱炭素施設等実装調査」に対する補助制度を創設しました。
今般、本制度による「鉄道脱炭素施設等実装調査」を実施する事業者を募集いたします。
・補助率 1/2(ただし、補助対象事業費には消費税及び地方消費税は含まない)
海洋プラスチックごみ問題など、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっており、多様な物品に使用されているプラスチックに関し、包括的な資源循環体制の強化が求められております。このことから、漁業・養殖業に由来する海洋プラスチック(漁業系廃棄物)及び漁業者が操業中に持ち帰った海洋プラスチックの資源循環を図るため、海洋プラスチックごみの分別~回収~再資源化までのサプライチェーンを構築する必要があります。このため、漁業者、自治体、企業、地域住民等が連携した漁業系廃棄物を含む海洋プラスチックごみの資源循環の取組に対して支援します。
- エリア
から検索 - 利用目的
から検索 - 業種
から検索