全国:さけ・ます広域連携体制構築推進事業
2025年2月10日
上限金額・助成額25503.3万円
経費補助率
0%
近年、我が国のさけ・ます資源は減少傾向にあり、その要因としては海洋環境の変化による、放流した稚魚の降海後の生残率の低下が大きいことが指摘されています。
資源を回復させるためには、環境変化に対応した稚魚の放流を行うことで回帰率の向上を図ることが急務と考えられます。
これまでの調査により大型種苗の生産・放流が効果的であることや、放流に適した時期・サイズに関する知見が蓄積されてきています。
このため、本事業においては放流種苗の大型化を目指した広域連携体制の構築や、これまでの知見を活用して放流効果を最大化するための河川間の連携を推進することにより、環境変化に対応した効果的な放流体制への移行を図ることを目的とし支援を行うものです。
また、先行事業で標識放流したサケが回帰することから、その放流効果を調査検証するとともに、これにより得られたふ化放流技術等の普及啓発を促進する取組についても支援を行うものです。
1 広域連携検討協議会・普及啓発
(1)広域協議会
賃金、謝金、旅費、消耗品費、その他
(2)地域協議会
賃金、謝金、旅費、消耗品費、その他
(3)ふ化放流技術の普及啓発
賃金、旅費、消耗品費、役務費、その他
2 回帰親魚調査
賃金、旅費、消耗品費、役務費、標本分析費、その他
3 さけ・ます増殖手法実証調査
(1)広域連携体制構築実証調査
種苗購入費、賃金、謝金、旅費、設備費、備品費、消耗品費、役務費、標本分析費、その他
(2)河川間の回帰率比較実証調査
種苗購入費、賃金、設備費、備品費、消耗品費、役務費、標本分析費、その他
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
放流種苗の大型化を目指した広域連携体制の構築や、これまでの知見を活用して放流効果を最大化するための河川間の連携を推進することにより、環境変化に対応した効果的な放流体制への移行を図る取組及び放流効果を調査する取組
1 広域連携検討協議会・普及啓発
(1)広域協議会
広域的なふ化放流事業の協力や調整を図るため、さけ・ますふ化放流団体の会員、関係行政機関の職員及び学識経験者等により構成される広域協議会を開催し、さけ・ます増殖手法実証調査の実施方法の調整や取組状況等の情報交換、広域的なふ化放流体制に係る検討などを行う。
(2)地域協議会
さけ・ます増殖手法実証調査等の円滑かつ的確な実施を図るため、さけ・ますふ化放流実施団体の会員、関係行政機関の職員及び学識経験者等により構成される地域協議会を開催し、補助事業の実施に係る連絡調整やさけ・ます増殖手法等に関する情報交換等を行う。
(3)ふ化放流技術の普及啓発
これまで得られたふ化放流技術の普及啓発を図るため、さけ・ますふ化放流技術に関する講習会の開催や現地研修等を行う。
2 回帰親魚調査
先行事業で標識放流した稚魚の放流効果を把握するため、地域全体の資源状況の調査と併せて、河川等に回帰したサケの年齢、標識等を調査し、その結果の取り纏め及び分析を行う。
なお、調査の結果については、広域協議会で報告することとします。
3 さけ・ます増殖手法実証調査
(1)広域連携体制構築実証調査
大型の種苗を生産するために必要な種卵の確保を通じた、広域連携体制を構築することでサケ資源の造成を図るため、広域連携体制の下で試験群を生産し、試験群の回帰率を比較検証するための種苗への標識付けや放流環境の把握を行ったうえで、それらの購入放流を行う。
(2)河川間の回帰率比較実証調査
河川間の連携により地域全体の放流効果の最大化を図るため、これまでの調査研究等の結果を踏まえた試験群を生産し、試験群の回帰率を比較検証するための種苗への標識付けや放流環境の把握を行ったうえで、それらの購入放流を行う。
2025/02/05
2025/02/20
民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とするほか、複数の民間団体等が本事業の実施のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの。以下「協定機関」という。)による提案も可とします。
■提出方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
原則として郵送、宅配便(バイク便を含む。)又は電子メールによる申請とし、やむを得ない場合には持参も可としますが、FAX による提出は受け付けません。
■提出先
〒100-8907
東京都千代田区霞が関 1-2-1
水産庁増殖推進部栽培養殖課
栽培漁業指導班
TEL:03-3502-8111(内線:6824)
※電子メールで申請する場合上記に記載される提出先に連絡してください。
〒100-8907 東京都千代田区霞が関 1-2-1 水産庁増殖推進部栽培養殖課 栽培漁業指導班 TEL:03-3502-8111(内線:6824)
近年、我が国のさけ・ます資源は減少傾向にあり、その要因としては海洋環境の変化による、放流した稚魚の降海後の生残率の低下が大きいことが指摘されています。
資源を回復させるためには、環境変化に対応した稚魚の放流を行うことで回帰率の向上を図ることが急務と考えられます。
これまでの調査により大型種苗の生産・放流が効果的であることや、放流に適した時期・サイズに関する知見が蓄積されてきています。
このため、本事業においては放流種苗の大型化を目指した広域連携体制の構築や、これまでの知見を活用して放流効果を最大化するための河川間の連携を推進することにより、環境変化に対応した効果的な放流体制への移行を図ることを目的とし支援を行うものです。
また、先行事業で標識放流したサケが回帰することから、その放流効果を調査検証するとともに、これにより得られたふ化放流技術等の普及啓発を促進する取組についても支援を行うものです。



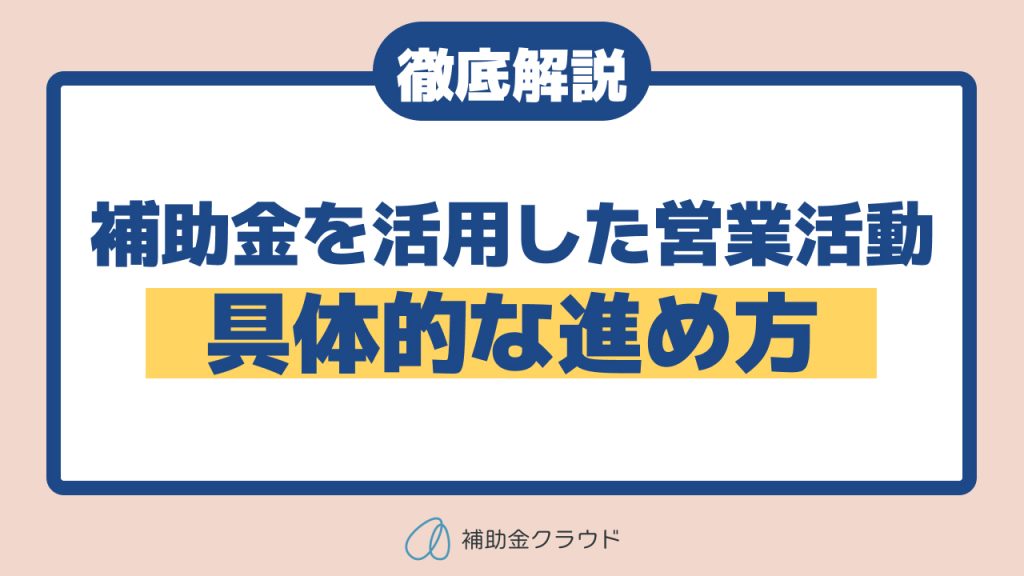
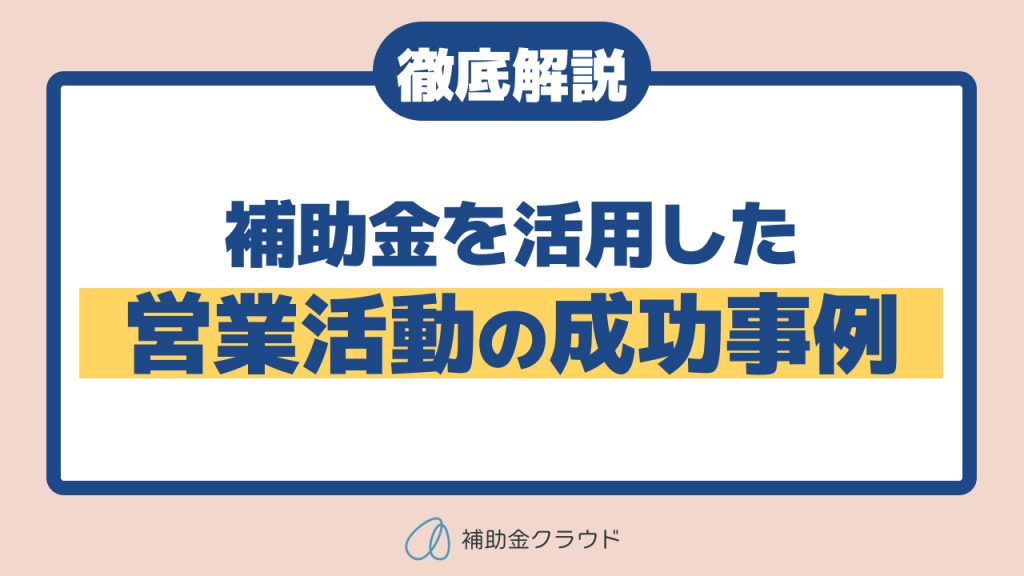
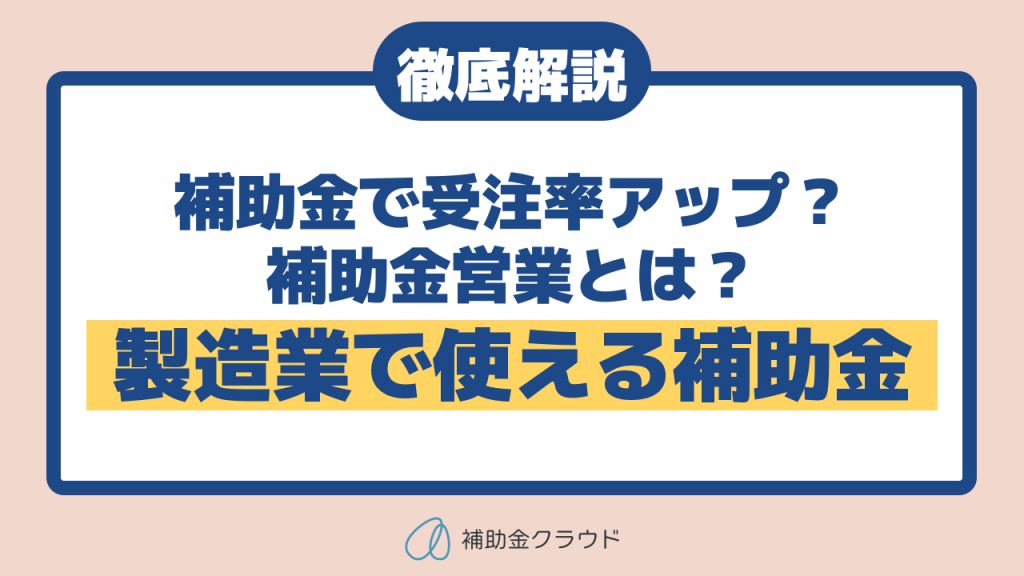
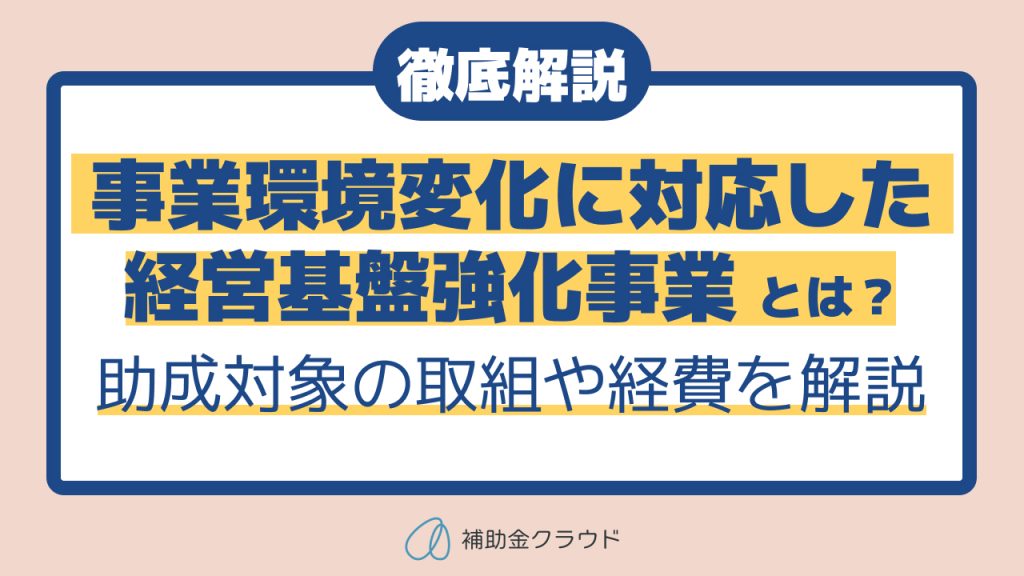
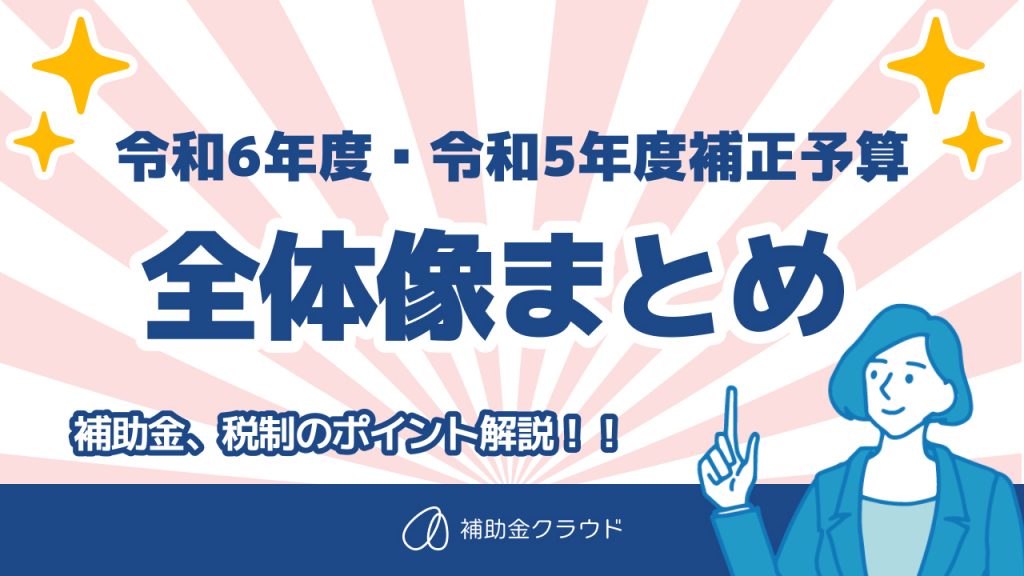
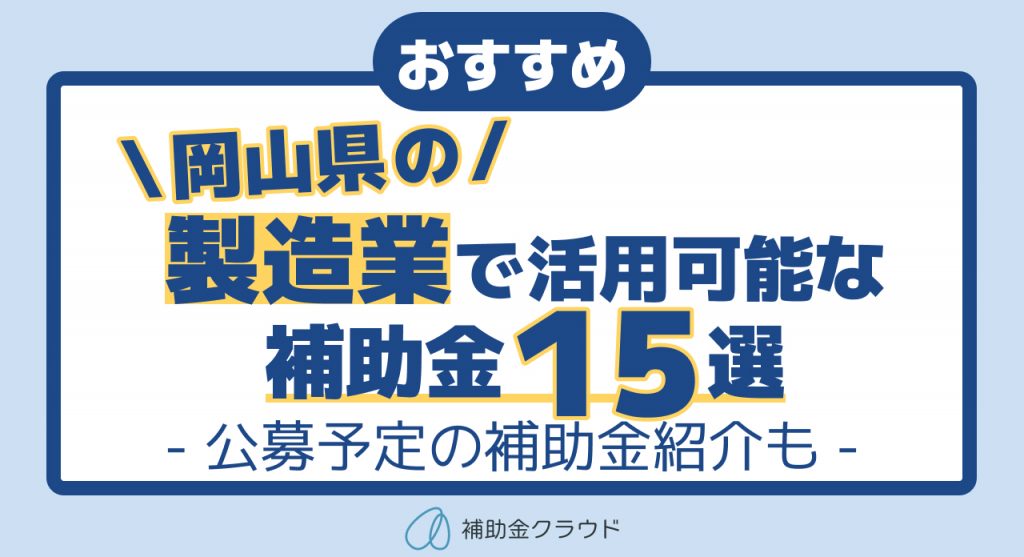


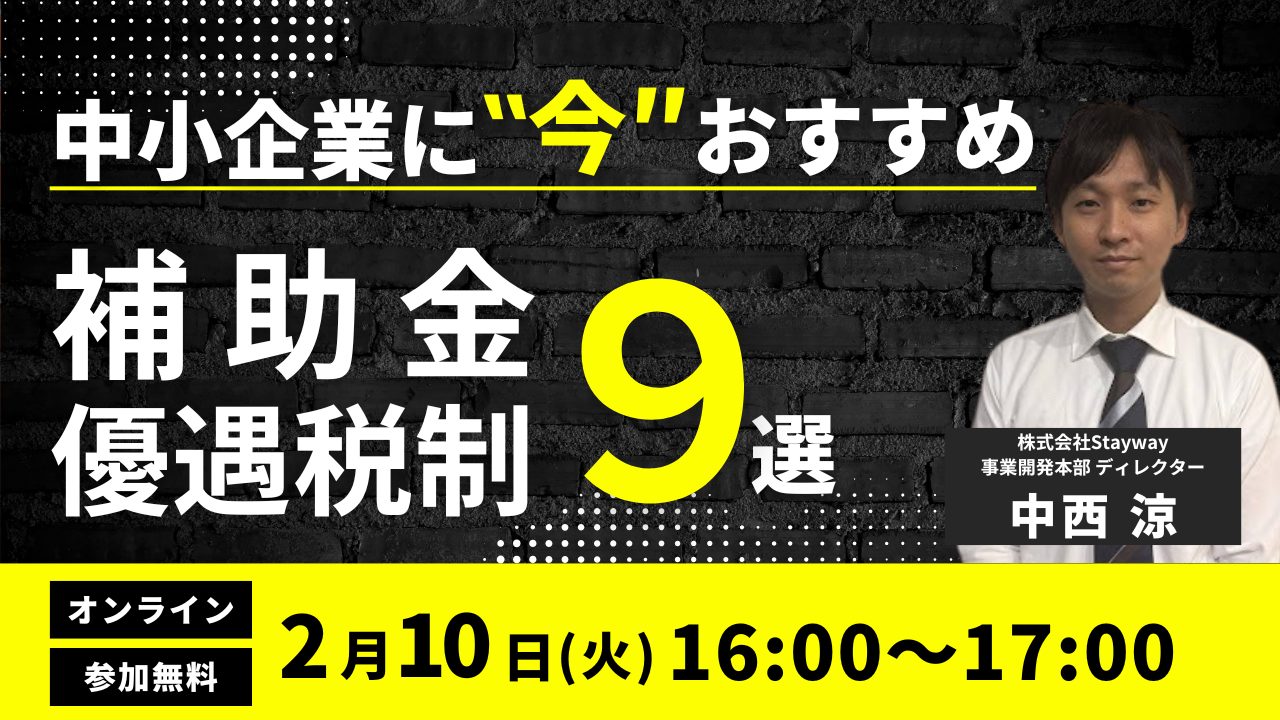


関連する補助金