全国:開発途上国・新興国等における医療技術等実用化研究事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年9月30日
開発途上国・新興国等は、日本とは異なる医療・事業環境や公衆衛生上の課題を抱えており、医療ニーズや製品に対する医療現場のニーズも日本と異なる面があります。これに対し、我が国の医療機器開発事業者は、現地の医療現場ニーズの把握や現地での製品の上市、事業化等において困難を抱えることがあります。そこで、本公募では、本事業で採択された開発事業者に対し伴走支援による製品開発・事業化の支援を行いつつ、その過程で得た知見を活かし、我が国の企業が開発途上国・新興国等に進出するプロセスの構築を行う開発サポート機関を公募します。
■直接経費
・物品費:研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
・旅費:研究参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費
・人件費:当該委託研究開発のために雇用する研究員等の人件費
・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費
・その他:上記のほか、当該委託研究開発を遂行するための経費
例)研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、不課税取引等に係る消費税相当額(委託研究開発のみ)等
■間接経費
直接経費も対して一定比率(30%上限)で手当され、当該委託研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費
■一般管理費
補助事業において直接経費に対して一定比率(10%上限)で手当され、一般管理業務に必要な経費として、AMED が支払い、研究機関が使用する経費
■委託費 ( 補助事業のみ)
研究開発課題の一部を第三者に委託する経費
委託先に対しては、事業が定める間接経費・一般管理費の率を上限に間接経費を計上することが出来ます。
国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【公募対象となる研究開発課題】
・創薬基盤の整備研究
・AI・ICT 等研究及び DX 基盤整備研究
・データ・試料のバンク整備
・疾患レジストリ・コホート研究
・調査等の解析による実態把握を目指す研究
・制度の改良・技術支援等
・ 規制科学
・研究倫理
・その他の研究開発基盤の整備研究
・その他
2025/12/26
2026/01/30
以下(1)~(6)の要件を満たす国内機関(学術機関、民間企業の研究開発部門・研究所等)に所属し、応募に係る研究開発課題について研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う能力を有する研究者(「研究開発代表者」)とします。複数の機関がコンソーシアムを形成して事業を実施する提案も認めます。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、令和 8 年 4 月 1 日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。
ただし、令和 8 年 4 月 1 日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、AMEDではスタートアップ企業等を「中小企業※の内、設立10年以内」と定義し、応募時や採択時、研究進捗確認時に、財務状況の健全性を確認していきます。
【詳細】
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関※1(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職※2、福祉職※2、指定職※2又は任期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関※3
(C) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、事業・企画部門、研究所等、その他調査機能を有する部門
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条に規定する独立行政法人、地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条に規定する地方独立行政法人及びその他特別の法律により設立された法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合※4
(H) その他 AMED 理事長が適当と認めるもの
※1 内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設をいいます。
※2 病院又は研究を行う機関に所属する者に限ります。
※3 地方公共団体の附属試験研究機関等
※4 技術研究組合法(昭和 36 年法律第 81 号)に基づく技術研究組合
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続又は交付申請等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)事業の実施中・終了後に関わらず、フォローアップ調査(実用化に向けた進展、担当者変更等)等のAMED(AMED が委託した業者を含む。)が実施する調査に回答できること。
(6)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等 AMED の求めに応じて協力できること。
(7)スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著しく脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著しく脆弱で委託研究開発契約の履行能力又は補助事業の実施能力がないと判断されると、契約締結又は交付できない場合があります。)
AMEDホームページより提案書類の様式等、必要な資料をダウンロードの上、代表機関が公募要領に従って「研究開発提案書」等を作成の上、e-Radよりご提出してください。
※ 応募にあたっては「研究開発代表者」および「研究開発分担者」が所属する研究機関がe-Radに登録されていることが必要となります。登録手続きに日数を要する場合がありますので、2週間以上の余裕をもって登録手続きをしてください。なお、一度登録が完了すれば、他省庁等が所管する制度・事業の応募の際に再度登録する必要はありません。(既に他省庁等が所管する制度・事業で登録済みの場合は再度登録する必要はありません。)
※ 全ての研究開発提案書類等について、公募期間を過ぎた場合には一切受理出来ませんのでご注意ください。
※ e-Radからの申請に際して所属機関の承認が必要です。「研究開発代表者」から所属機関にe-Radで申請した段階では応募は完了していませんので、所属機関の承認の手続きを必ず行ってください。
※ 受付期間終了時点で、「配分機関処理中申請中」又は「受理済」となっていない提案書類は無効となります。初めて申請を行う場合は、ご注意願います。
医療機器・ヘルスケア事業部 医療機器研究開発課 担当 E-mail:amed-sentan@amed.go.jp
開発途上国・新興国等は、日本とは異なる医療・事業環境や公衆衛生上の課題を抱えており、医療ニーズや製品に対する医療現場のニーズも日本と異なる面があります。これに対し、我が国の医療機器開発事業者は、現地の医療現場ニーズの把握や現地での製品の上市、事業化等において困難を抱えることがあります。そこで、本公募では、本事業で採択された開発事業者に対し伴走支援による製品開発・事業化の支援を行いつつ、その過程で得た知見を活かし、我が国の企業が開発途上国・新興国等に進出するプロセスの構築を行う開発サポート機関を公募します。




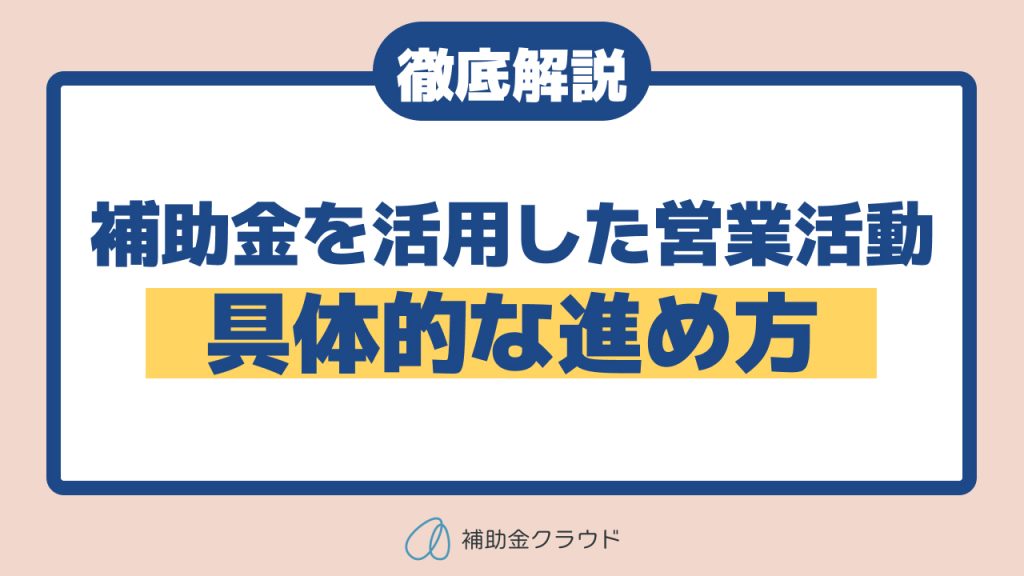
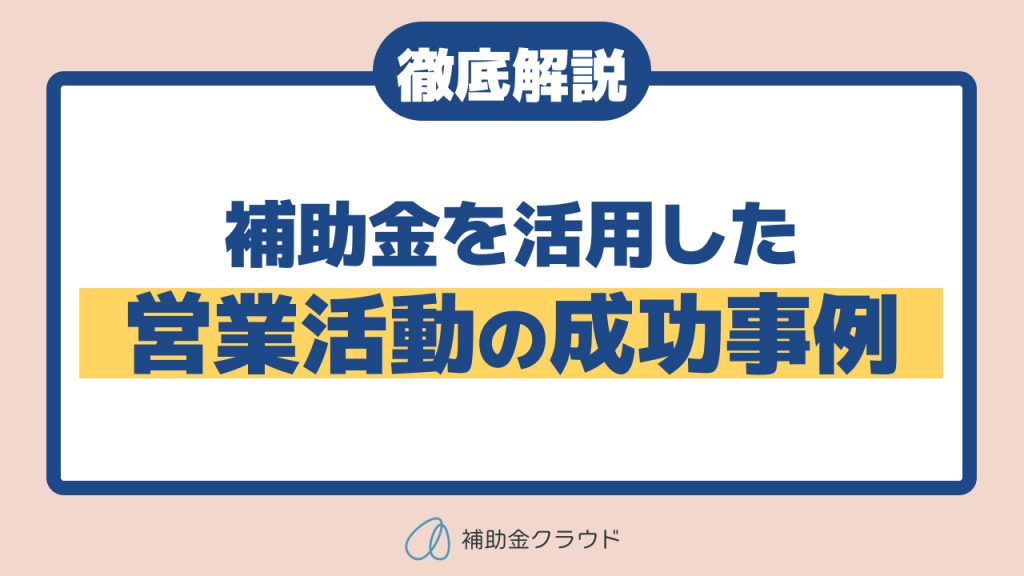
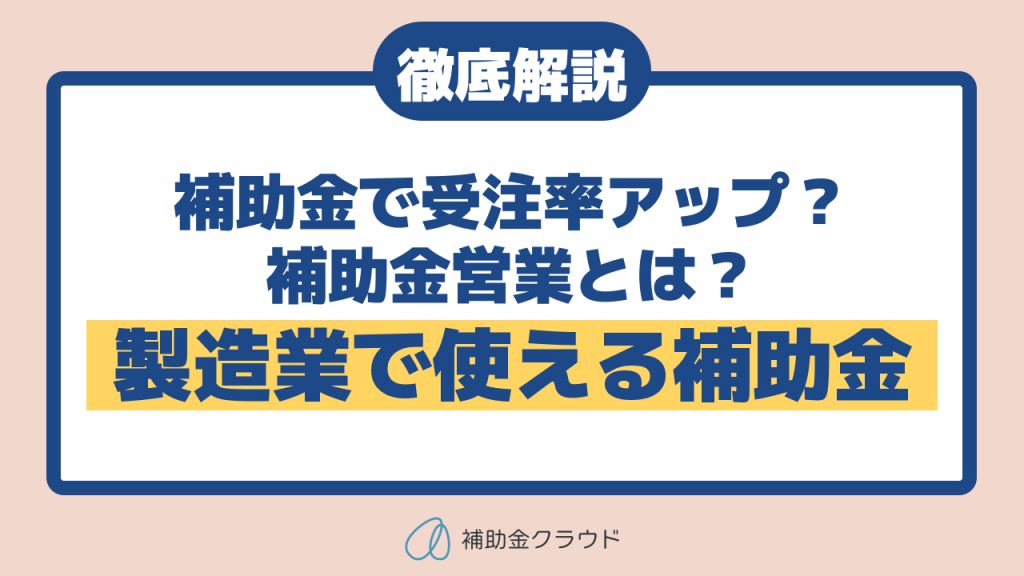
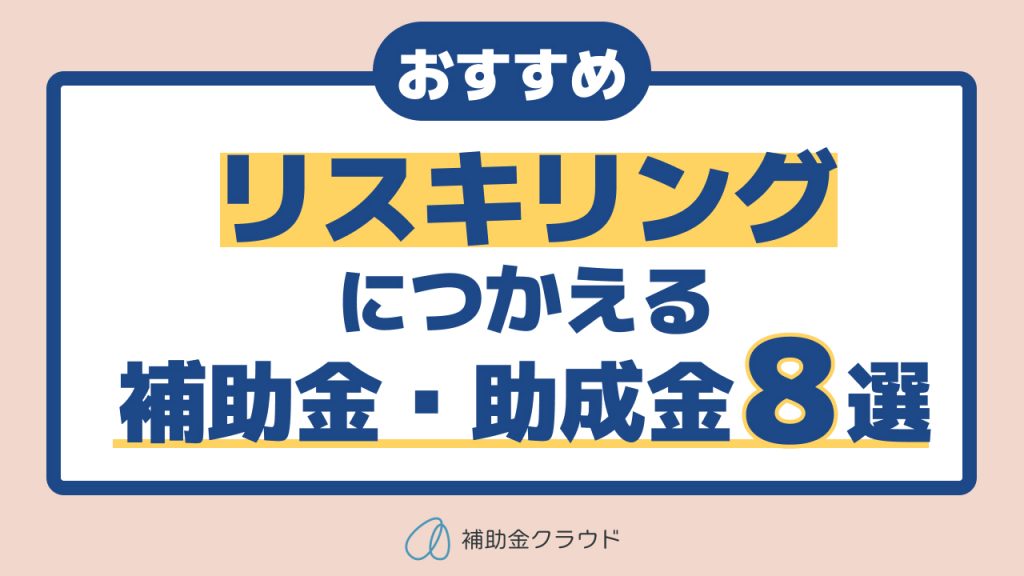
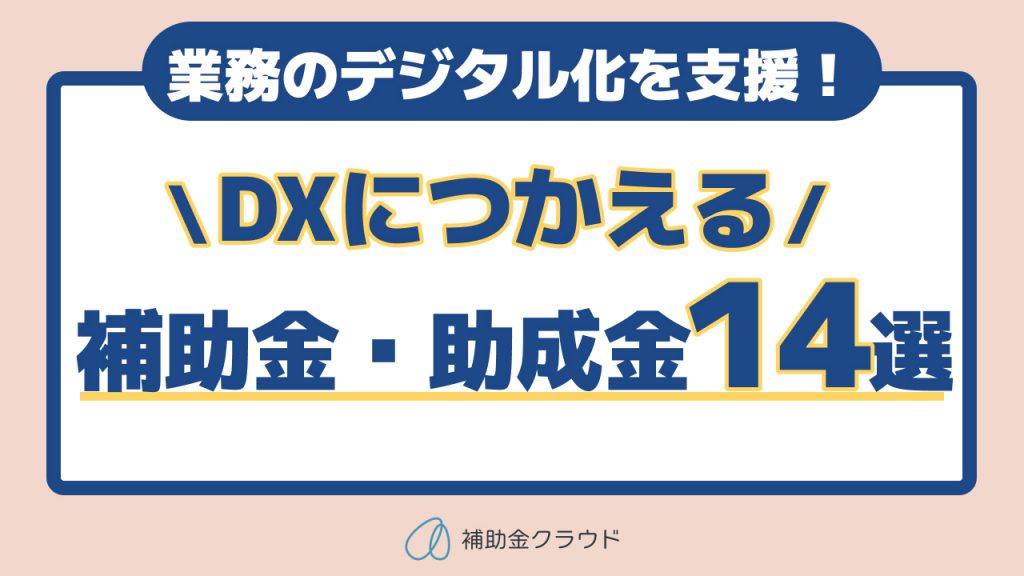
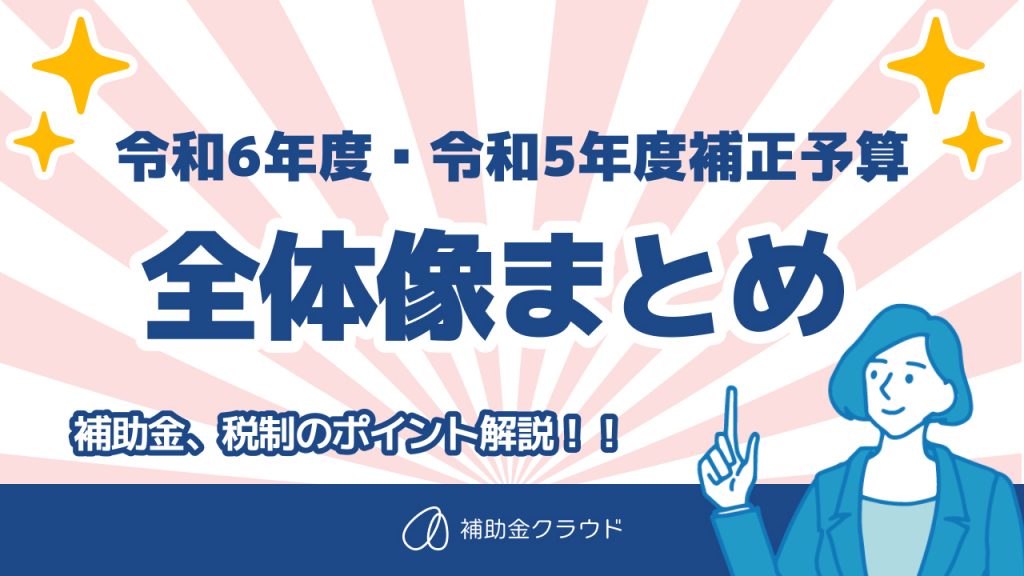


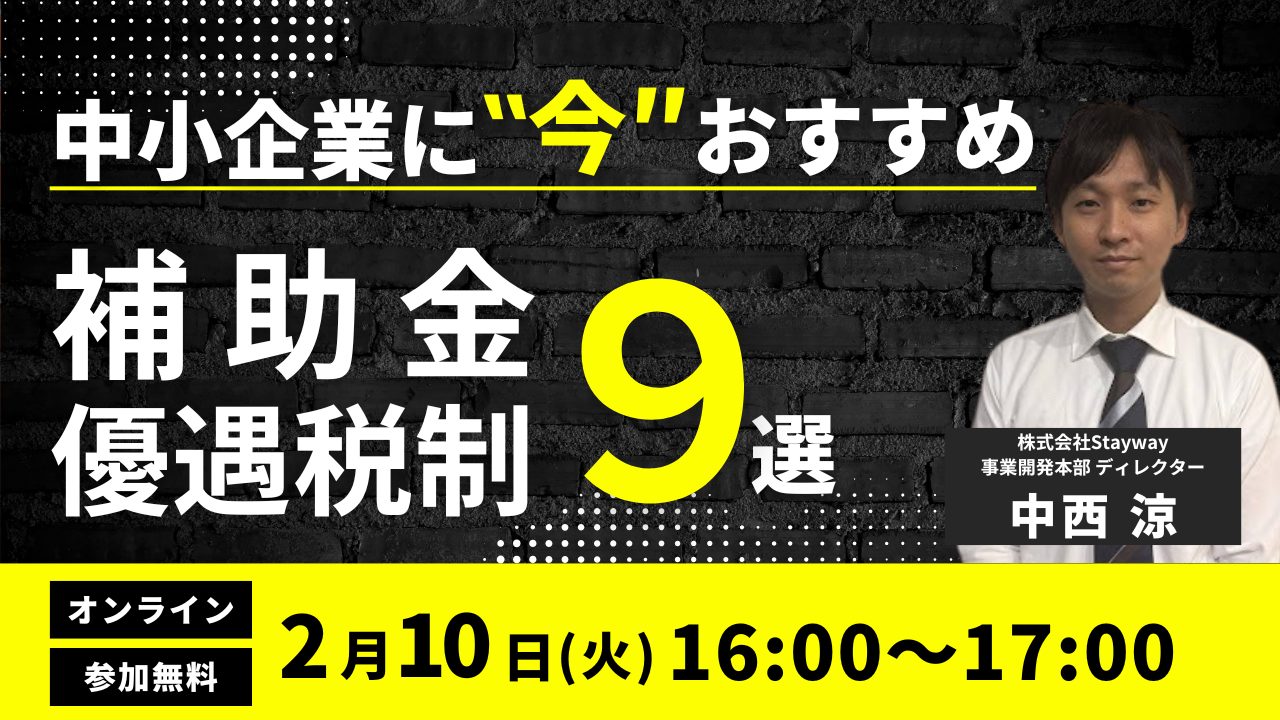


関連する補助金