橋渡し研究プログラム(preF、シーズF、シーズB、シーズC)

【補助率詳細】
■preF(非臨床 POC取得に必要な試験パッケージの策定ならびに産学協働体制の確立を目指す課題):1課題当たり年間1,000万円
■シーズF(実用化の加速のため産学協働でPOC取得を目指す課題):1課題当たり年間7,000万円、ステージゲート通過課題は3年目目以降上限9,000万円
■シーズF#(実用化の加速のため産学協働で臨床POC取得を目指し臨床試験を行う課題):1課題当たり年間9,000万円
■シーズB(非臨床 POC取得を目指す研究開発課題):1課題当たり年間5,000万円
■シーズC (臨床 POC取得を目指す臨床研究課題)
(a)臨床試験に向けた準備・臨床試験を行う課題:1課題当たり年間1,000万円、ステージゲート通過課題は2年度目以降8,000万円
(b)臨床試験を行う課題:1課題当たり年間8,000万円
≪引用元:公募要領p.5(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等について)参照≫
【対象経費】
■直接経費
・物品費 研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
・旅費 研究参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費
・人件費:当該研究開発のために雇用する研究員等の人件費(研究力向上のための制度(PI人件費)を含む。)
・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費
・その他 上記のほか、当該研究開発を遂行するための経費
例) 拠点支援費用、研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等
■間接経費
・直接経費に対して一定比率(30%上限)で手当され、当該研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費
≪引用元:公募要領p.63(Ⅱ-4.2.1 研究開発費の範囲 )参照≫
(1)対象
関連特許出願済み*で、治験等開始に必須な非臨床試験の項目確定等を目指す研究開発課題を対象とします。
*知財戦略上の理由により本公募への応募時点で特許出願をしていない場合を含む。その場合には、特許出願していない理由を説明すること。
(2)求められる成果
・導出や実用化に向けた企業との連携体制の構築
・治験等開始に必須な非臨床試験実施項目の確定(研究期間内に対面助言を終了)
・臨床性能試験開始の準備完了(体外診断用医薬品等の場合)
・シーズFへのステージアップ
(3)応募時に満たすべき条件
・治験等開始に必須な非臨床試験の項目についてのレギュラトリーサイエンス戦略相談(対面助言)を、研究開発実施予定期間内に受けるための蓋然性の高い研究計画及び開発計画が立てられてい
ること。
・企業との連携を行うための計画が立てられていること
・課題を支援する橋渡し拠点のプロジェクトマネージャーを指定すること
・各年度における四半期毎のマイルストーンと、予定通り進捗しない場合の対応策を示すこと。
シーズF
(1)対象
関連特許出願済み、かつ開発にあたって企業連携が確立しており、企業の参画を得て最長 5 年度以内に産学協働で下記の目標への到達を目指す研究開発課題を対象とします。
・非臨床POC取得及び治験届提出後、臨床POC取得を目指す医薬品及び医療機器等の研究開発課
題、又は薬事申請用臨床データ取得を目指す体外診断用医薬品等の研究開発課題
・上記に加え、医療への適応のため早期・戦略的な企業への導出を目指す研究開発課題
(2)求められる成果
・支援開始後2年度目終了時(ステージゲート)までに治験準備完了、後半ステージに向けた企業リソースのさらなる充実の準備
・ステージゲート通過後3年度以内に臨床POC取得、製販企業導出
(3)応募時に満たすべき条件
開発方針と必要な試験が明確になっていることを前提として、応募時に以下の条件を満たしていることとします。
・大学等と企業※の共同提案であり、シーズを有する大学等と実用化・事業化の主体となる企業との役割分担が明確で、シーズの臨床使用と検証が可能となる研究開発体制が構築されていること。
・企業連携について、以下の①②のいずれかを満たし、「連携企業及び導出予定先企業における
引き受け後の開発方針」について具体的な記載があること。
①「製造販売を担当する企業への導出に関する交渉状況」について、「有(内諾含む)」となっていること。
②「企業等からの技術協力」、「試験実施上の連携状況」、「資金面等での協力」について、原則全て「有」になっていること。これらの項目について、「無」の場合は合理的な理由を記載すること。
・以下の担当者を設置すること。
-研究開発代表者:参加する研究機関(大学等又は企業)から1名選出する。 -プロジェクトマネージャー:課題を支援する橋渡し拠点の担当者を指名する
-実用化担当者:橋渡し拠点と連携企業それぞれに、実用化促進に向けた計画策定・遂行を担う責任者を選出する。橋渡し拠点の実用化担当者はプロジェクトマネージャーと同一でも良い。
・連携企業は大学等との役割分担を明確化した上で、自らも研究開発を実施すること。
連携企業には、全研究開発期間を通じて企業規模及び AMED が支援する研究開発費の額に応じた企業リソースの負担を求める。
提案時には企業リソースを金銭的に換算した額、換算できない活動に対してはその具体的な内容について記述すること。
・連携企業が効率的・効果的な研究開発を実施可能な技術的基盤、人員、経営基盤を有していること。
・PMDA が実施するレギュラトリーサイエンス戦略相談(対面助言)で非臨床試験の試験内容の合意を得ており、PMDA作成による議事録の写し及び別紙(相談内容)を提出すること。
・提出した対面助言の議事録(対面助言を実施していない場合は、実用化に向けた戦略等)に基づいて決定された試験パッケージ(治験等開始前に評価が必要な項目)を提示すること。また、そ
れらのうち本研究開発課題で実施する試験の範囲を明確にし、各試験の実施費用の内訳について見積書をもって提示すること。
・支援開始2年度目終了時のステージゲートの時点において、以下の条件を全て満たすことが可能な研究計画が立てられていること。
①PMDA が実施するレギュラトリーサイエンス戦略相談(対面助言)で臨床試験の試験内容の合意を得ており、PMDA作成による議事録の写し及び別紙(相談内容)を提出すること。
②ステージゲート通過後速やかに(概ね 2 か月以内)倫理審査の申請ができる準備が済んでいること(令和9年度早期に治験を開始すること)。
③治験製品の製造工程においてバリデーションを完了していること。
④実施する医師主導治験等の実施候補施設を選定し、症例組入れの具体的な方策と組入れのスケジュールを示すこと。
⑤ステージゲート通過後、研究開発実施期間内に治験終了、製販企業導出を実現出来る計画が立てられていること。研究開発実施期間内に治験の観察期間まで終了しない場合の対応策を提示すること。
⑥後半ステージでの AMED が支援する研究開発費の増額に応じて、連携企業は企業リソースの提供をさらに充実させる準備ができていること。提案時には、研究開発の進展に応じた企業
■シーズF#
(1)対象
関連特許出願及び非臨床POC取得済み、かつ開発にあたって企業連携が確立しており、企業の参画を得て最長 3 年度以内に産学協働で下記の目標への到達を目指す研究開発課題を対象とします。ただし、研究開発期間内に治験又は臨床試験の観察期間終了(Last Patient Out)まで終了できる研究開発課題とします。
・臨床POC取得を目指す医薬品及び医療機器等の研究開発課題
・上記に加え、医療への適応のため早期・戦略的な企業への導出を目指す研究開発課題
(2)求められる成果
臨床POC取得、製販企業導出
(3)応募時に満たすべき条件
開発方針と必要な試験が明確になっていることを前提として、応募時に以下の条件を満たしていることとします。
・大学等と企業の共同提案であり、シーズを有する大学等と実用化・事業化の主体となる企業との役割分担が明確で、シーズの臨床使用と検証が可能となる研究開発体制が構築されていること。
・企業連携について、以下の①②のいずれかを満たし、「連携企業及び導出予定先企業における引き受け後の開発方針」について具体的な記載があること。
①「製造販売を担当する企業への導出に関する交渉状況」について、「有(内諾含む)」となっていること。
②「企業等からの技術協力」、「試験実施上の連携状況」、「資金面等での協力」について、原則全て「有」になっていること。これらの項目について、「無」の場合は合理的な理由を記載すること。
・以下の担当者を設置すること。
- 研究開発代表者:参加する研究機関(大学等又は企業)から1名選出する。
- プロジェクトマネージャー:課題を支援する橋渡し拠点の担当者を指名する。 - 実用化担当者:橋渡し拠点と連携企業それぞれに、実用化促進に向けた計画策定・遂行を担う責任者を選出する。橋渡し拠点の実用化担当者はプロジェクトマネージャーと同一でも良い。
・連携企業は大学等との役割分担を明確化した上で、自らも研究開発を実施すること。
連携企業には、全研究開発期間を通じて企業規模及び AMED が支援する研究開発費の額に応じた企業リソースの負担を求める。 提案時には企業リソースを金銭的に換算した額、換算できない活動に対してはその具体的な内容について記述すること。
・連携企業が効率的・効果的な研究開発を実施可能な技術的基盤、人員、経営基盤を有していること。
・PMDAが実施するレギュラトリーサイエンス戦略相談(対面助言)で臨床試験の試験内容の合意を得ており、PMDA作成による議事録の写し及び別紙(相談内容)を提出すること。
・採択後速やかに(概ね2か月以内)倫理審査の申請ができる準備が済んでいること(令和7年度早期に治験を開始すること)。著しく遅れる場合においては、必要に応じ臨時のヒアリングや課題評価委員会を行った上で支援中止等の判断を行うことがある。
・治験製品の製造工程においてバリデーションを完了していること。
・実施する医師主導治験等の実施候補施設を選定し、症例組入れの具体的な方策と組入れのスケジュールを示すこと。
・研究開発実施期間内に臨床 POC 取得、製販企業への導出を達成するための蓋然性の高い研究計画(製販企業との導出交渉の終了を含む)を有する課題であること。
・各年度における四半期毎のマイルストーンと、予定通り進捗しない場合の対応策を示すこと。
■シーズB
(1)対象
関連特許出願済みで、最長3年度以内に下記のいずれかの目標への到達を目指す研究開発課題を対象とします。申請時点での企業連携は必須ではありませんが、研究開発期間中に企業との連携を行うことを目指した計画が立てられている課題とします。希少疾患など、研究開発の一定の段階までは企業が関与しにくいシーズについては、その理由を提案書に記載の上応募することとし、理由は審査の際に考慮されます。
・非臨床POC取得及び治験届提出を目指す医薬品及び医療機器等の研究開発課題
・薬事申請用臨床データ取得を目指す体外診断用医薬品等の研究開発課題
(2)求められる成果
治験等を行うのに必要な非臨床POCの取得、シーズF#又はCへのステージアップ、企業導出 等
(3)応募時に満たすべき条件
開発方針と必要な試験が明確になっていることを前提として、応募時に以下の条件を満たしていることとします。
・PMDA が実施するレギュラトリーサイエンス戦略相談(対面助言)で非臨床試験の試験内容の合意を得ており、PMDA 作成による議事録の写し及び別紙(相談内容)を提出すること
・提出した対面助言の議事録(対面助言を実施していない場合は実用化に向けた戦略等)に基づいて決定された試験パッケージ(治験等開始前に評価が必要な項目)を提示すること。また、それらのうち本研究開発課題で実施する試験の範囲を明確にし、各試験の実施費用の内訳について見積書をもって提示すること。
・研究開発期間終了時点において、非臨床POC取得が可能な研究計画が立てられていること。
・申請時点で企業連携が無しの場合は、研究開発の一定の段階まで企業が関与しにくい理由を研究開発提案書に記載の上、支援期間中に企業との連携を行うための詳細な計画が立てられていること。また、支援期間中に企業と対話できる場に参画する計画を示すこと。
・課題を支援する橋渡し拠点のプロジェクトマネージャーを指定すること。
・各年度における四半期毎のマイルストーンと、予定通り進捗しない場合の対応策を示すこと。
■シーズC(a):臨床試験に向けた準備・臨床試験を行う課題
(1)対象
関連特許出願及び非臨床 POC 取得済みで、治験等開始を目指して原則1年度以内に臨床試験の準備を完了し、その後最長3年度以内に下記の目標への到達を目指す研究開発課題を対象とします。
ただし、研究開発期間内に治験又は臨床試験の観察期間終了(Last Patient Out)まで終了できる研究開発課題とします。
・健常人又は患者を対象とし、臨床POC取得を目指す医薬品等の研究開発課題
・治験又は性能試験を行い、承認・認証を目指す医療機器等の臨床研究開発課題
(2)求められる成果
・支援開始1年度目終了時(ステージゲート)までに治験製品の製造や臨床試験実施の体制整備等、医師主導治験等の準備完了
・ステージゲート後、研究期間終了までに臨床POC取得、企業導出、薬事承認・認証 等
(4)応募時に満たすべき条件
開発方針と治験等の内容が明確になっていることを前提として、応募時に以下の条件を満たしていることとします。
・支援開始1年度目終了時に設定予定のステージゲートの時点において、下記の条件を満たすための蓋然性の高い研究計画を有する課題であること。
①PMDA が実施するレギュラトリーサイエンス戦略相談(対面助言)で臨床試験の試験内容の合意を得ており、PMDA 作成による議事録の写し及び別紙(相談内容)を提出すること。
②ステージゲート通過後速やかに(概ね 2 か月以内)倫理審査の申請ができる準備が済んでいること(令和8 年度早期に治験を開始すること)。著しく遅れる場合においては、必要に応じ臨時のヒアリングや課題評価委員会を行った上で支援中止等の判断を行うことがある。
③治験製品の製造工程においてバリデーションを完了していること。
④実施する医師主導治験等の実施候補施設を選定し、症例組入れの具体的な方策と組入れのスケジュールを示すこと。
⑤本研究開発課題で実施する医師主導治験等の実施費用の内訳(橋渡し拠点及び臨床研究中核病院の支援料を含む)について見積書をもって提示すること。
⑥申請時点で企業連携が無しの場合は、支援期間中に企業との連携を行うための詳細な計画が立てられていること。また、支援期間中に企業と対話できる場に参画する計画を示すこと。
・課題を支援する橋渡し拠点のプロジェクトマネージャーを指定すること。
・各年度における四半期毎のマイルストーンと、予定通り進捗しない場合の対応策を示すこと。
特に、研究開発実施期間内にLast Patient Outまで終了する計画を提示し、進捗に遅延が見られた場合、誰がどのように管理し対応するか明確にした上で、万一期間内に終わらない場合の対応策を提示すること。
■シーズC(b):臨床試験を行う課題(臨床試験に向けた準備が整っている課題)
(1)対象
関連特許出願及び非臨床 POC 取得済みで、最長 3 年度以内に下記の目標への到達を目指す研究開発課題を対象とします。ただし、研究開発期間内に治験又は臨床試験の観察期間終了(Last Patient Out)まで終了できる研究開発課題とします。
・健常人又は患者を対象とし、臨床POC取得を目指す医薬品等の研究開発課題
・治験又は性能試験を行い、承認・認証を目指す医療機器等の臨床研究開発課題
(2)求められる成果
臨床POC取得、企業導出、薬事承認・認証 等
(3)応募時に満たすべき条件
開発方針と治験等の内容が明確になっていることを前提として、応募時に以下の条件を満たしていることとします。
・PMDA が実施するレギュラトリーサイエンス戦略相談(対面助言)で臨床試験の試験内容の合意を得ており、PMDA作成による議事録の写し及び別紙(相談内容)を提出すること。
・採択後速やかに(概ね契約後 2 か月以内)倫理審査の申請ができる準備が済んでいること(令和7 年度早期に治験を開始すること)。著しく遅れる場合においては、必要に応じ臨時のヒアリングや課題評価委員会を行った上で支援中止等の判断を行うことがある。
・治験製品の製造工程においてバリデーションを完了していること。
・実施する医師主導治験等の実施候補施設を選定し、症例組入れの具体的な方策と組入れのスケジュールを示すこと。
・本研究開発課題で実施する医師主導治験等の実施費用の内訳(橋渡し拠点及び臨床研究中核病院の支援料を含む)について見積書をもって提示すること。
・申請時点で企業連携が無しの場合は、支援期間中に企業との連携を行うための詳細な計画が立てられていること。また、支援期間中に企業と対話できる場に参画する計画を示すこと。
・課題を支援する橋渡し拠点のプロジェクトマネージャーを指定すること。
・各年度における四半期毎のマイルストーンと、予定通り進捗しない場合の対応策を示すこと。
特に、研究開発実施期間内にLast Patient Out まで終了する計画を提示し、進捗に遅延が見られた場合、誰がどのように管理し対応するか明確にした上で、万一期間内に終わらない場合の対応策を提示すること。
≪引用元:公募要領p.10-17(2.2公募対象となる研究開発課題の概要について)参照≫
橋渡し研究支援機関:北海道大学、東北大学、筑波大学、国立がん研究センター、東京大学、慶應義塾、藤田学園、名古屋大学、京都大学、大阪大学、岡山大学、九州大学
応募資格者(橋渡し研究支援機関)を通じて応募するシーズの研究開発代表者は、以下(1)~(5)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日まで、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。ただし、契約締結日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、AMED ではスタートアップ企業等を「中小企業※の内、設立10 年以内」と定義し、応募時や採択時、研究進捗確認時に、財務状況の健全性を確認していきます。※中小企業の定義は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)の定めるところによります。
なお、分担研究機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約時に必要な条件を満たすか確認が必要になります。分担研究機関は、代表研究機関と再委託研究開発契約を締
結します。 所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途ご相談ください。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職、福祉職、指定職又は任期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関
(C) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人及びその他特別の法律により設立された法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合
(H) その他AMED理事長が適当と認めるもの
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。
(6)スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著しく脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著しく脆弱で委託研究開発契約の履行能力がないと判断されると、契約締結できない場合があります。)
≪引用元:公募要領p.21(3.1応募資格者)参照≫
提案書類受付期間 :令和6年12月27日(金)~令和7年1月23日(木)【午前11時】(厳守)
書面審査 :令和7年2月上旬~令和7年2月下旬(予定)
ヒアリング審査 :
preF:令和7年3月12日(水)、 14日(金)
シーズF、シーズB:令和7年3月21日(金)
シーズF#、シーズC:令和7年3月17日(月)
採択可否の通知 :令和7年4月中旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日 :令和7年5月下旬(予定)



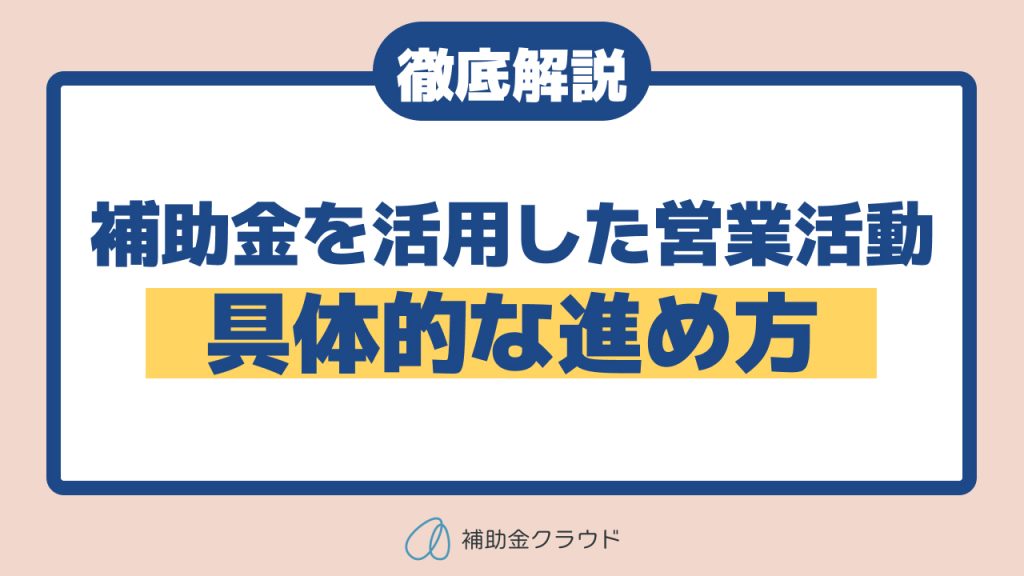
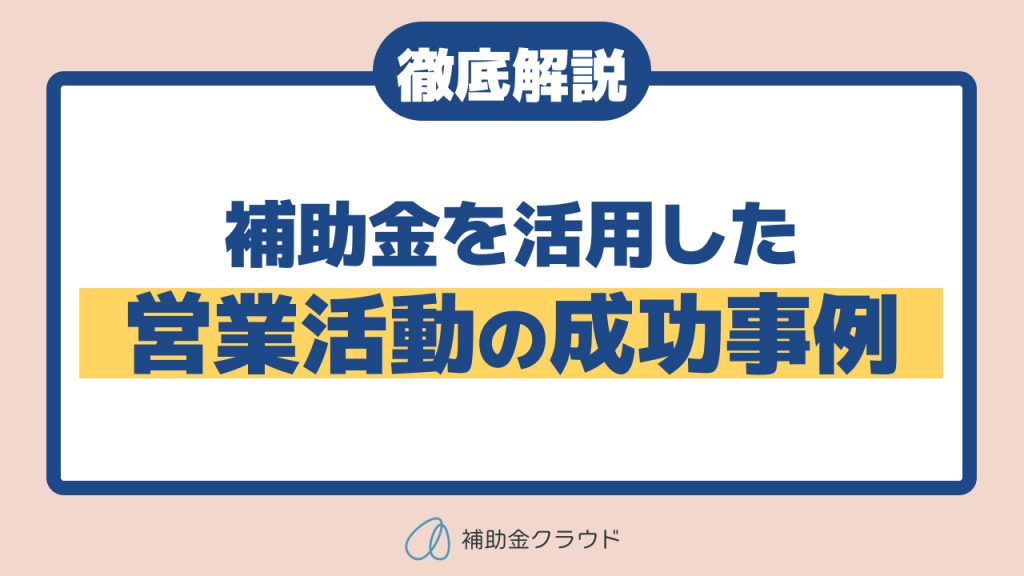
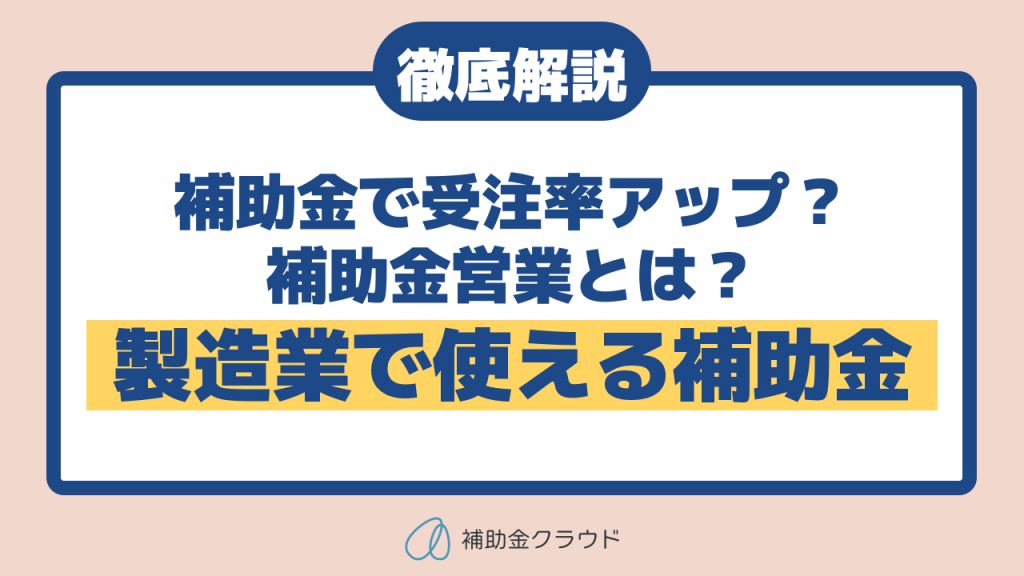
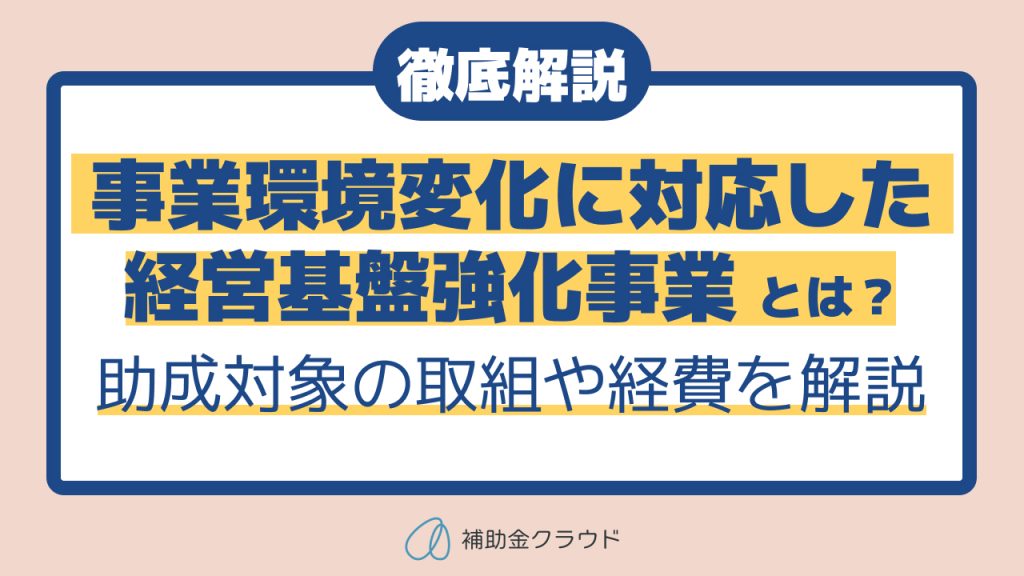
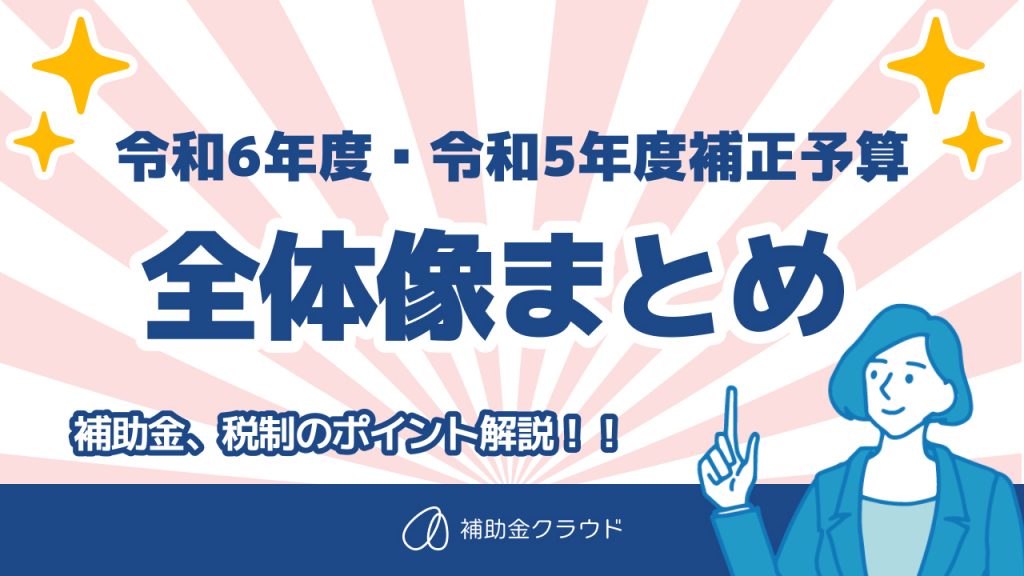
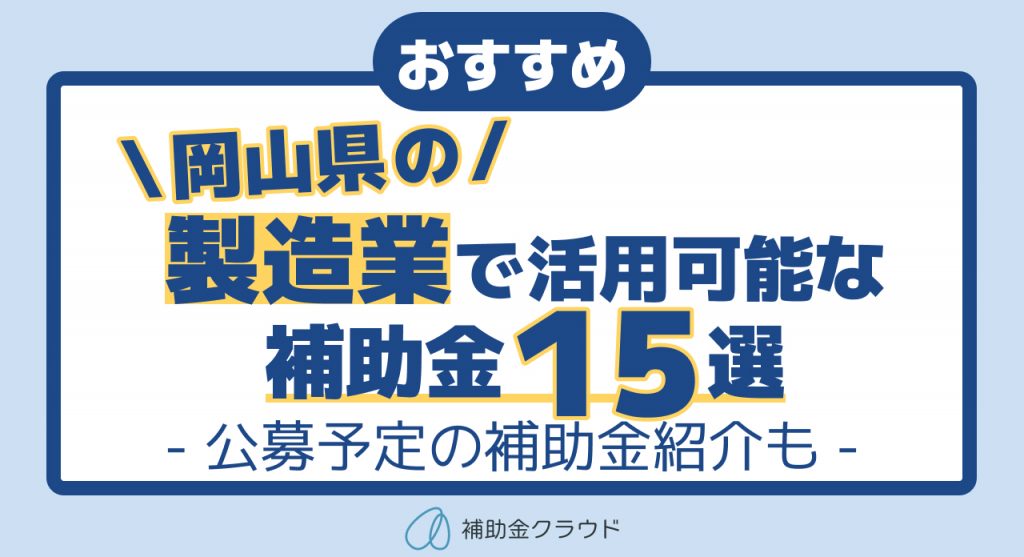





関連する補助金