創薬基盤推進研究事業(3次)

【補助率詳細】
• 創薬技術の創出研究(1-1 医薬品開発の進展に資する評価技術の高度化研究、1-2 革新的医薬品創出に資する基盤技術の高度化研究): 1課題あたり年間 2,000万円(上限)
• 医療情報等に基づく創薬研究(2-1 既存医療情報等に基づく創薬研究): 1課題あたり年間 3,000万円(上限)
• 産学連携研究成果に基づく創薬研究(3-1 基盤研究からの実装化に資する研究開発): 1課題あたり年間 3,000万円(上限)
注意事項:
• 申請額が規定の予算上限を超えていた場合は不受理となります。
• 研究開発費の規模及び新規採択課題予定数等は、予算状況等により変動する可能性があります。
【対象経費】
• 直接経費
◦ 物品費: 研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用。
◦ 旅費: 研究参加者、外部専門家等の招聘対象者、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費。
◦ 人件費・謝金: 当該研究開発のために雇用する研究員等の人件費(研究力向上のための制度(PI人件費)を含む)、講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費。
◦ その他: 研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等。
• 間接経費
◦ 直接経費に対して一定比率(30%上限)で手当され、当該研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費です。
公募対象となる研究開発課題は以下の3つの大分類です。
1. 創薬技術の創出研究
◦ 医薬品開発の進展に資する評価技術の高度化研究: 先端技術や異領域分野技術等を取り入れ、医薬品開発の場で活用される独創的な評価技術の創出・高度化を目指します。企業等からの意見が取り込まれていることや、定性的評価から定量的評価への技術創出が重視されます。
◦ 革新的医薬品創出に資する基盤技術の高度化研究: 従来の技術にとらわれず、先端技術や異領域分野技術を取り入れた基盤技術の融合・高度化を通じて、新たな技術駆動型創薬に資する基盤技術の開発を目指します。企業等での利活用を視野に入れた意見の取り込みが重視されます。
2. 医療情報等に基づく創薬研究
◦ 既存医療情報等に基づく創薬研究: 既存データの解析を通じて、創薬標的やバイオマーカーを見出し、その病態発生メカニズムにおける意味付けの明確化や疾患治療に役立つ知見の構築により、新たな創薬研究の展開を目指す提案が求められます。
3. 産学連携研究成果に基づく創薬研究
◦ 基盤研究からの実装化に資する研究開発: アカデミアと企業の共同または協業による研究成果の出口化、あるいは共同研究から派生する新しい基盤研究の展開を支援します。
◦ 国内の研究機関等に所属し、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)であること。
◦ 特定の研究機関に所属していない、または日本国外の研究機関に所属する研究者も、採択された場合、契約締結日までに日本国内の研究機関に所属する体制が取れれば応募可能です。
◦ スタートアップ企業等(設立10年以内の中小企業)は、財務状況の健全性が確認できること。
◦ 以下のいずれかの研究機関等に所属していること:国の施設等機関、公設試験研究機関、大学及び同附属試験研究機関等、民間企業の研究開発部門、研究を主な事業目的としている一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人、研究を主な事業目的とする独立行政法人・地方独立行政法人及びその他特別の法律により設立された法人、非営利共益法人技術研究組合、その他AMED理事長が適当と認めるもの。
◦ 課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること、契約手続等の事務を行うことができること、知的財産権及び研究開発データの取扱いに対して責任ある対処ができること、事業終了後も研究開発を推進し、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。
2. 研究体制:
◦ 研究班の構成員のジェンダーバランスに配慮し、特定の性別のみで構成されないようにすること。
◦ 若手研究者の積極的な参画に配慮すること。
◦ エビデンスを示すためにAIを活用する場合は、適切な専門家と連携すること。
◦ 疫学専門家は、日本疫学会や日本臨床疫学会、日本薬剤疫学会等の学会の認定資格、またはそれに準ずる専門知識・経験を有することが望ましい。
3. 社会共創・ダイバーシティ:
◦ 研究開発の初期段階から**倫理的・法的・社会的課題(ELSI)**を把握・検討し、その対処方策を研究計画等に組み込むこと。
◦ 医療研究開発プロセスにおいて、研究者が患者・市民の知見を取り入れる**患者・市民参画(PPI)**の取組を推進すること。
◦ 国籍、性別、年齢、経歴等に由来する多様な専門性や価値観を有する人々の参画を奨励し、その能力と見識を十分に発揮できる環境の醸成に努めること。
◦ 女性研究者のさらなる活躍を可能とする環境作りに努め、出産・育児・介護等のライフイベントを考慮した研究実施を支援すること。
◦ 研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明する取組や多様なステークホルダー間の対話・協働を推進するための「国民との科学・技術対話」に積極的に取り組むこと。
◦ 性差を考慮した研究開発(性別に特有の疾患や性別で差がないことが明らかになっている疾患以外を対象とする場合)を推進すること。
4. データシェアリング:
◦ 新規に人の検体やデータを取得する計画を含む場合、同意を得る際に「AMED説明文書用モデル文案」の「3.AMED文案」を使用した説明文書を用いること。
◦ ヒト全ゲノムシークエンス解析を実施する研究課題は、ヒト全ゲノムシークエンス解析プロトコール様式の提出が必須であり、提出がない場合は不受理となる。
◦ プロトコールは「AMEDデータ利活用プラットフォーム」で共有されているデータと同等の品質を担保し、国際共同研究で円滑に活用可能である必要がある。具体的には、ライブラリー作成、シークエンス反応、解析装置の機種名、クオリティーコントロール(QC)の方法、リファレンスゲノムとのマッピング及びアセンブルの方法を明記すること。
◦ 「AMED研究データ利活用に係るガイドライン」の条件を満たさない研究開発課題は不採択となる。
5. 不正行為等への対応:
◦ 本事業に参画する研究者等(再委託先を含む)が、国又は独立行政法人等から競争的研究費等の申請・参加資格制限措置を課された者ではないこと。
◦ 不正行為等に関する本調査の対象となっている場合は、AMEDに通知済みであり、AMEDの了解を得ていること。
◦ 研究機関において、国の不正行為等対応ガイドライン及び関係する法令等に定められた研究機関の体制整備として実施が要請されている各事項を遵守し実施していること。
◦ 初年度の契約締結前までに、本事業に参加する研究者等に対し研究倫理教育プログラムの履修を義務付けており、研究機関は履修状況を適切に管理・報告すること。臨床研究法における研究責任医師及び分担研究医師は、特定の研修プログラムを必ず受講すること。
◦ 本事業以外の競争的研究費等において不正行為等が認められ申請及び参加資格の制限が行われた研究者は、その期間中、本事業への研究開発代表者、研究開発分担者、研究参加者としての申請及び参加資格を制限される。
6. 研究費の不合理な重複及び過度の集中排除:
◦ 複数の公募研究開発課題への応募は認められるが、研究費の不合理な重複及び過度の集中に該当しないことを確認するため、同時に応募した研究開発課題の情報を研究開発提案書の該当欄へ必ず記載すること。
◦ 当該公募年度に研究開発代表者として本事業に参画を予定している場合は、研究開発代表者として本公募に応募できない。
◦ 応募時に、研究開発代表者・研究開発分担者等について、e-Radに記載のある現在の他府省を含む他の競争的研究費その他の研究費の応募・受入状況や、現在の全ての所属機関・役職に関する情報を応募書類に記載すること。
◦ 自身が関与する全ての研究活動に係る透明性確保のために必要な情報(寄附金等や資金以外の施設・設備等の支援を含む)について、関係規程等に基づき所属機関に適切に報告している旨の誓約を求められる。
7. 各公募課題固有の応募条件・留意事項
◦ 創薬技術の創出研究(1-1, 1-2):
▪ 事業趣旨及び公募課題の目的と合致し、研究開発を目指す技術が創薬研究の進展に資する提案として特徴付けが明確であること。
▪ 従来・先行評価技術が十分でない点を明示し、独自の着想点や新たに創出する技術について、従来技術と対比した上での先進性や差異化点を示し、企業等からの意見の対応や知財戦略を明示すること。
▪ 中間年度の3年度目において想定するマイルストーンを明確化すること。
▪ 生物系評価技術の場合、対象疾患を限定する必要はないが、その技術の妥当性をどのように検証するかを明らかにすること。
▪ 研究開発した技術が創薬研究にどのように利活用され、その発展に寄与するかについて、将来構想やインパクトを示すこと。
▪ 適切な研究体制(異なる分野の研究者や企業研究者の参画を含む)を整えること。
◦ 医療情報等に基づく創薬研究(2-1):
▪ 事業趣旨及び公募課題の目的と合致すること。
▪ 既存のリアルワールドデータ、患者検体から得られた医療情報、バイオバンクのオミックス情報や疫学情報等の医療ビッグデータを含む臨床エビデンスを使用すること。データの由来や現在データを取得中の研究を発展させる場合は事業名を提案書に記載すること。
▪ 新しい視点に基づいた挑戦的な研究開発課題の提案で、独自の着想や独創的な研究手法について、従来技術と対比した上での先進性や差異化点を示し、提案すること。
▪ 既知の薬効メカニズムに係る研究ではなく、新規の作用機序の発見や新規薬効メカニズムの探索等に資する研究であること。
▪ 創薬標的やバイオマーカーの病態発生メカニズムにおける意味付けを明確に出来る生物学的評価方法について、臨床外挿性も踏まえた妥当性も含めて明示すること。
▪ 研究チームの構成にあたっては、臨床学的意味づけを適正に行うため、臨床系研究者が研究開発代表者、研究開発分担者あるいは研究開発参加者の形で研究に参画すること。
▪ 新たに医療情報データを取得する研究や、解析手法の高度化研究が主眼となる研究提案は対象外。
◦ 産学連携研究成果に基づく創薬研究(3-1):
▪ 事業趣旨及び公募課題の目的と合致すること。
▪ 創薬に関する基盤研究で得られた成果が明確で、本公募課題での提案としての特徴付けが明確であること。先行研究に対しての先進性や差異化点を示し、提案すること。
▪ 企業を参画させ、企業からの視点、企業ニーズ等を取り入れること。
▪ 対象疾患を限定する必要はないが、目的・意義が単なる研究の補強だけでなく加速化の視点も含む提案であること。
▪ 研究終了後に新たな研究開発課題提案に展開することも含めて、将来の革新的医薬品の研究開発に実装するための具体的な戦略を示すこと。
▪ 適切な研究体制(異なる分野の研究開発分担者あるいは研究開発参加者の設置を含む)を整えること。
▪ 単なるツール化合物の追加適応やドラッグリポジショニングを目指す研究、データベース構築を目的とした研究、医療機器やDTxの開発および薬事規制上の再生医療・細胞医療・遺伝子治療の研究開発を主目的とした提案は対象外。
提案書類受付期間:令和 7 年 5 月 1 日(木) ~ 令和7年 6 月2日 (月)
書面審査:令和 7 年 6 月上旬 ~ 令和7年6月下旬
ヒアリング審査:令和7年 7 月 7 日 (月)、7 月 8 日 (火)
採択可否の通知:令和 7 年 8 月中旬
研究開発開始(契約締結等)日:令和 7 年 9 月中旬(予定)



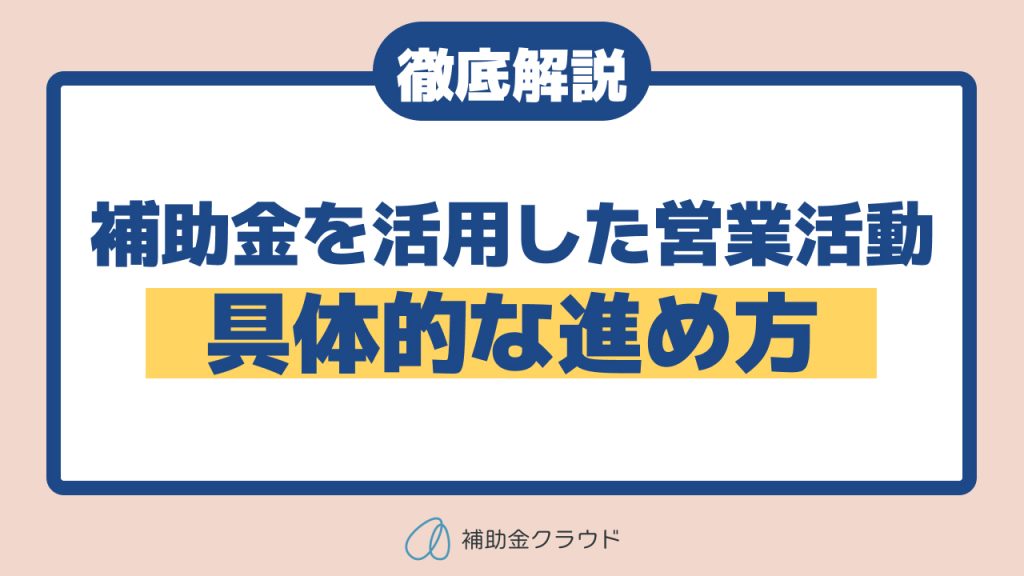
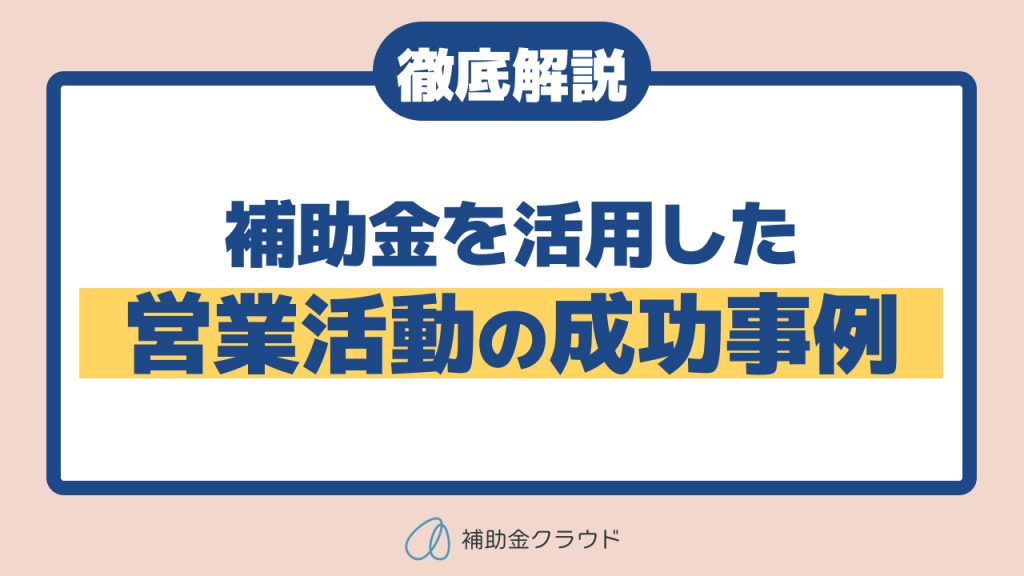
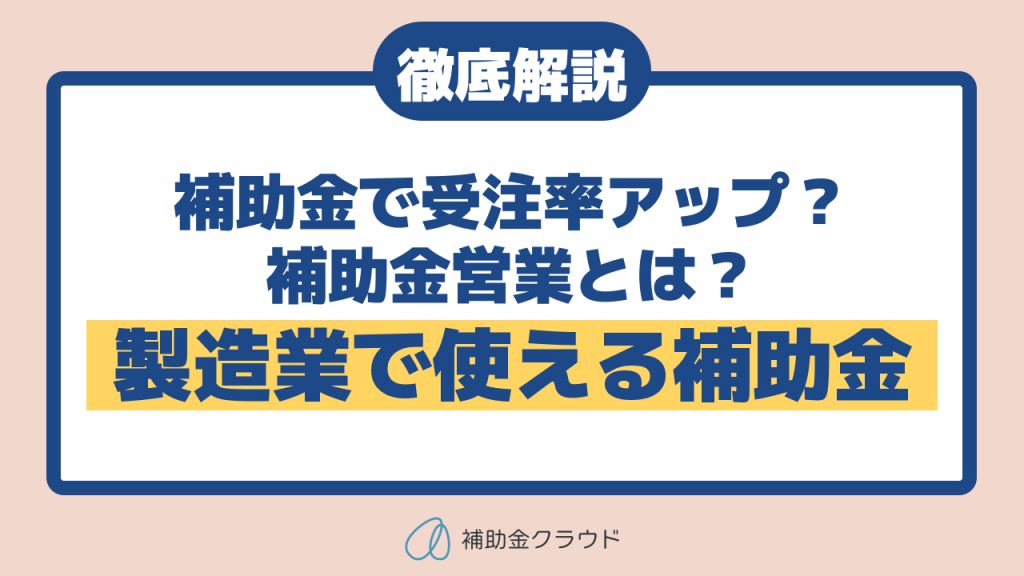
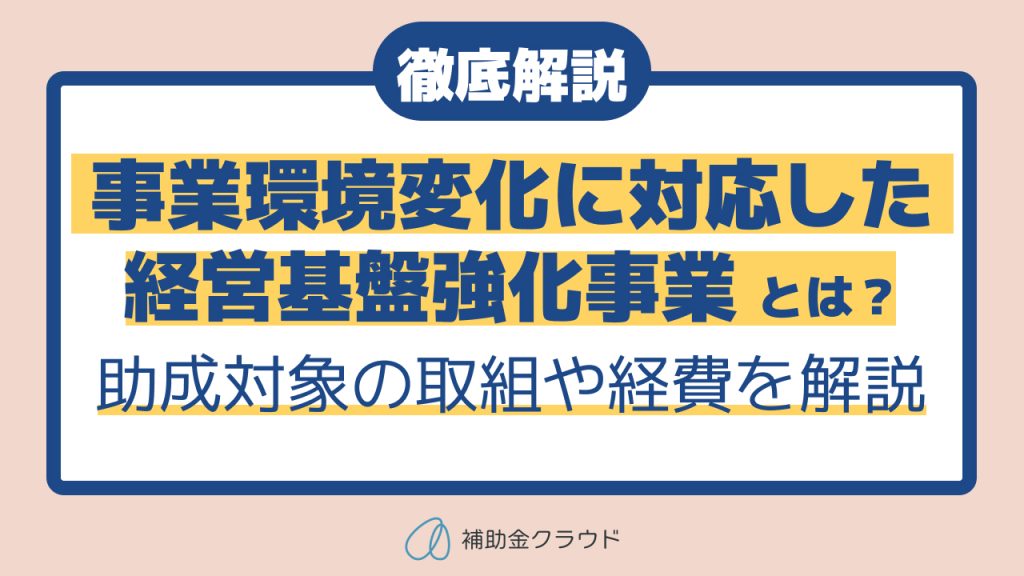
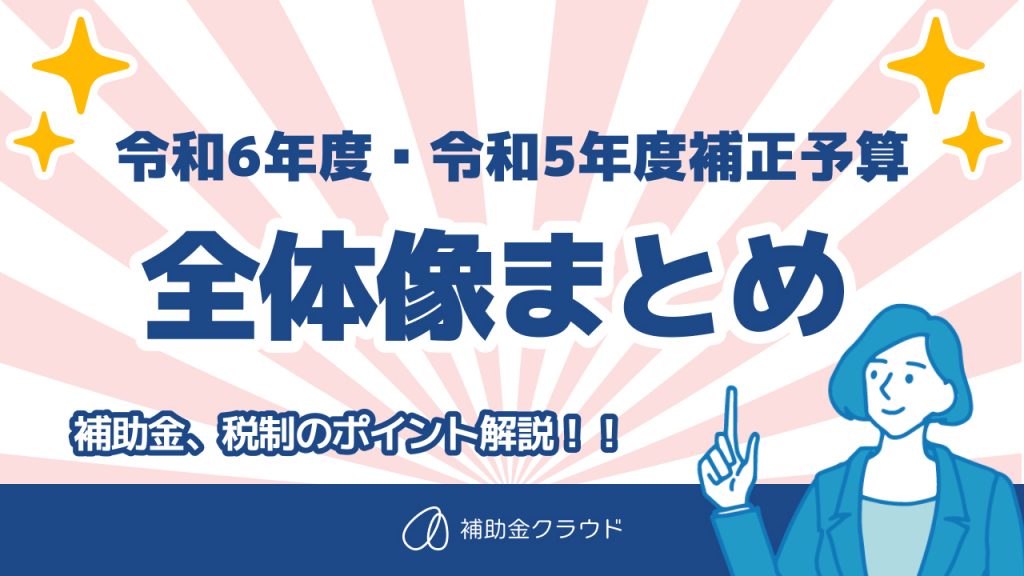
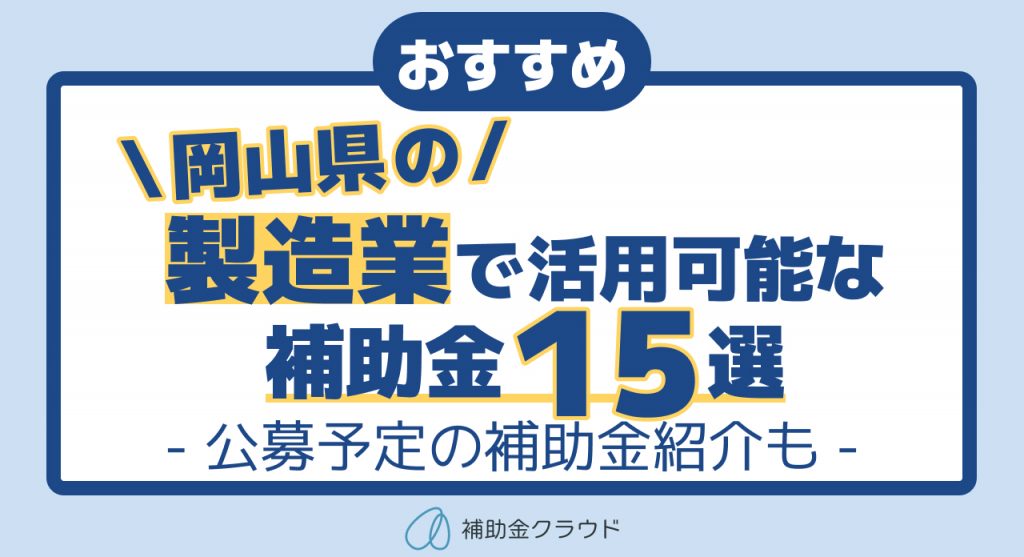





関連する補助金