全国:令和8年度 持続的生産強化対策事業のうち戦略作物生産拡大支援事業のうち作付体系転換支援事業
2023年2月11日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
「令和8年度持続的生産強化対策事業のうち戦略作物生産拡大支援事業のうち作付体系転換支援事業」に係る事業実施主体の公募については、以下に定めるとおりです。
なお、本公募は令和8年度政府予算案に基づいて行うものであるため、成立後の予算の内容により、事業内容、予算額等に変更があり得ることをあらかじめご了承の上、御応募ください。
-----
本事業は、大豆、麦及び飼料用米、加工用米、米粉用米その他地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下同じ。)が認める土地利用型作物 (以下「飼料用米等」という。)の生産性向上を図るため、新たな品種、作付体系、栽培技術等(以下「新技術等」という。)の導入又は大豆極多収品種の奨励品種決定調査の取組等を支援する。
・備品費
・賃金等
・給与
・報酬
・職員手当等
・事業費
-会場借料
-通信・運搬費
-借上費
-印刷製本費
-資料購入費
-原材料費
-資機材費
-消耗品費
・旅費
-委員旅費
-調査等旅費
-費用弁償
・謝金
・委託費
・役務費
・雑役務費
-手数料
-租税公課
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本事業の内容は以下のとおりとし、事業実施主体は以下の事業メニューの中から必要な取組を選択し、実施するものとする。
(1)作付体系転換推進検討会の開催
事業を実施する地域の状況に応じた新技術等の導入及び当該新技術等を導入した農産物の利用促進のために、都道府県(普及機関及び試験研究機関を含む。)、大豆、麦及び飼料用米等の生産性向上を重点的に図るべき地域(以下「生産性向上重点地域」という。)がある市町村、農業関係団体、農業者、実需者等により構成される作付体系転換推進検討会を開催する。
(2)作付体系転換のための合意形成
生産性向上重点地域において、事業実施の合意を形成するために必要な農業者の意向把握調査又は農業者を対象とした説明会を実施する。
(3)生産性向上に資する新技術等の実証及び改良
生産性向上重点地域において、実証を行うほ場を設置し、大豆、麦及び飼料用米等の生産性向上に資する新技術等を試験的に導入し、当該新技術等の実証(農産物の利用に関するものも含む。)及び実証結果を踏まえた改良を実施する。
(4)新技術等を用いた大規模技術・経営実証
(3)の結果等を踏まえ、大規模に普及することが可能と見込まれる新技術等について、生産性向上重点地域において、大豆、麦及び飼料用米等の面積を合わせて5ha 以上の規模で実証を実施する。その際、実証に直接必要となる機械であって、事業実施主体が所有していない又は所有しているものの改良若しくは更新が必要である場合に限り、本事業を活用して機械を購入することができるものとする。なお、購入した機械は、耐用年数が経過するまでの間、原則として5戸以上の農業者で共同利用するものとする。
(5)現地検討会の開催
(3)及び(4)に取り組む地域において、その効果の調査及び検証並びに普及が可能と見込まれる新技術等の普及のため、都道府県、生産性向上重点地域がある市町村、農業関係団体及び農業者等により構成される現地検討会を開催する。
(6)新技術等活用マニュアルの作成
都道府県域で、新技術等の普及を図るための新技術等活用マニュアルの作成を行う。
(7)新技術等普及研修会の開催
都道府県域で、新技術等の普及を図るための新技術等普及研修会を開催する。
2025/01/31
2026/02/24
(1)事業の内容が、3(1)に基づき設定する成果目標の達成に結びつく取組であること。
(2)大豆、麦及び飼料用米等の生産性向上に向け、事業実施区域の属する都道府県における大豆、麦及び飼料用米等の生産に係る課題及び取組方針が整理されており、かつ、都道府県内において普及すべき新技術等及び生産性向上重点地域が特定されていること。
(3)事業実施主体は本要領別紙2に掲げるものとし、大豆、麦及び飼料用米等生産性向上協議会である場合は、都道府県域内の区域を対象とし、かつ、以下の要件を全て満たしている者であること。
ア 都道府県、農業関係団体及び農業者等により構成されること。なお、都道府県農業再生協議会(経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成 27 年4月9日付け 26経営第 3569 号農林水産事務次官依命通知)第2の1の(2)に定めるもの。)等の既存の協議会であってもよい。
イ 本事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、①代表者及び意思決定の方法、②事務・会計の処理方法及びその責任者、③財産管理の方法、④公印の管理、使用及びその責任者、⑤内部監査の方法等を明確にした運営等に係る規約(以下「生産性向上協議会規約」という。)が定められていること。
ウ 生産性向上協議会規約において、一つの手続につき複数の者が関与する等、事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。
エ 必要に応じて議決権を持たないオブザーバーを置き、オブザーバーが会議に出席して意見を述べることができる体制が整備されていること。
オ 3(1)の基準を満たす成果目標を立てていること。
提出期限:令和8年2月24日(火曜日)午後5時必着
事業の内容、提出先等に関するお問い合わせ先一覧:https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/attach/pdf/260202_160-1-3.pdf
「令和8年度持続的生産強化対策事業のうち戦略作物生産拡大支援事業のうち作付体系転換支援事業」に係る事業実施主体の公募については、以下に定めるとおりです。
なお、本公募は令和8年度政府予算案に基づいて行うものであるため、成立後の予算の内容により、事業内容、予算額等に変更があり得ることをあらかじめご了承の上、御応募ください。
—–
本事業は、大豆、麦及び飼料用米、加工用米、米粉用米その他地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下同じ。)が認める土地利用型作物 (以下「飼料用米等」という。)の生産性向上を図るため、新たな品種、作付体系、栽培技術等(以下「新技術等」という。)の導入又は大豆極多収品種の奨励品種決定調査の取組等を支援する。



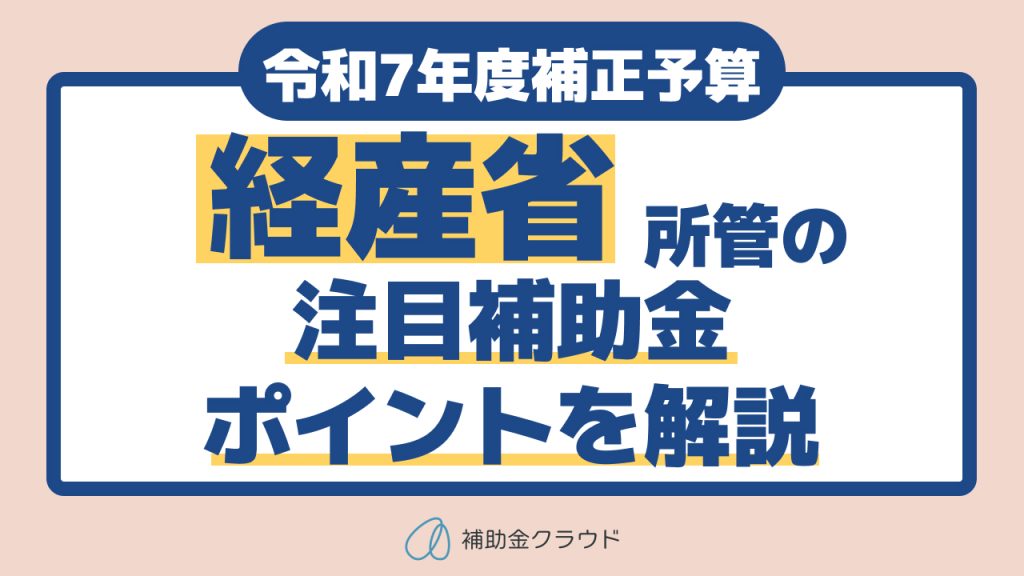
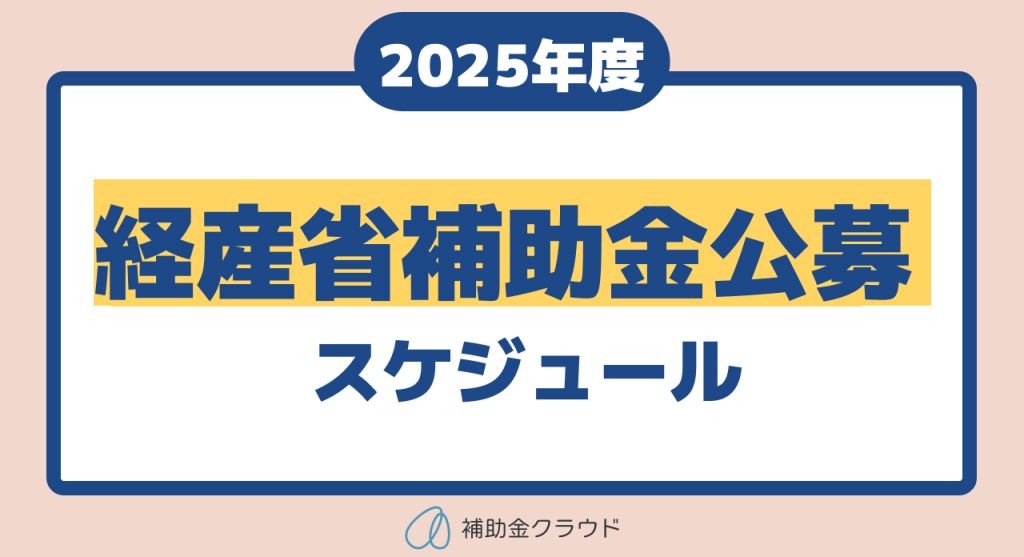
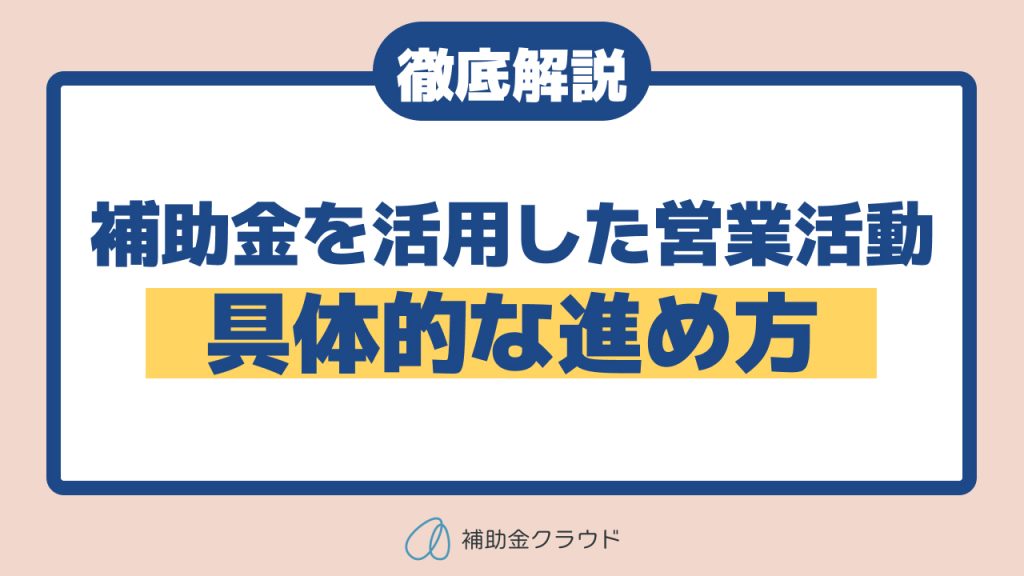
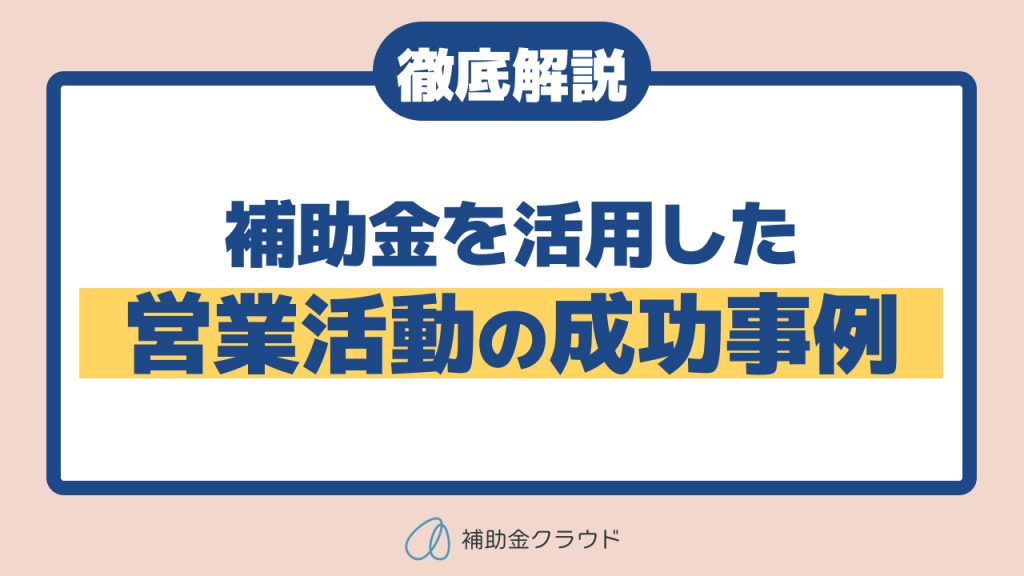
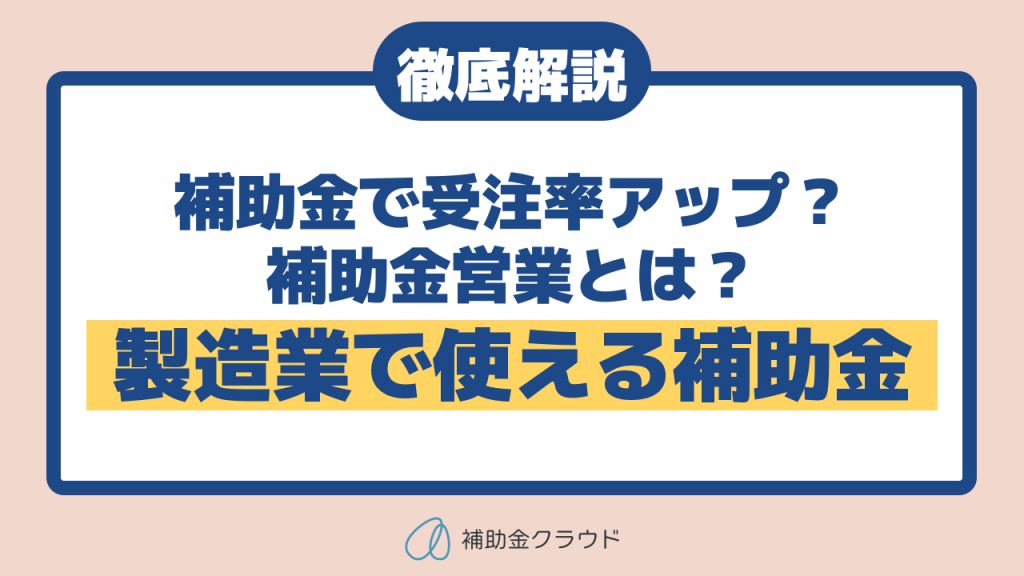
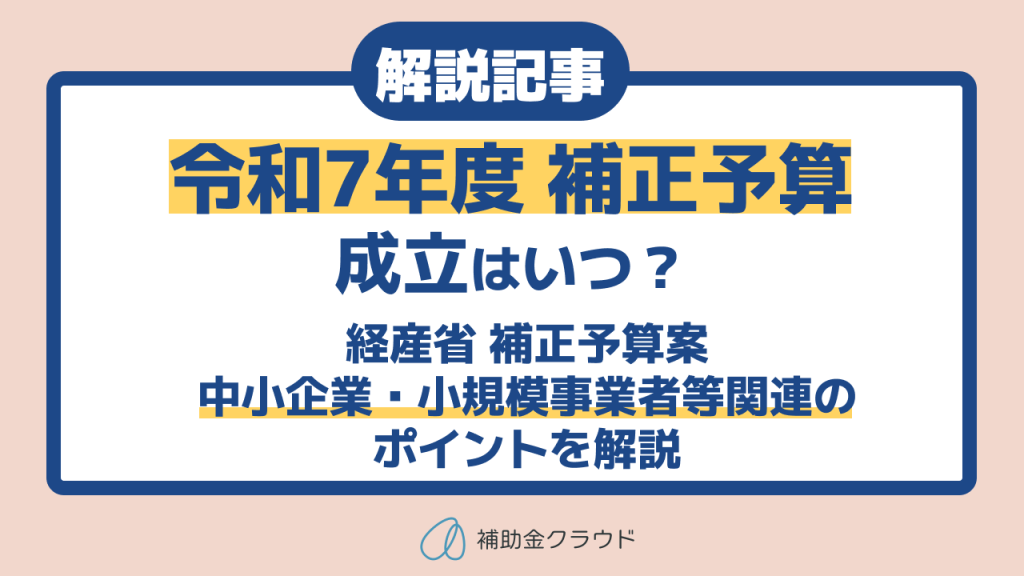

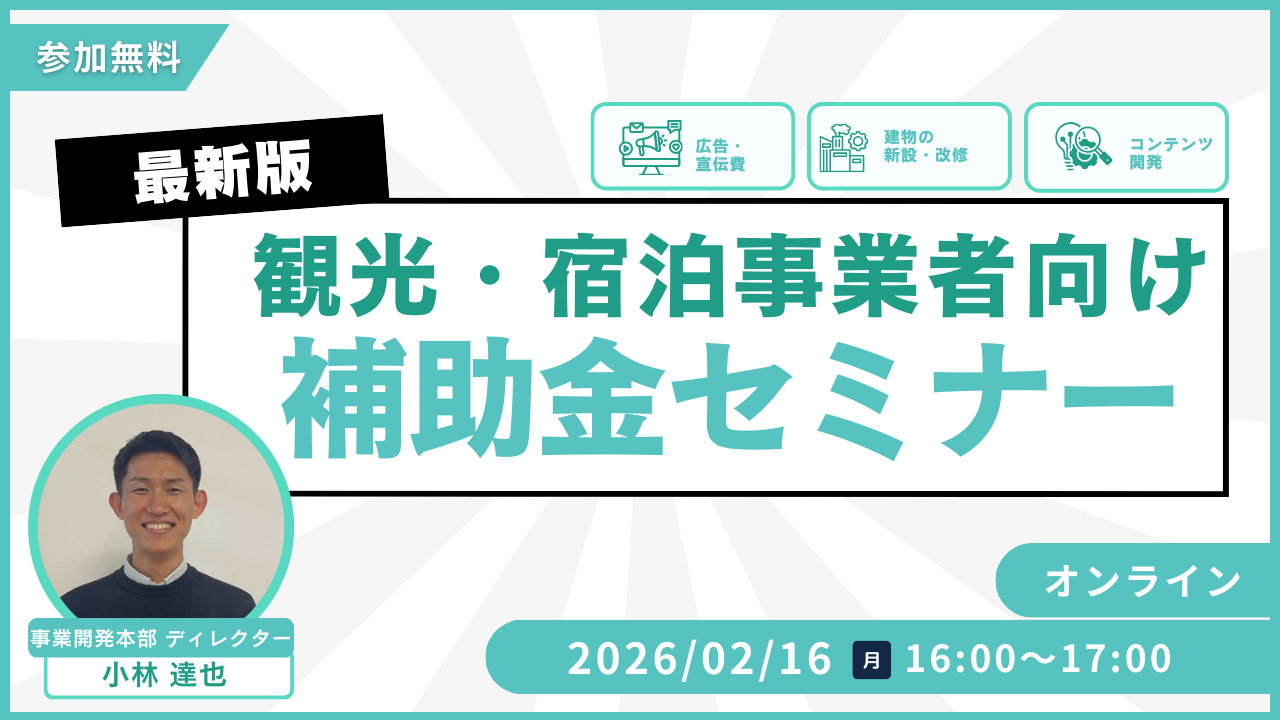


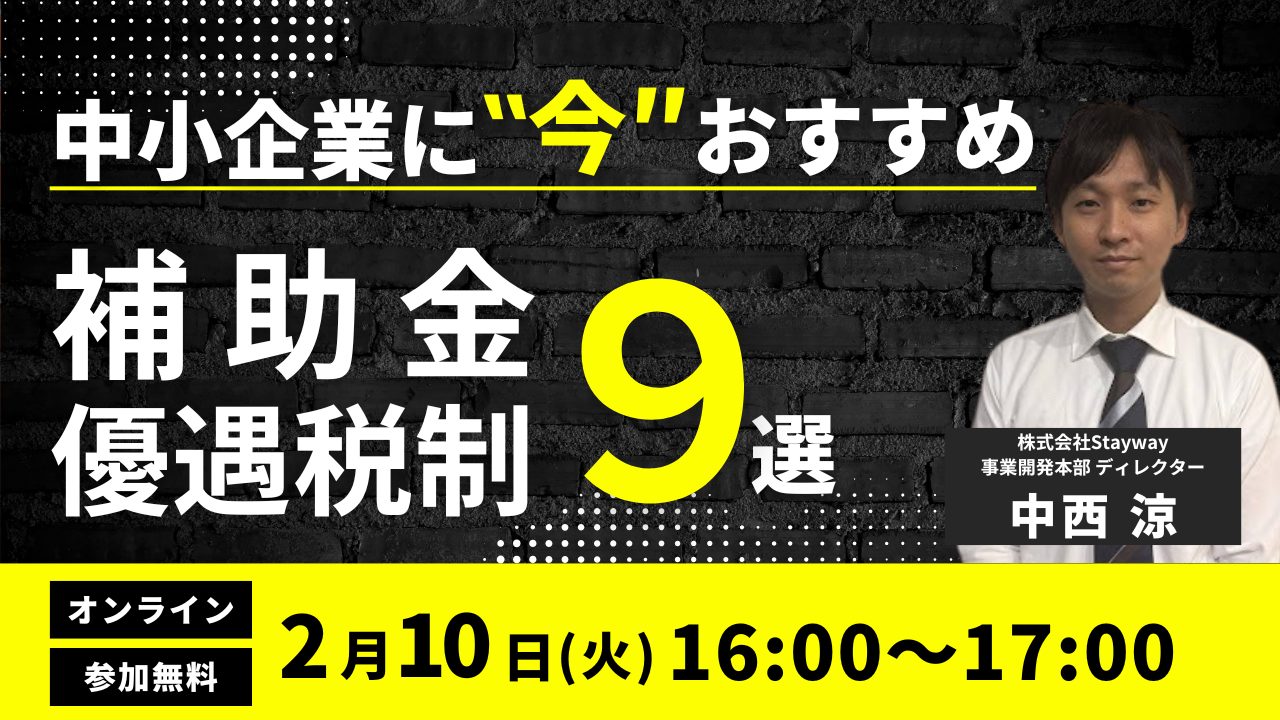
関連する補助金