長寿科学研究開発事業

【補助率詳細】
■1 科学的根拠が検証されたサルコペニアに関するバイオマーカー開発研究:1課題当たり年間2,400万円(上限)
■2 高齢者の意欲低下の診断に資するフローチャートの開発及び指針作成:1課題当たり年間800万円(上限)
■3 災害時リハビリテーション支援のための生活機能評価・トリアージシステムの開発に向けた研究:1課題当たり年間800万円(上限)
≪引用元:公募要領p.3(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等について)参照≫
【対象経費】
■直接経費
・物品費 研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
・旅費 研究参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費
・人件費:当該研究開発のために雇用する研究員等の人件費(研究力向上のための制度(PI人件費)を含む。)
・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費
・その他 上記のほか、当該研究開発を遂行するための経費
例) 研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等
■間接経費
直接経費に対して一定比率(30%上限)で手当され、当該研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費
≪引用元:公募要領p.36(Ⅱ-4.2.1 研究開発費の範囲 )参照≫
科学的根拠が検証されたサルコペニアに関するバイオマーカー開発研究
(目標)
高齢期におけるサルコペニアの病態を反映するバイオマーカーの開発が進む中、理論的な裏付けがなさ
れたバイオマーカーの臨床応用が求められる。本研究開発課題では、サルコペニアのスクリーニングに
有用とされる、既知あるいは新規バイオマーカー候補について、既存のコホート研究等を活用して性能
検証を行い、サルコペニアのスクリーニングや介入指標に資するバイオマーカー開発研究を実施する。
新規でバイオマーカーの探索を実施する場合は、そのメカニズム解明による科学的根拠の裏付けを行う
基礎研究を行い、臨床現場における活用が期待される候補を選別し、性能検証を行うことでバイオマー
カー開発を目指す。
(求められる成果)
・サルコペニアのスクリーニングと介入指標としてのバイオマーカー性能検証。
・バイオマーカー性能検証の結果を基に、臨床応用としてのスクリーニング方法、介入指標の基準を具
体的に提示する。
・なお、サルコペニアの臨床応用可能なバイオマーカーを新規で探索する場合、想定するメカニズムに
ついて科学的根拠の裏付けのための基礎研究を行い、サルコペニアのスクリーニングに活用可能な感
度・特異度に優れるバイオマーカー候補を選別すること。
(採択条件)
・臨床現場での利用を視野にいれた提案であること。すでにバイオマーカー候補を有する(あるいは既
知バイオマーカー候補を検証する)場合、その有用性が文献等で示されているとともに、具体的な性
能検証プロセスと想定可能な出口戦略が明示されていること。
・新規でバイオマーカー探索を行う場合は、メカニズム解明による科学的根拠の裏付けを行う基礎研究
を実施した後、得られた候補の具体的な性能検証プロセス、想定可能な出口戦略が明示されているこ
と。
・開発するバイオマーカーの臨床応用を見据えた長期的なロードマップを作成し、当該研究が開発のど
の段階にあってどのような役割を果たすのかを明示するとともに、臨床現場等で想定される具体的な
活用方法など、将来的な展望を提示すること。
・研究開発代表者は神経筋組織の生理学研究や、サルコペニアの生物学的メカニズム解明を目的とする
研究分野において、過去5年間で査読付き英文雑誌への掲載実績を有すること。
・ 加齢医学研究分野や、免疫学や代謝学等の研究分野において研究経験を有する研究者、および老年医
学における臨床経験豊富な研究者が研究開発代表者および研究開発分担者に含まれる研究班体制が構
築されていること。
(公募名)
高齢者の意欲低下の診断に資するフローチャートの開発及び指針作成
(目標)
高齢者の意欲低下は、本人のQOLを低下させるほか、リハビリテーションやケアの阻害要因となる。意
欲低下の原因は、脳血管障害や脳変性疾患などの脳障害、内分泌疾患などの内科疾患、うつ病などの精
神疾患、薬剤の影響、社会的要因など多岐にわたるが、これらの中には治療等によって改善が図れる病
態や状態がある。しかし意欲低下があっても加齢が原因である等と考えられて、十分な対応がなされて
いない場合がある。 本研究課題においては、高齢者の意欲低下の原因、その診断方法、治療可能な病
態については治療及びケア方法について整理し意欲低下の診断に資するフローを開発することで、在宅
および介護施設などで生活している高齢者に対する医療・介護現場で広く使用できる指針としてまとめ
ることを目指す。
(求められる成果)
・高齢者の意欲低下の評価方法、原因、治療・ケア方法についてエビデンスを整理し、治療可能な意欲
低下の診断に資するフローチャートを開発し、ケアギバーが医療・介護現場で使用できる指針として公開すること。
(採択条件)
・研究計画の前半においては、意欲低下の評価方法、意欲低下が生じる病態やその頻度、治療可能な病
態に関してはその治療法・ケア方法等について文献レビューを行い、現状のエビデンスを体系的に整
理すること。
・開発したフローチャート等を用いて診察を行い、医療・介護現場で指針に基づくリハビリテーション
やケアの介入の妥当性検証を行い、その結果を評価することでフローチャートならびに指針のブラッ
シュアップを提示すること。
・成果の活用について、公開・普及方法における展望を具体的に提示すること。
・高齢者診療およびケアに関する多領域の専門家が研究開発代表者および研究開発分担者に含まれる研
究班体制が構築されていること。
・社会心理的な側面における専門家やケア現場からの意見を取り入れることができる体制が構築されて
いること。
(公募名)
災害時リハビリテーション支援のための生活機能評価・トリアージシステムの開発に向けた研究
(目標)
災害時には、避難所生活を送る高齢者の健康とQOLを維持するため、適切な介入・支援を行う必要
があり、そのための生活機能評価・トリアージシステムが求められる。現状、災害現場においては医
療チームの診療記録を標準化し報告、それを集約することで医療ニーズの把握と対応を効率化するシ
ステムが活用されている。一方、避難所生活が長くなることで高まる機能低下のリスク回避するために
生活機能評価・トリアージを行う包括的な評価指標についての検証は十分ではない。
本研究課題の目的は、避難所生活を送る高齢者の生活機能を適切に評価し、悪化傾向が見られた場合、
すみやかに適切な介入・支援を行うための、包括的な評価指標を明確化することが可能な、生活機能
評価・トリアージシステムの開発に向けた研究を行うことである。
(求められる成果)
・災害時に避難所生活を送る高齢者の生活機能評価・トリアージを行うために、既存のエビデンスや統
計データに基づいて生活機能評価・トリアージに必要な項目を整理・分析し、心身機能低下リスクが
高い状態や支援が必要な人の抽出に必要な評価項目や方法を開発すること。
・開発した評価項目をもとに、生活機能評価・トリアージを簡便に行うことを可能にするスマートフォ
ンに追加できるアプリケーションの開発に向けた提案をすること。なるべく早期に災害現場で使用開始
できる成果物が望ましい。
・適時に適切な介入を開始するためには、各高齢者の平時の状態や悪化速度等の情報が必要であり、開発した評価項目をもとに、簡便かつ複数時点での入力情報を比較できる等の利便性を考慮したシステ
ムが望ましい。
※新たなアプリケーション開発を想定する場合は、アプリケーションを試作するとともに、仕様書を
作成し、仕様書の構成は以下を含むこと。なお、原則として追加の説明なしに、ソフトウェア開発ベ
ンダーが仕様書に基づいてアプリケーションを開発できる粒度の文書であること。
・要件定義書―アプリケーションの要件を定義した文書
・画面設計書―アプリケーションのユーザーインターフェイス画面の設計書
・API仕様書―アプリケーションが使用するAPIのインターフェイス定義、処理ロジックのフローチ
ャート等を含む説明文書
・テーブル定義書―アプリケーションが使用するデータベース等のテーブル定義書
・テスト仕様書等―アプリケーションのテスト手順を定めた文書
(採択条件)
・災害時に避難所生活を送る高齢者の生活機能評価・トリアージを行うために、既存のエビデンスや統
計データに基づいて生活機能評価・トリアージに必要な項目を整理・分析し、心身機能低下リスクが
高い人や支援が必要な人の抽出に必要な評価項目や方法を開発する計画になっていること。
・スマートフォンに追加するアプリケーションは、保健師・理学療法士などの専門職や災害リハビリテ
ーション支援団体など多職種によって使用されることを想定していること。
・アプリケーションを既存システムに機能をアドオンする場合は、アプリケーション開発に向けた手順
を明確に提示することを目的とした計画になっていること。
・新たなアプリケーション開発を想定する場合は、単独で利用できるスタンドアローンのアプリケーシ
ョンを想定し、必要な項目を含む仕様を提案する計画になっていること
・トリアージシステムを広く普及させるために、関係学会、関係団体等から協力が得られる連携体制が
構築されている、または研究期間中に構築することが計画に盛り込まれていること。
・災害時の医療、リハビリテーション、高齢者医療や介護に関連する専門家、および社会心理的側面に
関する専門家や災害支援を経験した実践家が研究開発代表者および研究開発分担者に含まれる研究班
体制が構築されていること。
≪引用元:公募要領p.4-7(2.2公募対象となる研究開発課題の概要について)参照≫
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、令和 7 年 3 月10 日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。ただし、令和7年3月10日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、AMED ではスタートアップ企業等を「中小企業※の内、設立10 年以内」と定義し、応募時や採択時、研究進捗確認時に、財務状況の健全性を確認していきます。 ※中小企業の定義は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)の定めるところによります。
なお、分担研究機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約時に必要な条件を満たすか確認が必要になります。分担研究機関は、代表研究機関と再委託研究開発契約を締結します。 所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途ご相談ください。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職、福祉職、指定職又は任期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関
(C) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合
(H) その他AMED理事長が適当と認めるもの
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本タイプ実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)本タイプ終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。
(6)スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著しく脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著しく脆弱で委託研究開発契約の履行能力がないと判断されると、契約締結できない場合があります。)
≪引用元:公募要領p.8(3.1応募資格者)参照≫
提案書類受付期間 :令和7年1月15日(水)~令和7年2月17日(月)【正午】(厳守)
書面審査 :令和7年2月下旬~令和7年3月中旬(予定)
ヒアリング審査 :令和7年3月28日(金)(予定)
採択可否の通知 :令和7年4月中旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日 :令和7年5月下旬(予定)



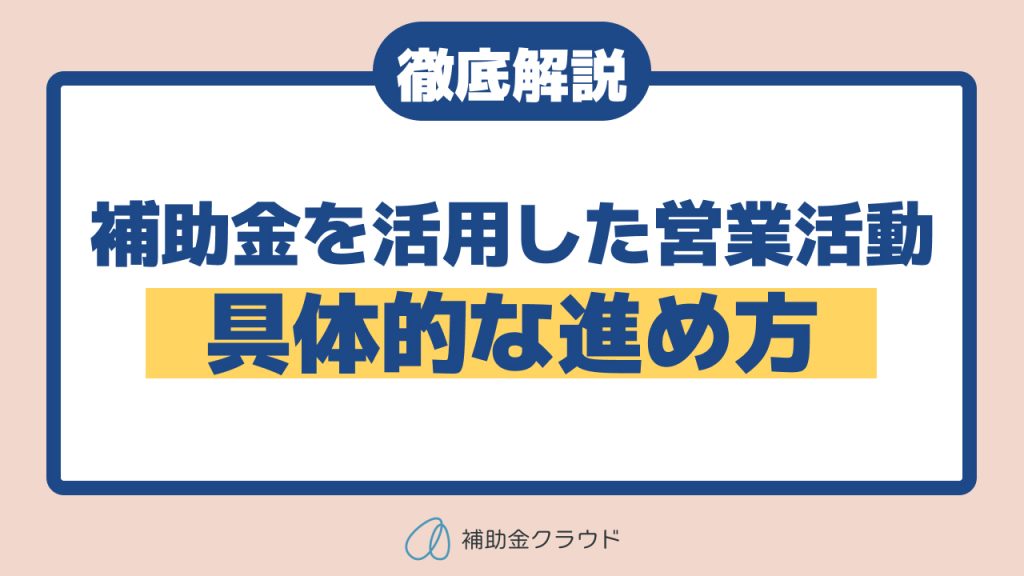
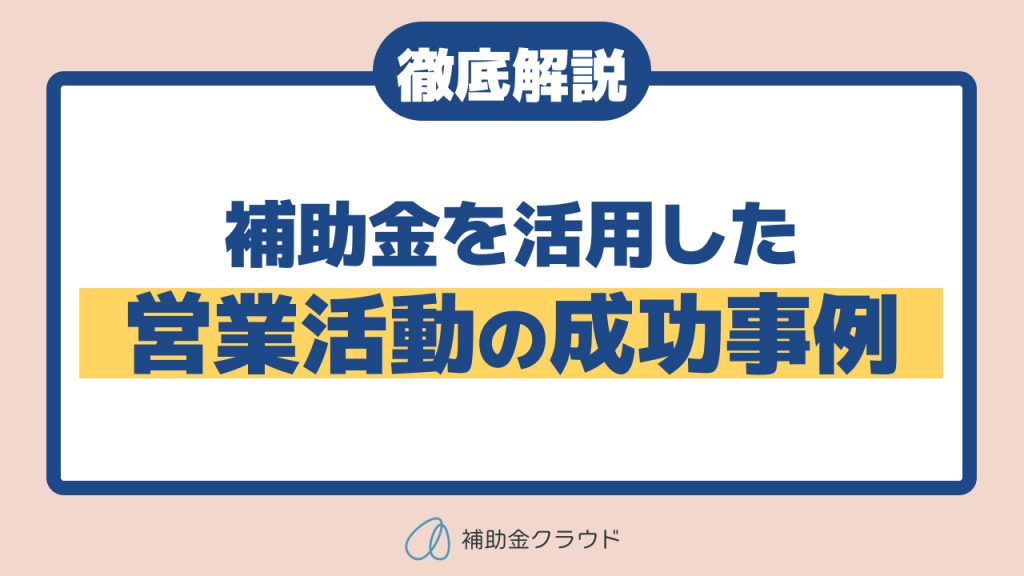
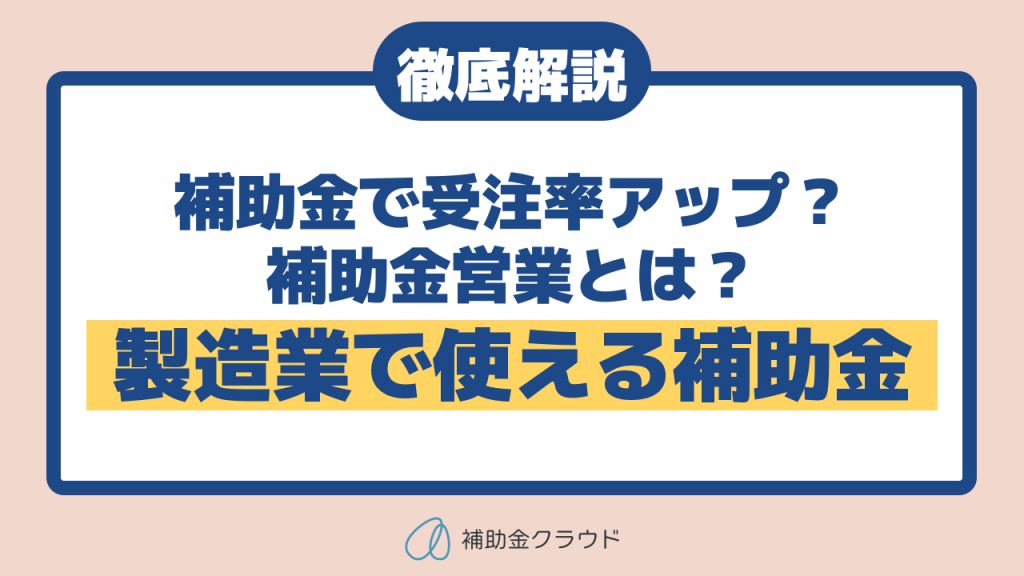
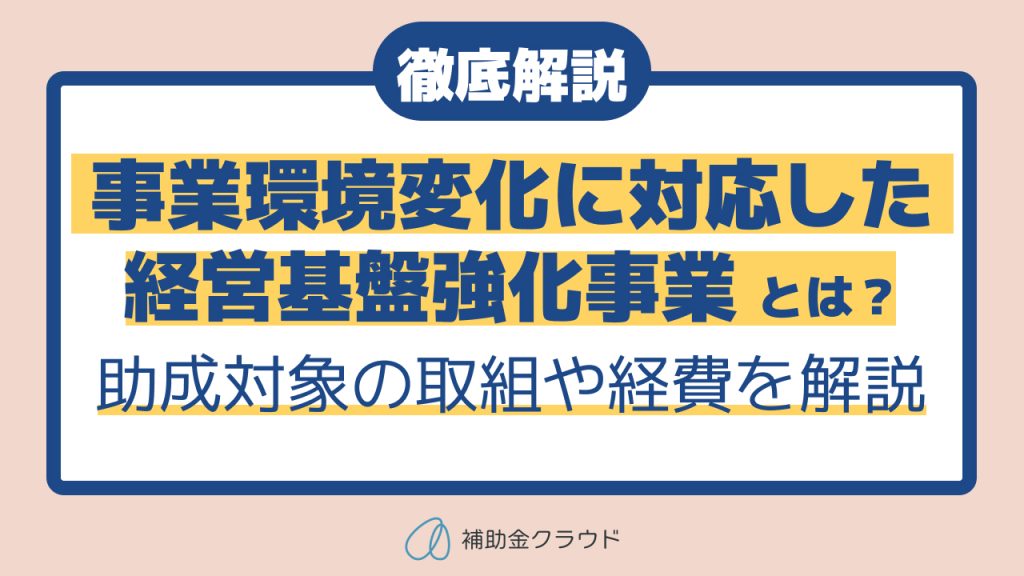
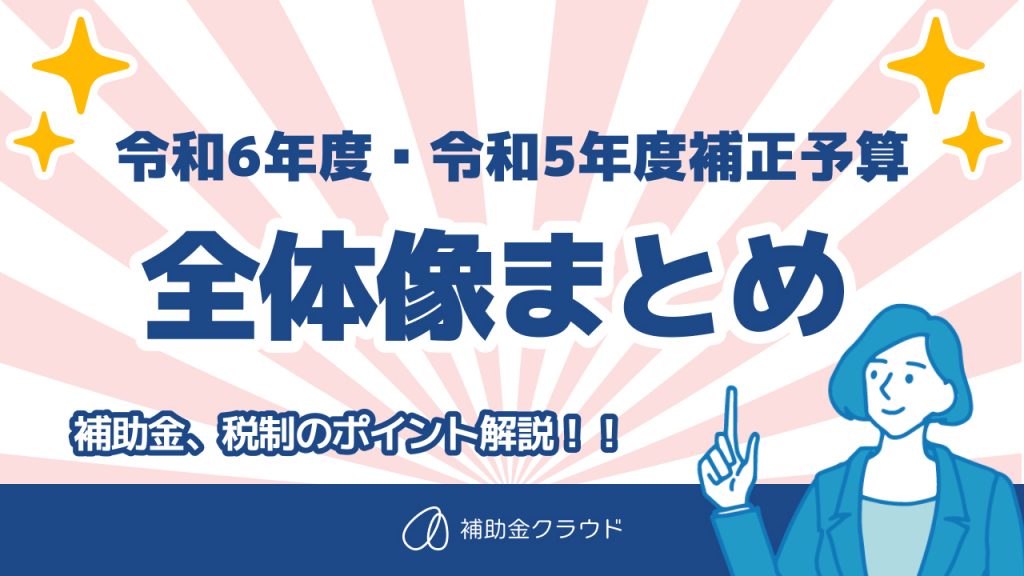
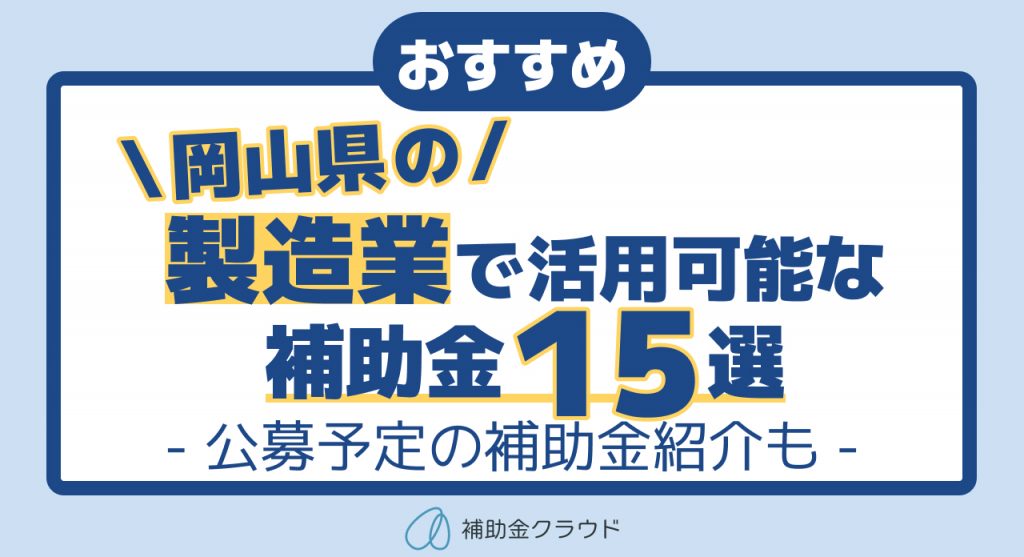





関連する補助金