難治性疾患実用化研究事業

【補助率詳細】
■A-1医薬品のシーズ探索研究 (医薬品ステップ0):1課題あたり年間 2,000万円(上限)
■A-2超希少難治性疾患に対する医薬品のシーズ探索研究 (医薬品ステップ0・超希少):1課題あたり年間 2,000万円(上限)
■A-3医薬品の治験準備 (医薬品ステップ1):1課題あたり年間 6,000万円(上限)
■A-4希少難治性疾患で医薬品の治験に適応できる分散型臨床試験 (医薬品プレステップ2):1課題あたり年間 2,000万円(上限)
■A-5医薬品の治験 (医薬品ステップ2):1課題あたり年間 8,000万円(上限) ※ドラッグ・リポジショニングは 6,000万円(上限)
■A-6国内開発未着手の治験 (医薬品ステップ2・ドラッグロス):1課題あたり年間 8,000万円(上限)
■B-1再生・細胞医療・遺伝子治療のシーズ探索研究 (再生等ステップ0):1課題あたり年間 2,000万円(上限)
■B-2再生・細胞医療・遺伝子治療の治験準備 (再生等ステップ1):1課題あたり年間 6,000万円(上限)
■B-3再生・細胞医療・遺伝子治療の治験 (再生等ステップ2):1課題あたり年間 8,000万円(上限)
≪引用元:公募要領p.3(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等について)参照≫
【対象経費】
■直接経費
物品費:研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
旅費:研究参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費
人件費:当該研究開発のために雇用する研究員等の人件費(研究力向上のための制度(PI人件費)を含む。)
謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費
その他:上記のほか、当該委託研究開発を遂行するための経費
例)研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等
■間接経費
直接経費に対して一定比率(30%上限)で手当され、当該研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費
≪引用元:公募要領p.79(Ⅱ-4.2.1 委託研究開発費の範囲 )参照≫
(1)公募研究開発課題名
A-1.医薬品のシーズ探索研究(医薬品ステップ0)
A-2.超希少難治性疾患に対する医薬品のシーズ探索研究(医薬品ステップ0・超希少)
A-3.医薬品の治験準備(医薬品ステップ1)
A-4.希少難治性疾患で医薬品の治験に適応できる分散型臨床試験(医薬品プレステップ2)
A-5.医薬品の治験※2(医薬品ステップ2)
A-6.国内開発未着手品の治験(医薬品ステップ2・ドラッグロス)
(2)採択条件
【共通部分】
(a)対象とする疾患が特定され希少難治性疾患であること。その疾患の現状(既存及び先行開発中の医
薬品等医療技術など)について調査方法・調査実施時期等根拠を示した上で、提案する治療法の優位
性を含むTPP(Target Product Profile)※3が明記されていること。
※3 開発候補物名(化学名)、薬事申請上の分類(新有効成分、新効能、新投与量など)、想定効能・効果(有効性
が期待される疾患の症状)、ポジショニング(医療技術における位置づけ、アンメットメディカルニーズの充足
性)、有効性(臨床的に受け入れられる基準を満たしうることを、in vivo 評価結果を元に明示する)、安全性上の
課題(想定される毒性所見、in vivo 評価による安全域評価実現可能性、毒性バイオマーカーの有無)、用法・剤
形(患者の服用容易性)、臨床開発における課題などを意味する。
【公募研究開発課題毎の条件】
「A-1. 医薬品のシーズ探索研究(医薬品ステップ0)」及び「A-2. 超希少難治性疾患に対する医薬品のシー
ズ探索研究(医薬品ステップ0・超希少)」の条件
(b)「(3)求められる成果(a)」に記載された成果を求めるものであり、研究の主たる部分がシーズ探
索であること。
(c)創薬化学、毒性学等の開発候補物の開発及び評価が可能な専門家※4又は製薬企業が研究に関与する
体制が整備されている、もしくは当該業務について専門性を有する橋渡し研究支援機関や CRO に委
託する研究計画であること。
※4 ここでいう創薬化学等の専門家とは開発候補化合物の特定における化合物設計、合成、物性評価の経験を有
する者。毒性学の専門家とは開発候補化合物選定における毒性評価及び薬物動態スクリーニングについての経験
を有する者をいう。
「A-2. 超希少難治性疾患に対する医薬品のシーズ探索研究(医薬品ステップ0・超希少)」の条件
(d)提案する研究開発内容が、本事業で規定する希少難治性疾患の克服を目指すものであり、かつ、超
希少難治性疾患を対象としていること。対象患者数は国内に1,000人未満を目安とし、提案が妥当で
ある根拠を研究開発書に記載すること(必須)。
また、根拠となる客観的証拠(国内患者を対象とした、公開済みかつ査読有りの文献や厚生労働科
学研究事業や信頼される学会の調査結果等)を資料番号9に追加すること。 複数の根拠があり、少な
い患者数を呈示する場合は、その合理性を説明すること。接頭語やただし書き等を提案者の判断で追
加することによって、患者数を1,000人未満とすることは認められません。
超希少難治性疾患については、独立した疾患概念が確立している、もしくは既存の疾患概念に当て
はまらないことが明確であることが望ましい。明らかに国内に 1,000 人以上の患者が確認されている
疾患の亜型、サブタイプ、一症候に関する研究は認められない。また、希少であっても医原性疾患は
対象外とする。死亡患者数は対象患者数に含めない。本採択条件を満たすかどうかは評価委員の判断
に委ねられる。
「A-3. 医薬品の治験準備(医薬品ステップ1)」の条件
(e)治験を実施するために必要な全ての非臨床試験が研究開発期間内に完了する計画であること。また、
既に行った非臨床試験及び今後行おうとする非臨床試験について非臨床試験報告書等をもとに研究開
発提案書別紙である「非臨床試験サマリー」及び「非臨床試験ガントチャート」を記載すること。
(f)治験用原薬と同等の品質が求められる非臨床試験で使用する原薬、及び原薬の規格安定性用、製剤
処方製法検討用の原薬の調達が済んでいる、あるいは調達が可能であることの理由を記載すること。
治験で使用する原薬及び製剤の治験GMP製造を実施する準備状況、今後の計画を記載すること。
「A-4. 希少難治性疾患で医薬品の治験に適応できる分散型臨床試験(医薬品プレステップ2)」の条件
(g)分散型治験に用いる手法を検証するために必要な全ての試験が研究開発期間内に完了する計画であ
ること。応募時の資料に従来の治験手法に対する患者、治験機関の負担軽減、実施可能性の向上、再
現性を比較するための評価項目と方法、期待する成果に加え、用いる治療法が標準治療であることを
提示すること。また、研究開発期間終了後に治験を行う開発候補物の提示又は確保に向けた計画が示
せること。
「A-5. 医薬品の治験(医薬品ステップ2)」の条件
(h)治験を実施するために必要な全ての非臨床試験について、非臨床試験報告書等をもとに研究開発提
案書別紙(非臨床試験サマリー)及び研究開発提案書別紙(非臨床試験ガントチャート)を記載し、
その中で非臨床データパッケージの充足性について説明すること。
(i)製造販売承認申請を実施する導出予定企業名及び導出予定時期が記載されており、本研究にて臨床
POCが取得できた場合は当該企業が承認申請を担当することに同意したことを示す記録(メール等で
可)が提出されていること。なお、AMEDとの契約締結後1年以内に、本件についての契約書を研究
開発代表者と当該企業にて締結することとし、当該企業の権利、競争上の地位その他正当な利益を害
するおそれがある情報を除き、AMEDが契約内容を閲覧することを承諾すること。
(j)導出予定企業の協力内容が明記され、評価(事前・中間・事後)や進捗管理の際に当該企業等の担
当者が同席すること。
(k)対象とする製剤等の入手方法(企業等から供与、購入、自施設で製造、委託製造)、更にDR治験に
ついては薬事承認状況(国内外における承認状況及び取得している主な効能・効果と用法・用量)が
明記されていること。
(l)AMEDとの契約締結後、半年以内に治験届を提出できること。
(m)難病患者に関するデータベース等を活用するなどして、短期間に予定被験者数を登録できる体制が
整備されている、又は初年度中に整備して実施できること(症例登録計画、予定登録数の事前調査等、
根拠となるデータを明示すること)。
(n)治験(多施設で実施する場合は多施設共同治験)を実施できる体制や専門家(当該医薬品の対象と
なる疾患に関わる臨床専門家、生物統計家※5、臨床薬理専門家、薬事専門家等)が関与する体制が整
備されていること、医薬品の創製から製剤化までを網羅的に評価できる創薬化学等の専門家※4、薬物
動態研究者等が体制の中に含まれていること、又は整備された機関等と契約して実施できること。
※5 責任試験統計家(日本計量生物学会)等の試験統計家の認定資格を有する又は統計検定(日本統計学会公認)
等の資格を有したうえで臨床試験統計家としての実績(例えば5試験以上等)があることが好ましい。
(o)提案する研究開発課題で実施する実験、研究に関する臨床試験又は非臨床試験等に関するプロトコー
ル又はプロトコール概要等(目的、期間、対象、選択基準、除外基準、症例又は検体数、観察内容、
介入内容、試薬、使用機器、統計的手法、研究体制等の当該実験又は研究を実施するために必要な情
報を含むこと)を資料番号4に記載すること。
(p)厚生科学研究における難病の実態把握、診断基準・診療ガイドライン等に資する調査研究から、
AMED における実用化を目指した基礎的な研究、診断法、医薬品等の研究開発まで、切れ目なく実臨
床につながる研究開発が行われるよう、研究開発提案における対象疾患をカバーする(対象とする)
厚生労働省難治性疾患政策研究事業の研究班(以下、政策班)が存在する場合は原則、連携すること
(連携先及び連携内容を明らかにすること。申請時に連携していない場合はその理由を明示する必要
があり、その場合であっても採択後にAMEDが指定する政策班と連携すること)。
「A-6. 国内開発未着手品の治験(医薬品ステップ2・ドラッグロス)」の条件
(q)治験を実施するために必要な全ての非臨床試験について、ライセンサー企業より入手した非臨床
試験報告書等をもとに研究開発提案書別紙(非臨床試験サマリー)及び研究開発提案書別紙(非臨
床試験ガントチャート)を記載し、その中で非臨床データパッケージの充足性について説明するこ
と。
(r)治験薬を保有するライセンサー企業より国内で治験を実施するための治験薬の提供又は購入の同
意が得られていること。
(s)治験薬を国内へ輸入するための方策と準備状況が示されていること。
(t)実施治験でPOC取得後の国内における製造販売承認申請の行動計画が立案できていること。
(u)AMEDとの契約締結後、1年以内に治験届を提出できること。
(v)難病患者に関するデータベース等を活用するなどして、短期間に予定被験者数を登録できる体制
が整備されている、又は初年度中に整備して実施できること(症例登録計画、予定登録数の事前調
査等、根拠となるデータを明示すること)。
(w)治験(多施設で実施する場合は多施設共同治験)を実施できる体制や専門家(当該医薬品の対象
となる疾患に関わる臨床専門家、生物統計家※5、臨床薬理専門家、薬事専門家等)が関与する体
制が整備されていること、医薬品の創製から製剤化までを網羅的に評価できる創薬化学等の専門家
※4、薬物動態研究者等が体制の中に含まれていること、又は整備された機関等と契約して実施で
きること。
※5 責任試験統計家(日本計量生物学会)等の試験統計家の認定資格を有する又は統計検定(日本
統計学会公認)等の資格を有したうえで臨床試験統計家としての実績(例えば 5 試験以上等)があ
ることが好ましい。
(x)提案する研究開発課題で実施する実験、研究に関する臨床試験又は非臨床試験等に関するプロト
コール又はプロトコール概要等(目的、期間、対象、選択基準、除外基準、症例又は検体数、観察
内容、介入内容、試薬、使用機器、統計的手法、研究体制等の当該実験又は研究を実施するために
必要な情報を含むこと)を資料番号4に記載すること。
(y)厚生科学研究における難病の実態把握、診断基準・診療ガイドライン等に資する調査研究から、
AMED における実用化を目指した基礎的な研究、診断法、医薬品等の研究開発まで、切れ目なく実
臨床につながる研究開発が行われるよう、研究開発提案における対象疾患をカバーする(対象とす
る)厚生労働省難治性疾患政策研究事業の研究班(以下、政策班)が存在する場合は原則、連携す
ること(連携先及び連携内容を明らかにすること。申請時に連携していない場合はその理由を明示
する必要があり、その場合であっても採択後にAMEDが指定する政策班と連携すること)。
■B. 希少難治性疾患に対する画期的な再生・細胞医療・遺伝子治療の実用化に関する研究分野
(1)公募研究開発課題名
B-1.再生・細胞医療・遺伝子治療のシーズ探索研究(再生等ステップ0)
B-2.再生・細胞医療・遺伝子治療の治験準備(再生等ステップ1)
B-3.再生・細胞医療・遺伝子治療の治験(再生等ステップ2)
(2)採択条件
【共通部分】
(a)再生・細胞医療・遺伝子治療について、治験あるいは申請までの研究開発の経験が研究代表者にあ
ること、又は経験がある研究者(アカデミア・企業は問わない)が体制に加わっていること(提案
書【協力体制】に該当者を記入すること)。その開発で得られた成果について提案書において説明が
なされていること。
(b)対象とする疾患が特定され希少難治性疾患※1であること。その疾患の現状(既存及び先行開発中の
医薬品等医療技術など)について調査方法・調査実施時期等根拠を示した上で、提案する治療法の優
位性を含むTPP(Target Product Profile)※2が明記されていること。
※1「希少性」、「原因不明」、「効果的な治療方法未確立」、「生活面への長期にわたる支障」の4 要件を満たす。
※2 想定効能・効果(有効性が期待される疾患の症状)、ポジショニング(医療技術における位置づけ、アンメ
ットメディカルニーズの充足性)、有効性(臨床的に受け入れられる基準を満たしうることを、in vivo 評価結果
を元に明示する)、安全性上の課題(想定される毒性所見、in vivo 評価による安全域評価実現可能性、毒性バイ
オマーカーの有無)、用法、各構成体の「形状、構造、成分」等、臨床開発における課題などを意味する。開発
継続の判断基準についても想定があれば記載すること。
【公募研究開発課題毎の条件】
「B-1.再生・細胞医療・遺伝子治療のシーズ探索研究(再生等ステップ0)」の条件
(c)「(3)求められる成果(a)」に記載された成果を求めるものであり、研究の主たる部分がシーズ
探索であること。
「B-2.再生・細胞医療・遺伝子治療の治験準備(再生等ステップ1)」の条件
(d)治験又は再生医療等安全確保法に則した臨床研究を実施するために必要な全ての非臨床試験が研究
開発期間内に完了する計画であること。また、既に行った非臨床試験及び今後行おうとする非臨床試
験について非臨床試験報告書等をもとに研究開発提案書別紙(非臨床試験サマリー)及び研究開発提
案書別紙(非臨床試験ガントチャート)を記載すること。
(e)治験製品と品質の一貫性が求められる非臨床試験で使用する被験製品、及び品質試験、製剤処方製
法検討用の被験製品の製造に用いる原材料等の調達が済んでいるか、あるいは調達が可能であること
の根拠を記載すること。
「B-3.再生・細胞医療・遺伝子治療の治験(再生等ステップ2)」の条件
(f)治験又は再生医療等安全確保法に則した臨床研究を実施するために必要な全ての非臨床試験につい
て、非臨床試験報告書等をもとに研究開発提案書別紙(非臨床試験サマリー)及び研究開発提案書別紙
(非臨床試験ガントチャート)を記載し、その中で非臨床データパッケージの充足性について説明す
ること。
(g)製造販売承認申請を実施する導出予定企業名及び導出予定時期が記載されており、本研究にて臨床
POC が取得できた場合は当該企業が承認申請を担当することに同意したことを示す記録(メール等で
可)が提出されていること。なお、AMEDとの契約締結後1年以内に、本件についての契約書を研究
開発代表者と当該企業にて締結することとし、当該企業の権利、競争上の地位その他正当な利益を害
するおそれがある情報を除き、AMEDが契約内容を閲覧することを承諾すること。
(h)導出予定企業の協力内容が明記され、評価(事前・中間・事後)や進捗管理の際に当該企業等の担
当者が同席すること。
(i)対象とする製剤等の入手方法(企業等から供与、購入、自施設で製造、委託製造)が明記されてい
ること。
(j)AMEDとの契約締結後、半年以内に治験が開始できる開発計画であること。
(k)難病患者に関するデータベース等を活用するなどして、短期間(1 年以内を推奨)に予定被験者数
を登録できる体制が整備されている、又は初年度中に整備して実施できること(症例登録計画、予定
登録数の事前調査等、根拠となるデータを明示すること)。
(l)治験(多施設で実施する場合は多施設共同治験)又は再生医療等安全確保法に則した臨床研究を実
施できる体制や専門家(生物統計家※3、臨床薬理専門家、薬事専門家等)が関与する体制が整備され
ていること、又は整備された機関等と契約して実施できること。
※3 責任試験統計家(日本計量生物学会)等の試験統計家の認定資格を有する又は統計検定(日本統計学会公認)
等の資格を有したうえで臨床試験統計家としての実績(例えば5試験以上等)があることが好ましい。
(m)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)に基づく遺伝子治
療技術を利用した製品を用いた治験又は再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療等安全
性確保法)に基づく臨床研究では製品のタイプに応じた長期フォローアップが必要なことに留意し、
治験終了後のフォローアップ計画も含む提案であること。
(n)原則、実験、研究に関する臨床試験又は非臨床試験等に関するプロトコールについて PMDA と協議
(再生医療等製品探索的試験開始前相談等)済みであること。提案書にはプロトコール概要(目的、期
間、対象、選択基準、除外基準、症例又は検体数、観察内容、介入内容、試薬、使用機器、統計的手法、
研究体制等の当該試験等を実施するために必要な情報を含むこと)を記載し、PMDA相談結果を添付す
ること。なお、当該試験の施行に際しコンパニオン診断薬(法)が必要な場合はそのための計画に関し
ても含めること。
(o)厚生科学研究における難病の実態把握、診断基準・診療ガイドライン等に資する調査研究から、
AMED における実用化を目指した基礎的な研究、診断法、医薬品等の研究開発まで、切れ目なく実臨
床につながる研究開発が行われるよう、研究開発提案における対象疾患をカバーする(対象とする)厚
生労働省難治性疾患政策研究事業の研究班(以下、政策班)が存在する場合は原則、連携すること(連
携先及び連携内容を明らかにすること。申請時に連携していない場合はその理由を明示する必要があり、
その場合であっても採択後にAMEDが指定する政策班と連携すること)。
≪引用元:公募要領p.7(2.2公募対象となる研究開発課題の概要について)参照≫
などの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。ただし、契約締結日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、AMED ではスタートアップ企業等を「中小企業※の内、設立10 年以内」と定義し、応募時や採択時、研究進捗確認時に、財務状況の健全性を確認していきます。※中小企業の定義は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)の定めるところによります。 なお、分担研究機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約時に必要な条件を満たすか確認が必要になります。分担研究機関は、代表研究機関と再委託研究開発契約を締結します。 所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途ご相談ください。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
(A) 国の施設等機関(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職、福祉職、指定職
又は任期付研究員である場合に限る。)
(B) 公設試験研究機関
(C) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
(D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
(E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
(F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定 する独立行政法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人及びその他特別の法律により設立された法人
(G) 非営利共益法人技術研究組合
(H) その他AMED理事長が適当と認めるもの
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。
(6)スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著しく脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著しく脆弱で委託研究開発契約の履行能力がないと判断されると、契約締結できない場合があります。)
≪引用元:公募要領p.50(3.1応募資格者)参照≫
提案書類受付期間 :令和6年10月18日(金)~令和6年12月2日(月)【午前12時】(厳守)
書面審査 :令和6年12月中旬 ~令和7年1月上旬(予定)
ヒアリング審査 :令和7年1月31日(金)~2月7日(金)(予定)
採択可否の通知 :令和7年3月上旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日 :令和7年4月上旬(予定)



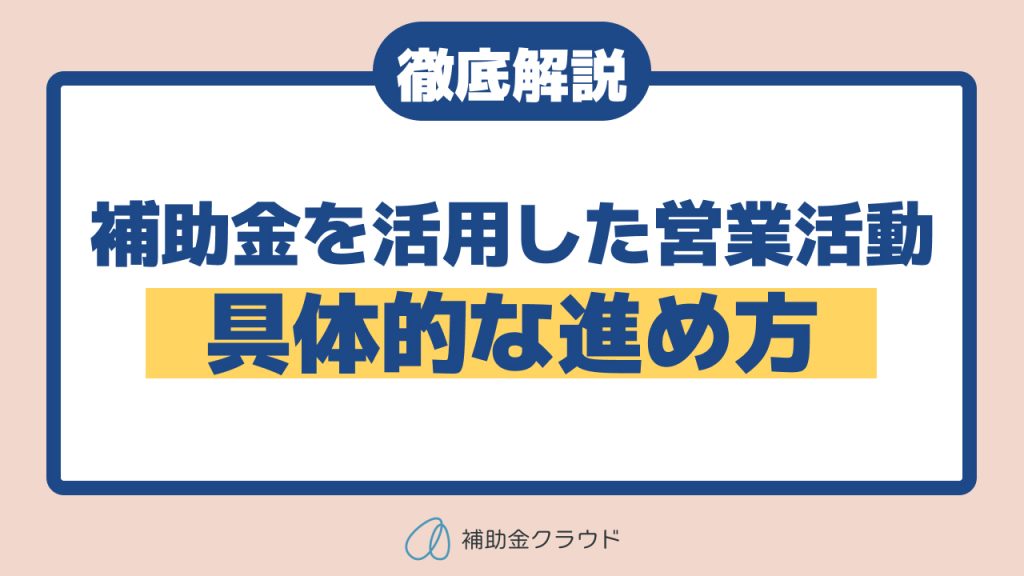
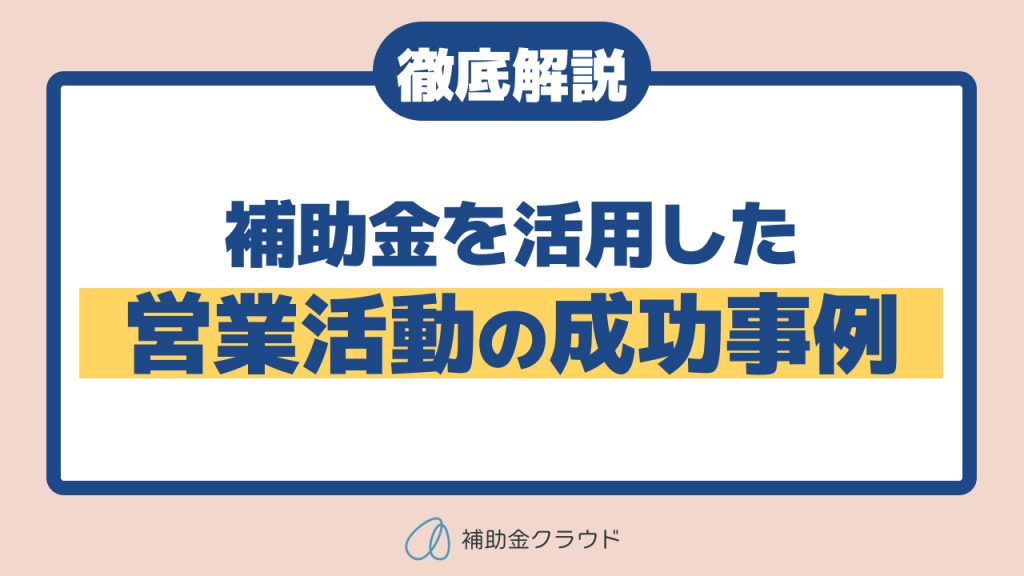
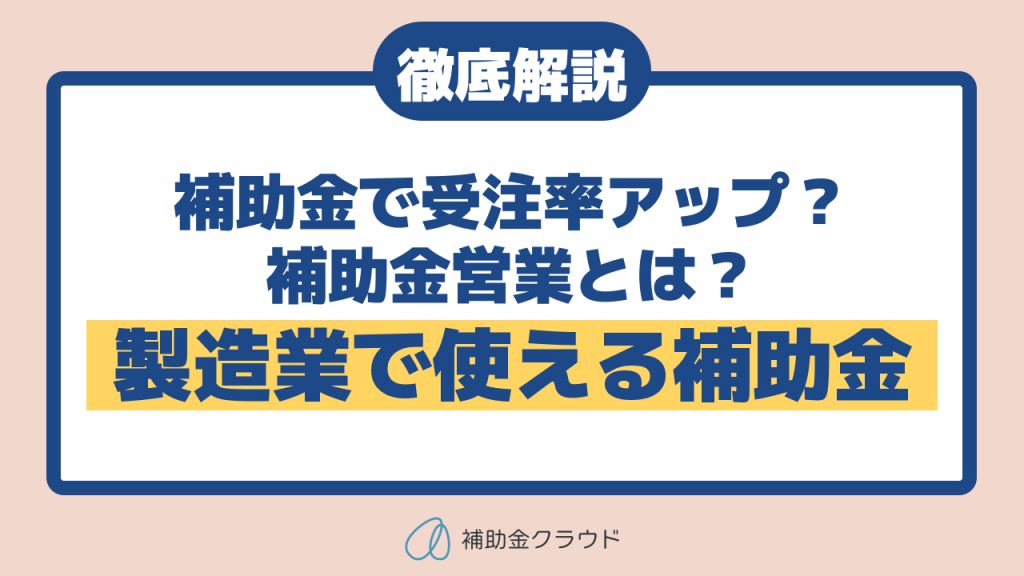
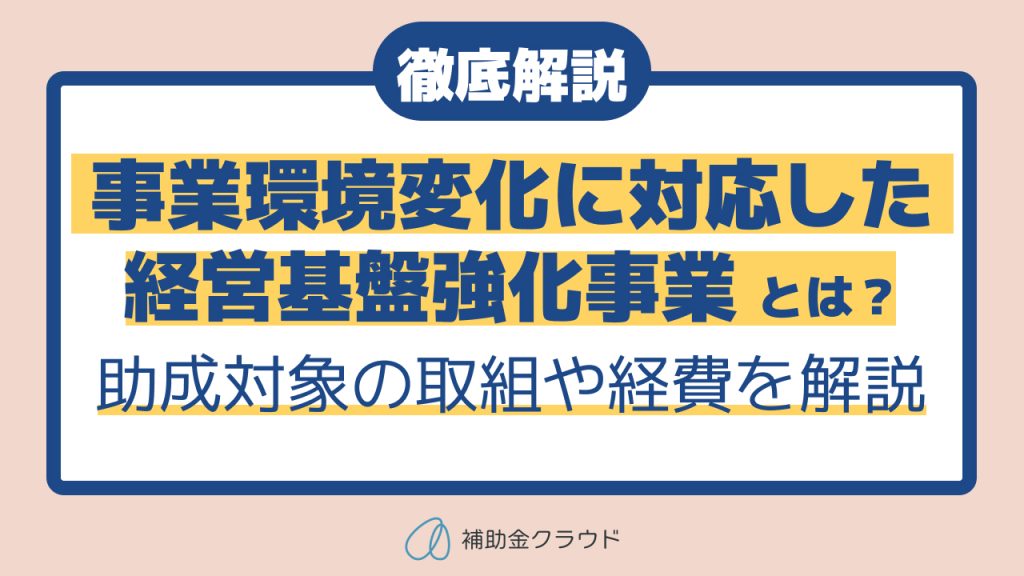
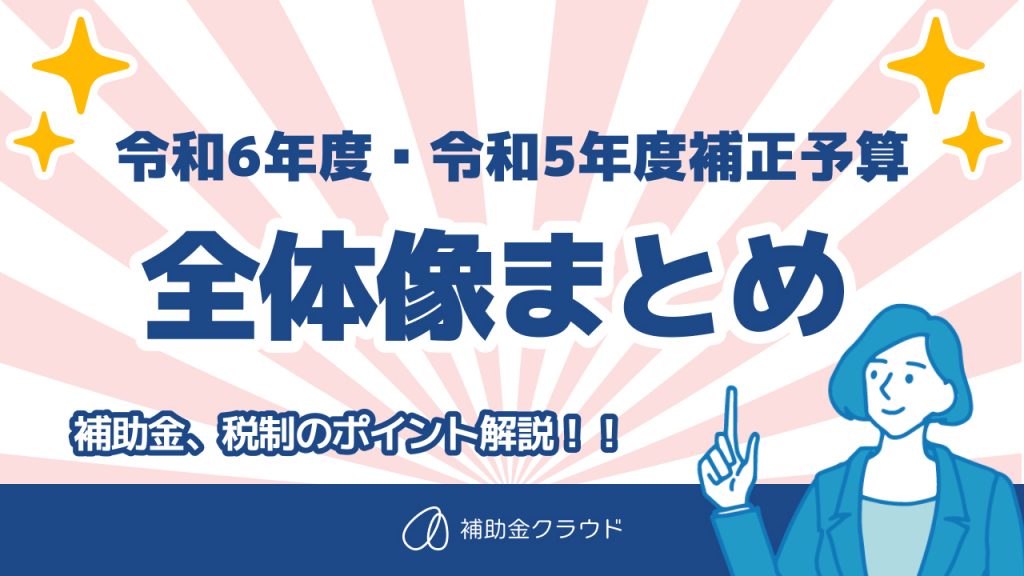
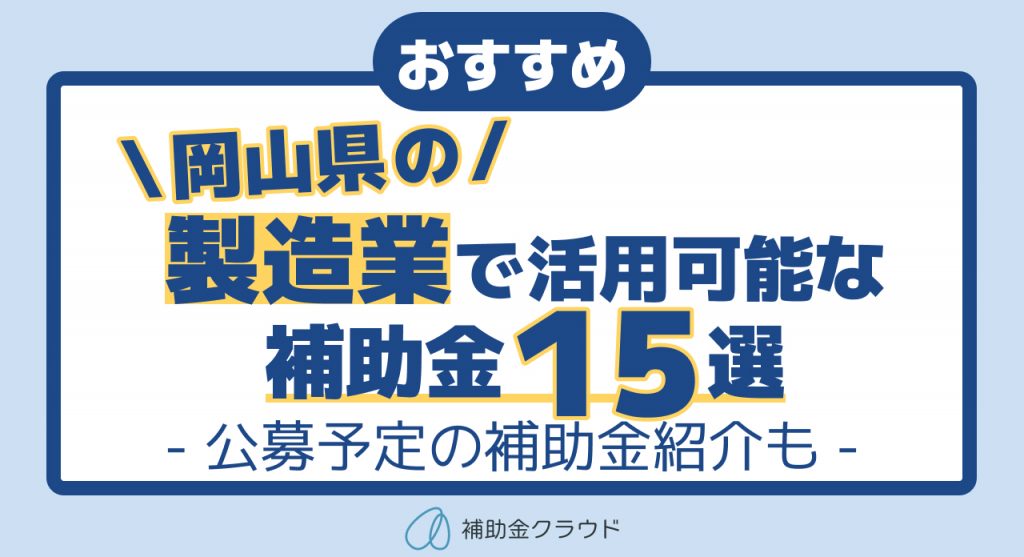
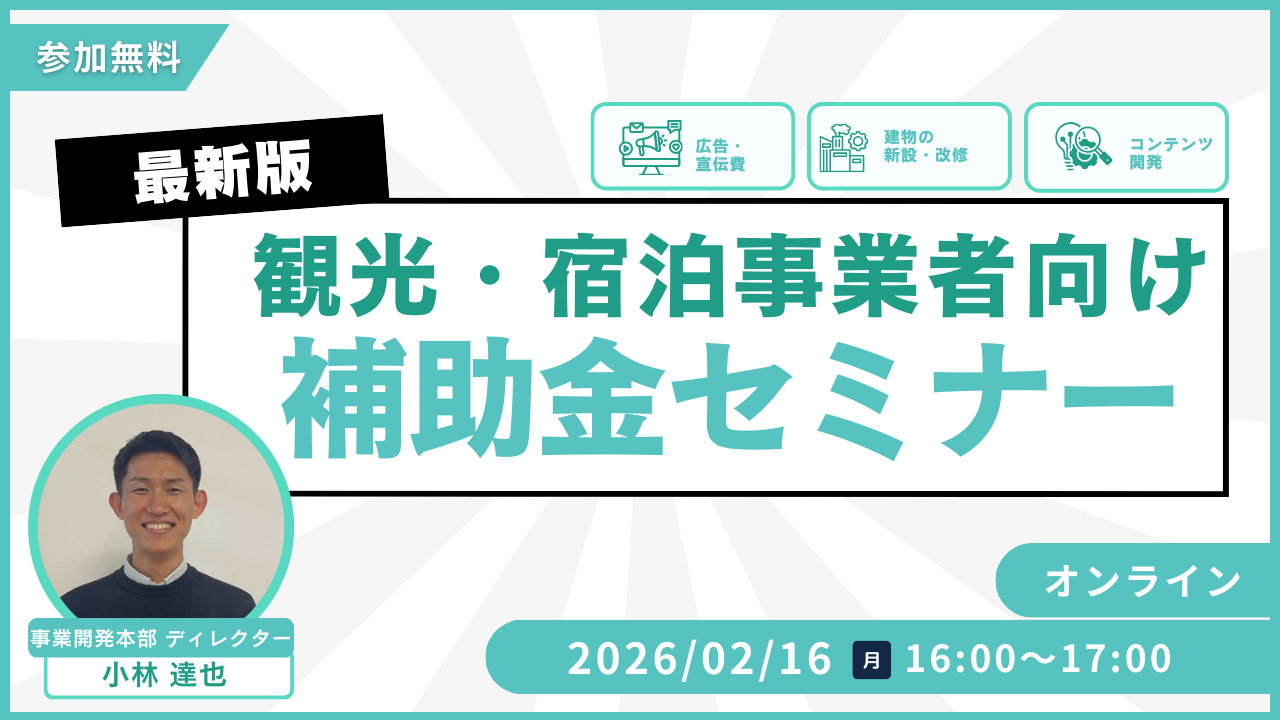


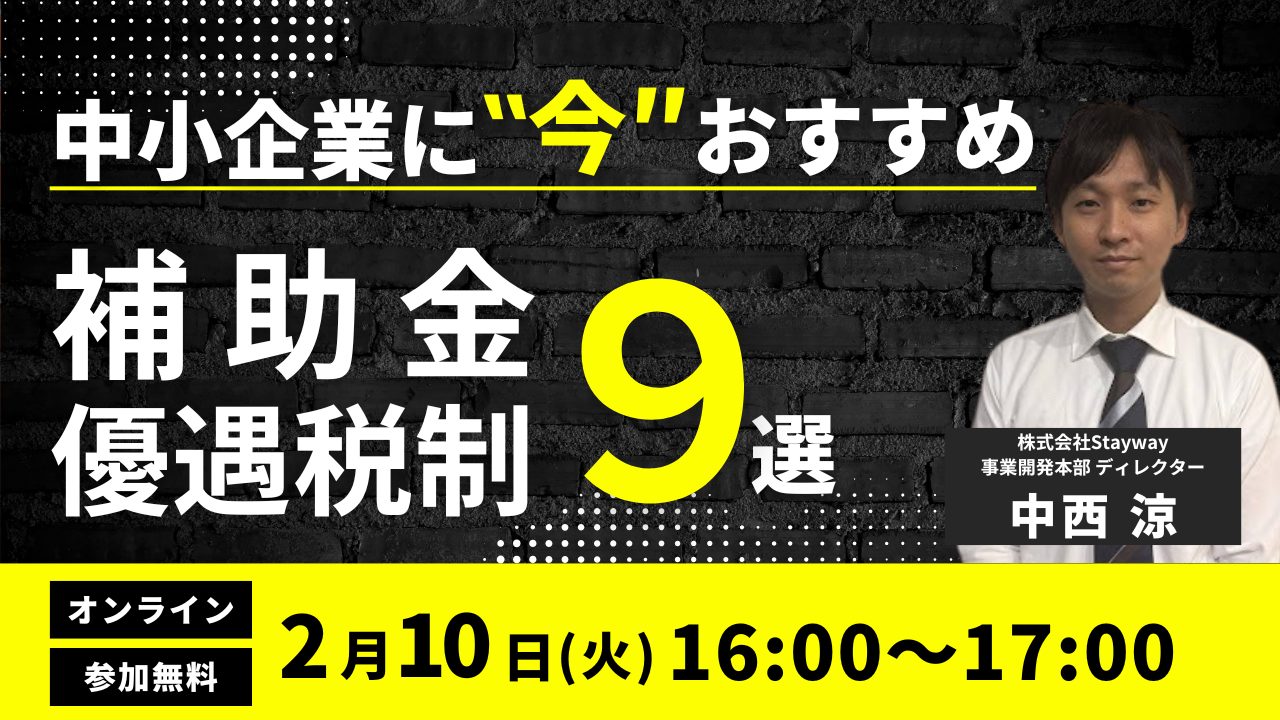

関連する補助金