全国:令和7年度(令和6年度補正)国産野菜サプライチェーン連携強化緊急対策事業(サプライチェーン連携強化推進事業)/第4次公募
2025年1月08日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
我が国で流通する野菜は、家計消費用はほぼ全てが国産で賄われているのに対し、加工・業務用は3割を輸入に依存している。これは、加工・業務用野菜は、定時・定量・定価格・定品質といった供給の安定性が求められているところ、輸入野菜に比べると国産野菜は安定供給体制が整っていないことに起因している。
このことに加えて、頻発化する酷暑等の異常気象により、国内における野菜生産の不安定化は一層増しており、食料安全保障上のリスクに備える観点から、国産野菜サプライチェーンの連携を強化し、周年安定供給体制を早急に構築することが必要である。
このため、本事業により、実需者のニーズに対応した品種の栽培実証、農業機械や予冷・貯蔵庫のリース導入のほか、生育予測システムや集出荷システムの導入、システム連携、電子タグ付き大型コンテナのリース導入等の複数産地と実需者が連携して行う生産・流通体系の合理化の取組を支援し、国産野菜サプライチェーンの連携強化を支援することとする。
■下記にかかる費用
(1)システム導入
(2)システム連携
(3)大型コンテナ等のリース導入
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
国産野菜サプライチェーン連携強化緊急対策事業(サプライチェーン連携強化推進事業)
国産野菜のサプライチェーン連携強化に必要な複数産地と実需者が連携して行う合理化の取組について、生育予測システムや集出荷システムの導入、システム連携、電子タグ付き大型コンテナのリース導入等による実証を行う。
2025/08/18
2025/09/05
(1)都道府県
(2)市町村
(3)公社
(4)農業協同組合連合会
(5)農業協同組合
(6)農業者の組織する団体
(7)民間事業者
(8)特認団体
(9)コンソーシアム(農産局長が別に定める場合に限る。)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
(1)公募期間
令和7年8月18日(月曜日)から令和7年9月5日(金曜日)まで
(2)提出部数
郵送等の場合は、各2部(詳細は公募要領等を御参照ください。)
農林水産省農産局園芸作物課 TEL 03-3501-4096(直通)
我が国で流通する野菜は、家計消費用はほぼ全てが国産で賄われているのに対し、加工・業務用は3割を輸入に依存している。これは、加工・業務用野菜は、定時・定量・定価格・定品質といった供給の安定性が求められているところ、輸入野菜に比べると国産野菜は安定供給体制が整っていないことに起因している。
このことに加えて、頻発化する酷暑等の異常気象により、国内における野菜生産の不安定化は一層増しており、食料安全保障上のリスクに備える観点から、国産野菜サプライチェーンの連携を強化し、周年安定供給体制を早急に構築することが必要である。
このため、本事業により、実需者のニーズに対応した品種の栽培実証、農業機械や予冷・貯蔵庫のリース導入のほか、生育予測システムや集出荷システムの導入、システム連携、電子タグ付き大型コンテナのリース導入等の複数産地と実需者が連携して行う生産・流通体系の合理化の取組を支援し、国産野菜サプライチェーンの連携強化を支援することとする。



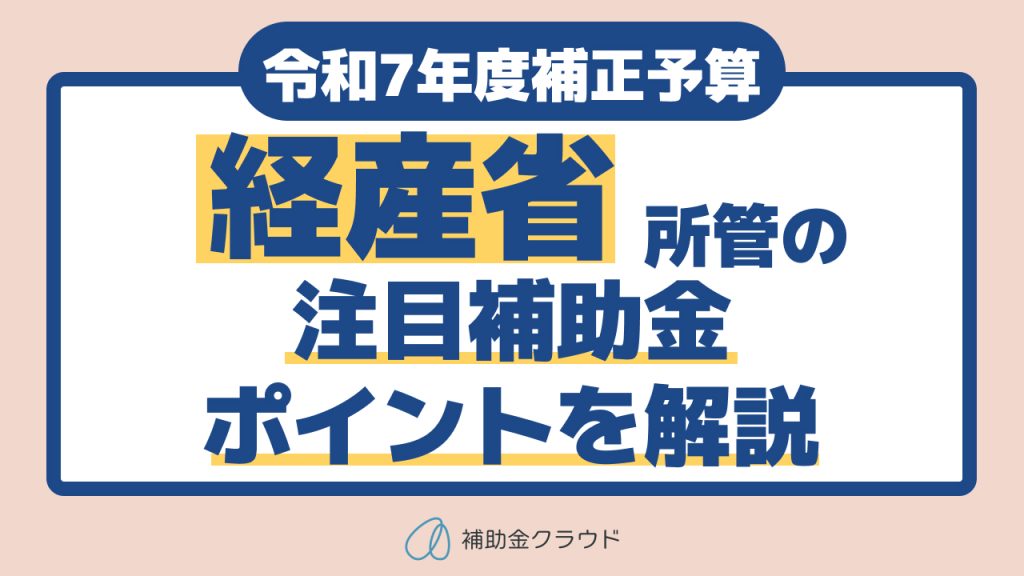
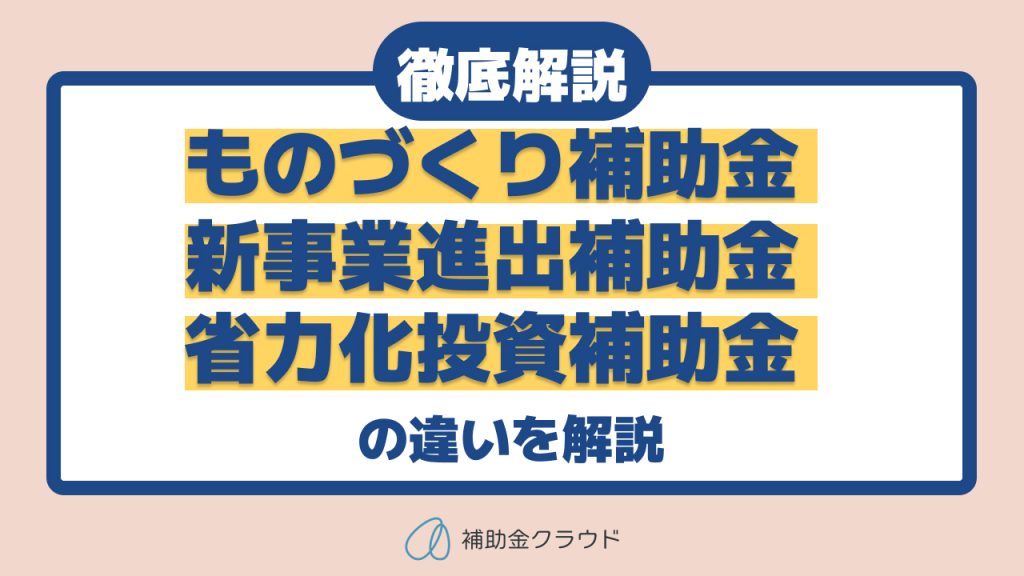
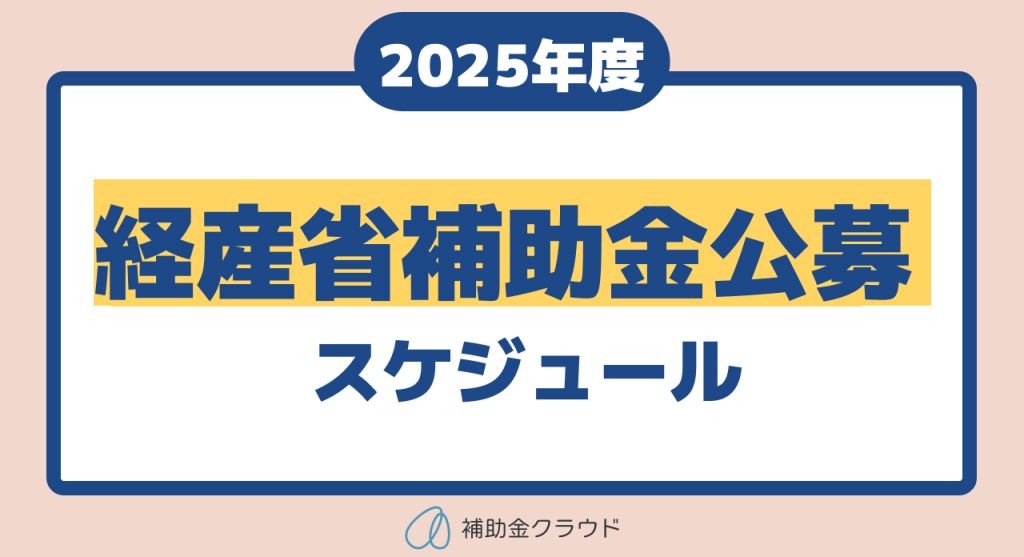
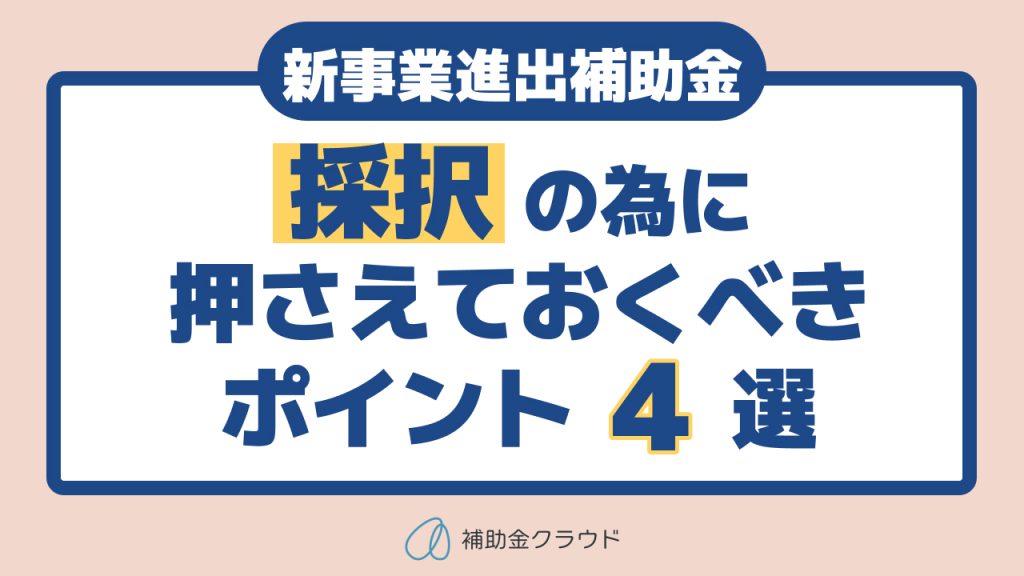
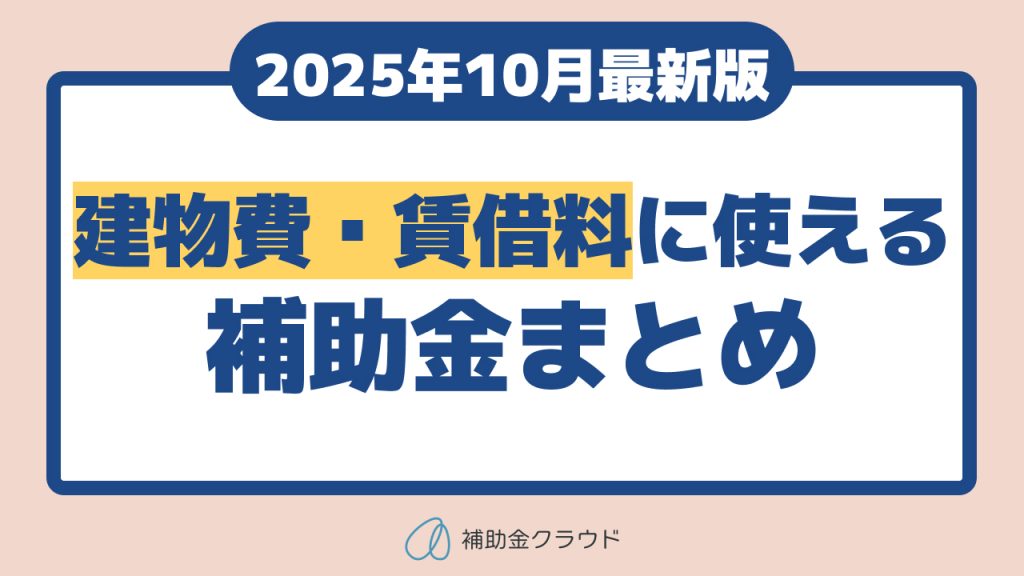
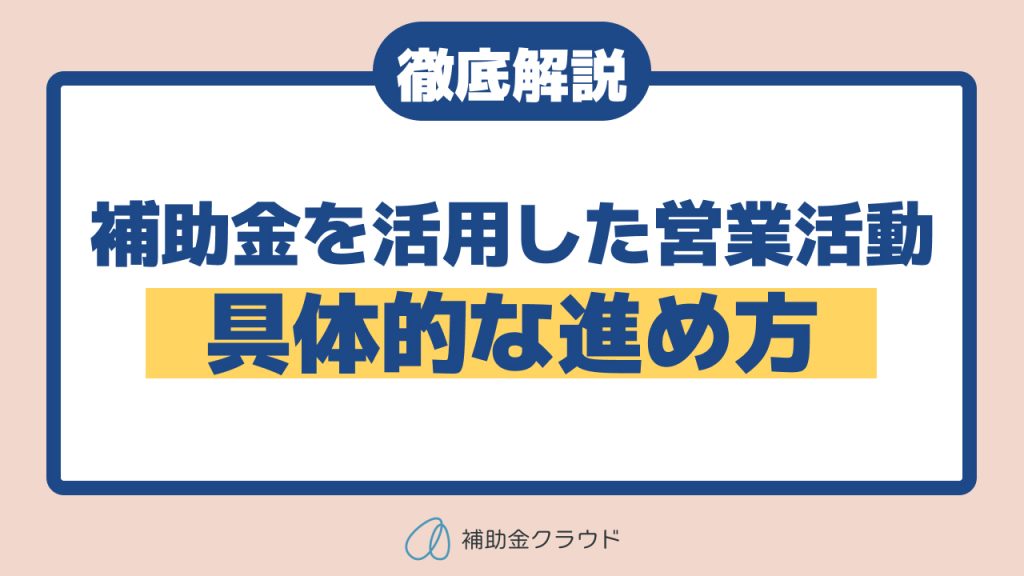
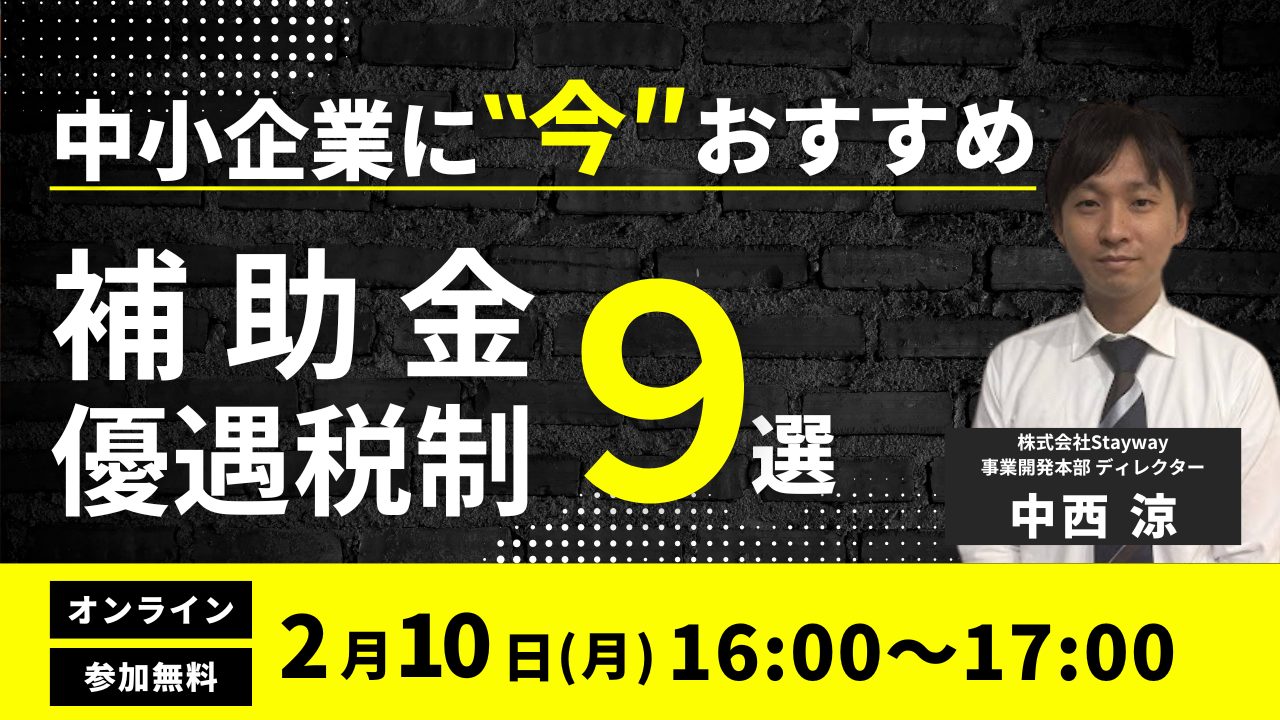


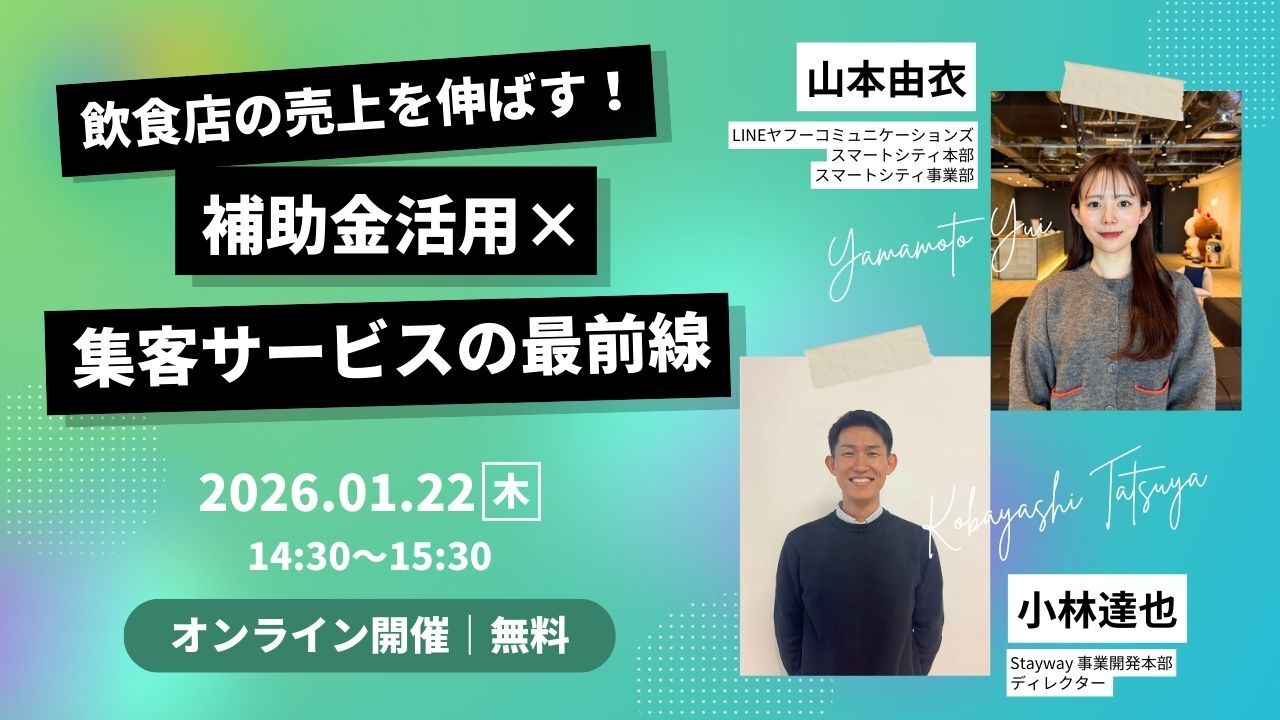

関連する補助金