全国:令和7年度 環境保全型農業直接支払交付金
2023年4月17日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
平成23年度から化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援しています。
(平成27年度から「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年法律第78号)に基づき、日本型直接支払(多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金)の一つとして実施しています。)
※ 本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。
申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。
農業者団体等が別紙第1の4に規定する活動に要する経費に充てるため、市町村が農業者団体等に対し交付金を交付するのに要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
支援の対象となる農業生産活動は、農業生産に由来する環境への負荷の低減、地球温暖化の防止、生物多様性の保全等に資する以下の(1)から(6)までに掲げる取組であって、農産局長が別に定める要件を満たすものとする。
支援の対象となる(7)に掲げる活動は、農産局長が別に定める要件を満たすものとする。
(1)化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組
(2)5割低減の取組と緑肥の施用を組み合わせた取組
(3)5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組
(4)5割低減の取組と総合防除(有害動植物の防除のうち、その発生及び増加の抑制並びにこれが発生した場合における駆除及びまん延の防止を適時で経済的なものにするために必要な措置を総合的に講じて行うものをいう。以下同じ。)を組み合わせた取組
(5)有機農業の取組
(6)その他都道府県知事が特に必要と認める取組(以下「地域特認取組」という。)
(7)有機農業の取組の拡大に向けた活動(以下「取組拡大加算」という。)
2023/04/01
2026/03/31
① 農業者の組織する団体
複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織(以下「農業者団体」という。)が対象になります。
農業者団体は、代表者、組織の規約を定めるとともに、組織としての口座を開設してください。
② 一定の条件を満たす農業者
単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)は、以下のいずれかの条件に該当するとともに、市町村が特に認める場合に対象になります。
・集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
・複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く。)
■支援の対象となる農業者の要件
農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者が環境保全型農業直接支払交付金の支援の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。
・主作物について販売することを目的に生産を行っていること
・環境負荷低減のチェックシートの各取組について、チェックした上で提出すること
・環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等。以下「推進活動」といいます。)に取り組むこと
■対象農地
交付金の交付の算定の対象となる農地は、次のいずれかの農地とする。
(1)農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和 44 年法律第 58号)第6条第1項に基づき指定された農業振興地域をいう。)内に存する農地
(2)生産緑地地区(生産緑地法(昭和 49 年法律第 68 号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区をいう。)内に存する農地
■交付金を利用したい方へ
取組を行う上での詳細な要件等は、取組を行う農地が所在する市町村にご確認をお願いします。
なお、本事業の申請受付事務や交付金の負担を行うことが難しい市町村もあることから、あらかじめ農地の所在する市町村に、本事業の申請が可能かどうかをお尋ねください。
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による本交付金の電子申請が行えます。
電子申請には、デジタル庁が提供するgBizID (ジービズアイディ)の取得が必要となりますので、農業者団体又は法人名でアカウントを取得してください。
農産局農業環境対策課 担当者:環境直接支払班 代表:03-3502-8111(内線4748) ダイヤルイン:03-6744-0499
平成23年度から化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援しています。
(平成27年度から「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年法律第78号)に基づき、日本型直接支払(多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金)の一つとして実施しています。)
※ 本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。
申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。



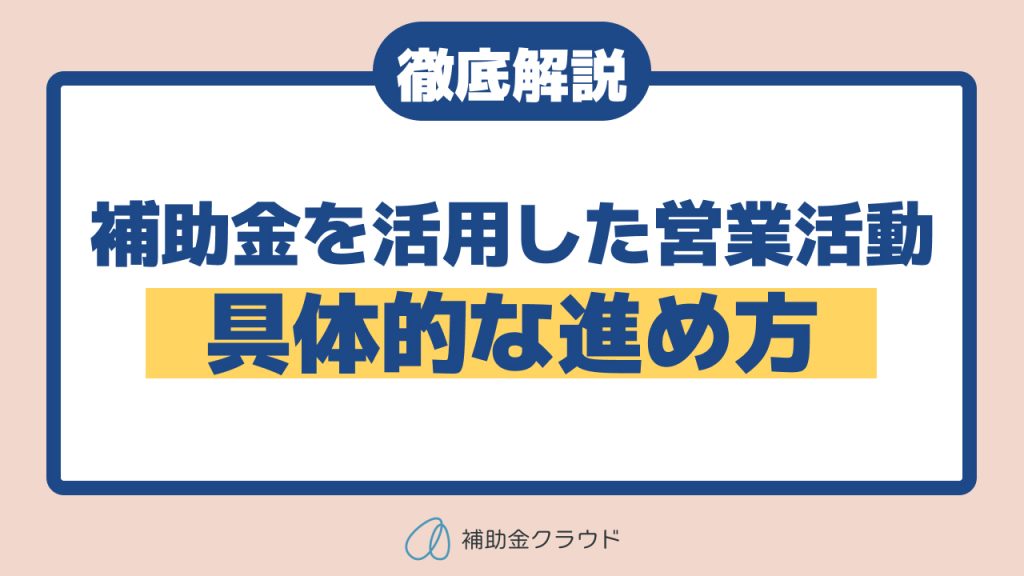
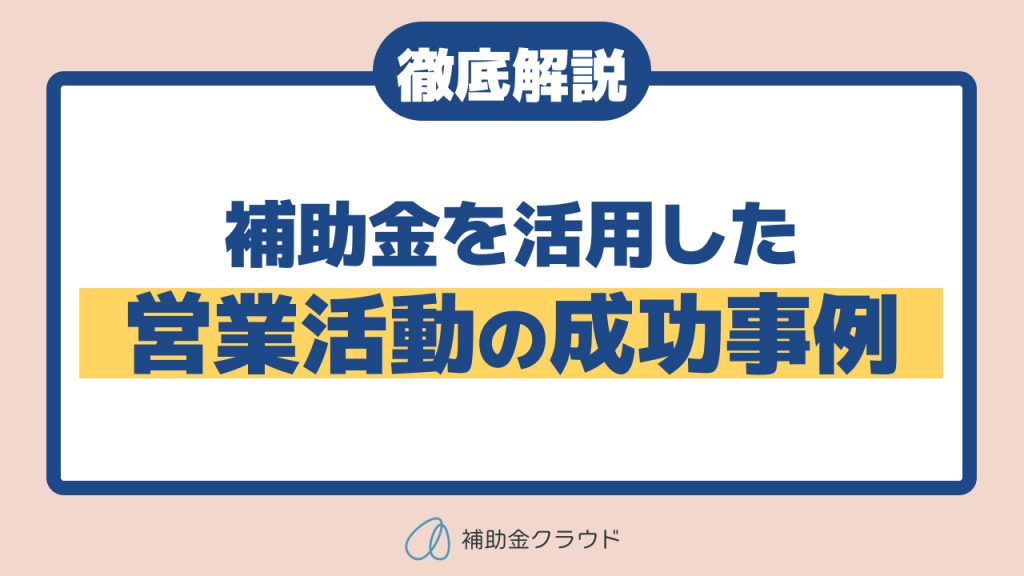
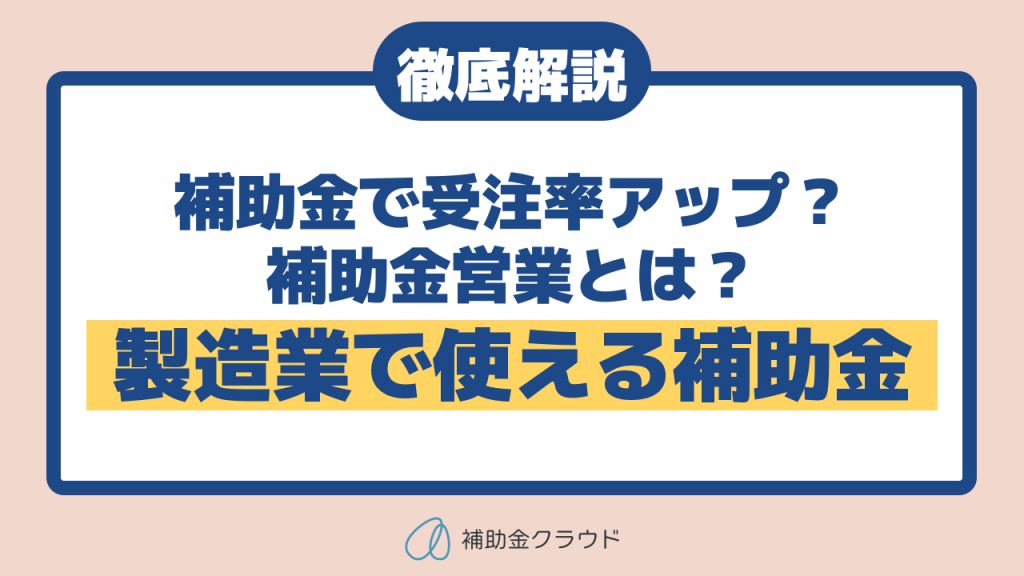
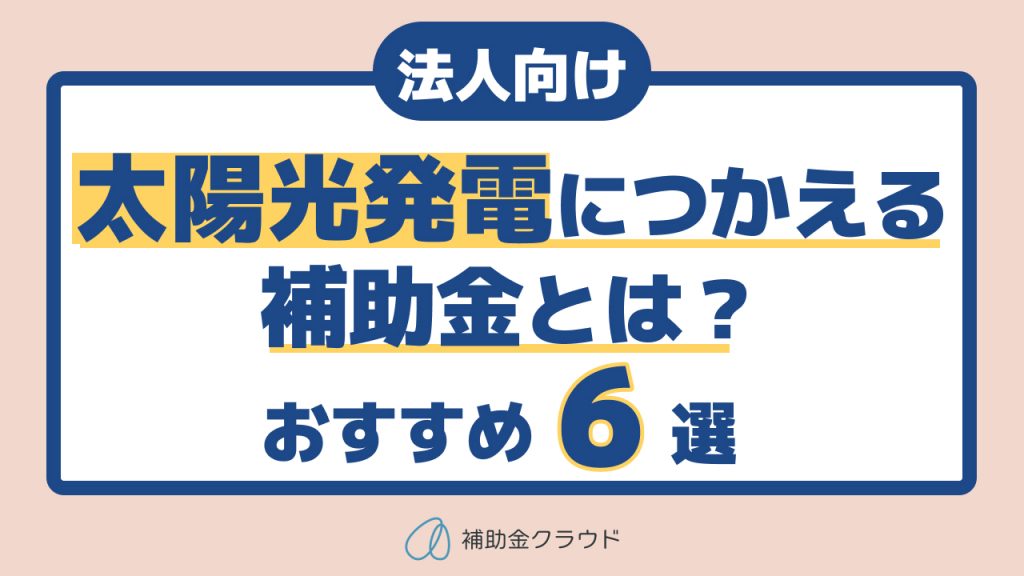
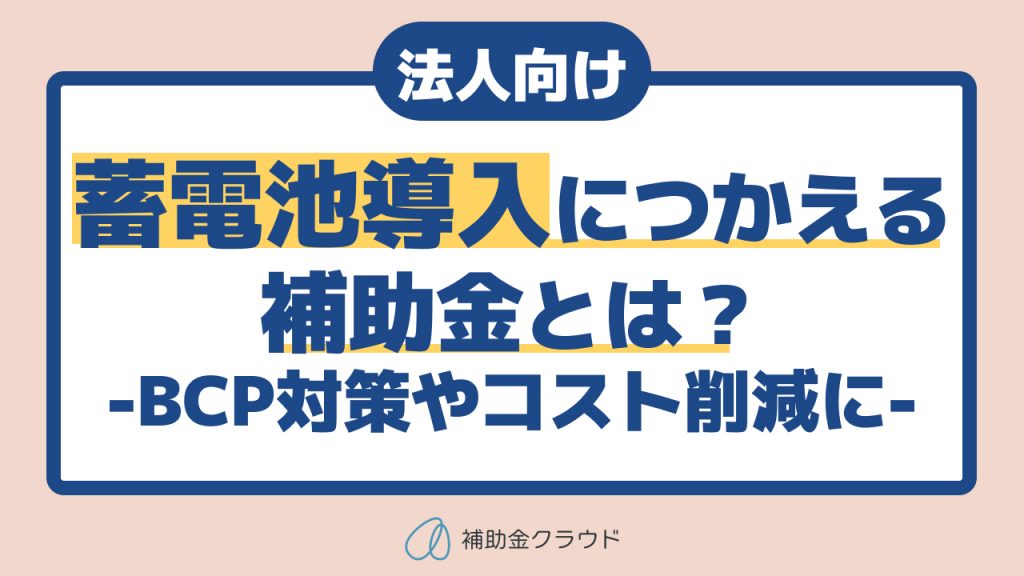
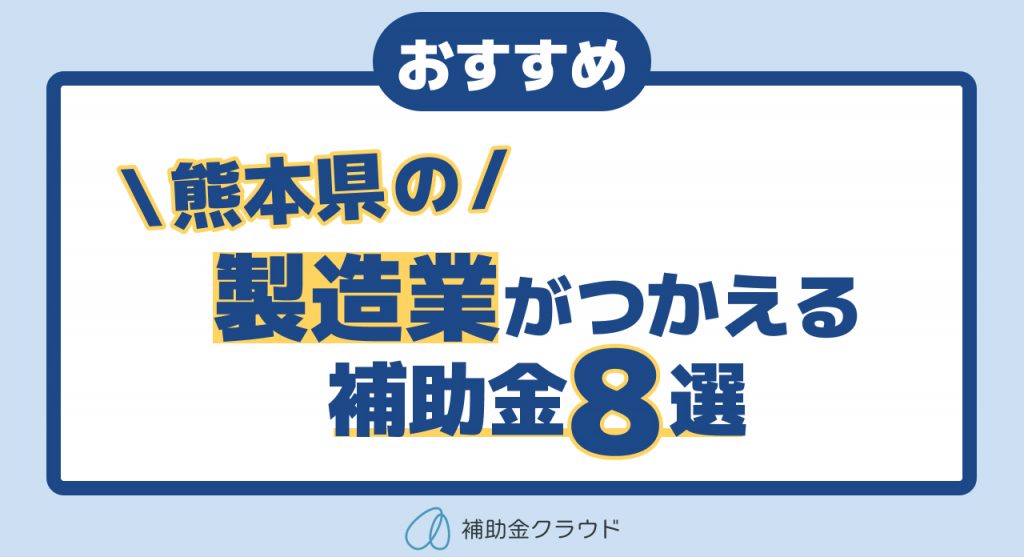


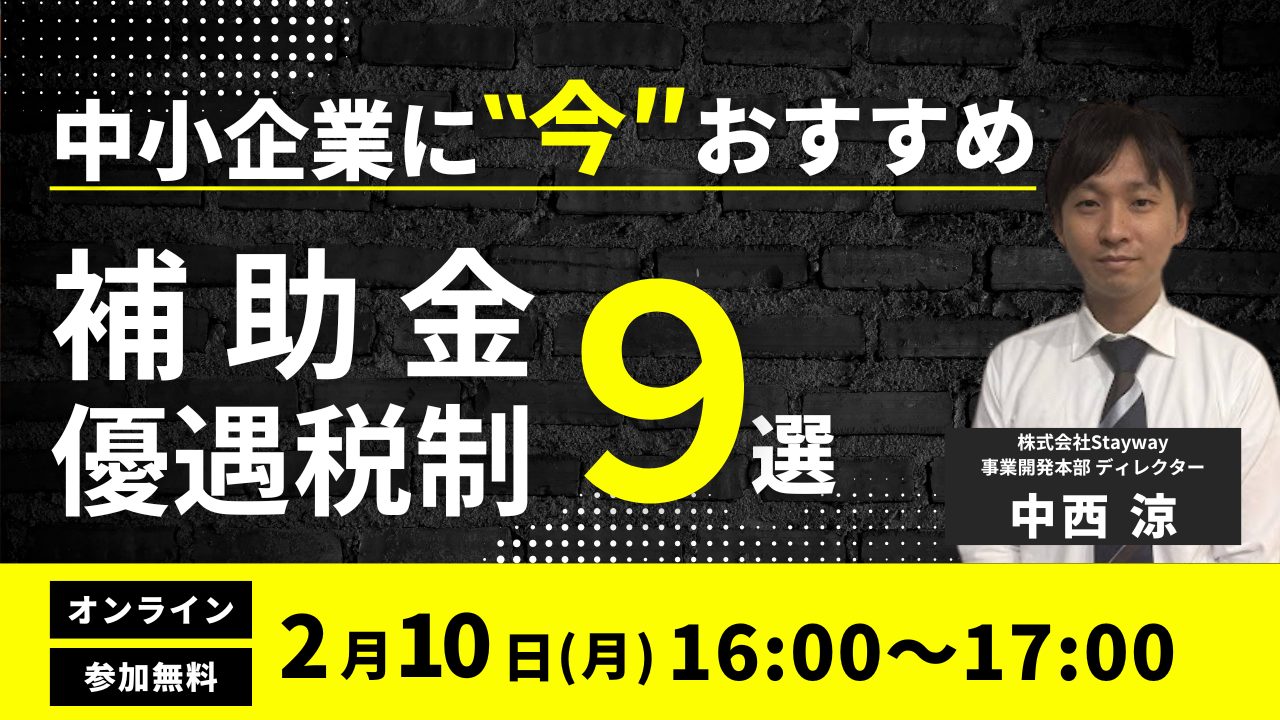


関連する補助金