企業が複数の金融機関から借入を行う際、各金融機関への返済条件をどのように設定すれば公平性を保てるのでしょうか。その解決策として注目されるのが「プロラタ方式」です。
この記事では、プロラタ方式の基本的な概念や種類、そして実施手順について解説します。複数の金融機関への返済を最適化する方法の理解や、資金繰り改善の参考にしてください。
プロラタ方式とは?
プロラタ方式とは、企業が複数の金融機関から借入を行っている際に、各金融機関への返済額を借入金額に応じて比例的に決定する返済方法を指します。
この方式は、全ての金融機関に対して公平な返済条件を設定することを目的としており、リスケジュール(返済条件の変更)を行う際に利用されます。
各金融機関の借入残高を確認し、それに応じて返済額を按分するので、金融機関間での不公平感を解消し、企業の資金繰りを円滑に進められます。
プロラタ方式の種類
プロラタ方式には、以下の2つがあります。
・残高プロラタ
・信用プロラタ
これらは、借入金の返済額を決定する際の基準が異なり、企業の財務状況や金融機関との関係性に応じて適切な方法が選択されます。
残高プロラタ
残高プロラタは、各金融機関からの借入残高に基づいて返済額を決定する方式です。具体的には、借入総額に占める各金融機関の借入残高比率に比例して、返済額が設定されます。
例えば、借入総額が1,000万円で、月々の返済額が20万円の場合の按分は、以下の表のとおりです。
|
金融機関 |
借入残高 |
借入残高比率 |
月々の返済額 |
|
A銀行 |
500万円 |
50% |
10万円(20万円 × 50%) |
|
B銀行 |
300万円 |
30% |
6万円(20万円 × 30%) |
|
C銀行 |
200万円 |
20% |
4万円(20万円 × 20%) |
信用プロラタ
信用プロラタとは、各金融機関の無担保部分の借入残高に基づいて返済額を決定する方式です。具体的には、担保が設定されていない借入部分の残高割合に応じて、各金融機関への返済額を按分します。
この方法は、債権回収の保証がない無担保部分の返済を優先することで、金融機関間の公平性を保つことを目的としています。
特に、担保の有無や評価額を考慮するため、無担保融資を行っている金融機関にとっては、より適切な返済配分ができる方法です。
例えば、以下の条件で総額1,000万円の借入がある場合を見ていきましょう。
|
金融機関 |
借入残高 |
担保金額 |
無担保部分の借入残高 |
|
A銀行 |
500万円 |
200万円 |
300万円 |
|
B銀行 |
300万円 |
200万円 |
100万円 |
|
C銀行 |
200万円 |
100万円 |
100万円 |
無担保部分の総額は500万円(300万円 + 100万円 + 100万円)となります。各金融機関の無担保部分の割合は以下の通りです。
|
金融機関 |
無担保部分の割合 |
|
A銀行 |
60%(300万円 / 500万円) |
|
B銀行 |
20%(100万円 / 500万円) |
|
C銀行 |
20%(100万円 / 500万円) |
月々の返済額が100万円の場合、各金融機関への返済額は以下のように計算されます。
|
金融機関 |
月々の返済額 |
|
A銀行 |
60万円(100万円 × 60%) |
|
B銀行 |
20万円(100万円 × 20%) |
|
C銀行 |
20万円(100万円 × 20%) |
プロラタ方式のメリットとデメリット
プロラタ方式のメリットとデメリットを、それぞれ見ていきましょう。
メリット
プロラタ方式の主なメリットは、複数の金融機関間での公平性を確保できる点です。各金融機関への返済額が借入額や担保に応じて比例的に決定されるため、特定の金融機関が優先されることなく、全ての金融機関が平等に扱われます。
また、プロラタ方式を採用することで、金融機関のリスクが分散され、融資を受けやすくなる可能性があります。これは、全ての金融機関が同時に返済を受けるため、返済の遅延や不履行のリスクが低減されるためです。
デメリット
一方、プロラタ方式の主なデメリットは、各金融機関の借入残高や返済条件を正確に把握し、適切に按分する必要があるため、計算が複雑になる点です。特に、無担保部分や担保評価額を考慮する場合、計算はさらに複雑化します。
さらに、プロラタ方式の採用には全ての金融機関の同意が必要であり、交渉が困難になる場合があります。各金融機関の利害が異なるため、全ての関係者の合意を得るには慎重な調整と交渉が必要です。
プロラタ方式を実施する際の流れ
プロラタ方式を適切に実施するためには、明確な手順と計画が不可欠です。プロラタを実施する際の流れを、次に挙げる5つの段階ごとに見ていきましょう。
1. 借入残高の確認
2. 金融機関との交渉
3. 返済計画の作成
4. 計画の調整
5. 合意の形成
1. 借入残高の確認
プロラタ方式を進める第一歩は、返済計画の基盤を築くために、各金融機関からの借入残高を正確に把握することです。
具体的には、各金融機関から提供される返済予定表や残高証明書を活用し、最新の借入状況を確認します。この作業は、税理士や公認会計士などの専門家に依頼することで、より正確かつ効率的に進めていけるでしょう。
2. 金融機関との交渉
借入残高の確認が完了したら、次に各金融機関に対してプロラタ方式での返済について同意を得る交渉を行います。この際、全ての金融機関に対して同時に交渉を行うことで、公平性と透明性を確保することが重要です。
3. 返済計画の作成
返済計画の作成は、まず各金融機関からの借入残高や担保の状況を詳細に分析し、現実的かつ持続可能な返済計画を策定します。この計画は、企業の財務状況と将来のキャッシュフロー予測を基に、各金融機関への返済額を比例的に割り当てるものです。
さらに、返済計画と並行して、事業計画の策定も不可欠です。事業計画では、今後の収益見通しや成長戦略を明確に示し、企業の返済能力を裏付けます。
4. 計画の調整
返済計画の初期案が完成したら、各金融機関との協議を通じて計画の調整を行います。このプロセスでは、各金融機関の意見や要望を取り入れながら、全関係者が納得できる計画を目指します。特に、返済条件や期間についての合意形成が重要です。
調整の際には、全ての金融機関に対して公平性を保つ姿勢が欠かせません。特定の金融機関が優遇されることなく、比例的な返済が行われるよう配慮します。
5. 合意の形成
返済計画の調整が完了したら、次に全ての金融機関から正式な同意を得るプロセスに進みます。この段階では、各金融機関が計画内容を十分に理解し、納得していることを確認することが重要です。
全ての関係者が同じ認識を持つことで、後のトラブルを防ぐことができます。必要に応じて、合意内容を明文化した書面を作成し、各金融機関と正式に契約を交わします。書面での合意は、後日の誤解や紛争を避けるためにも不可欠です。
まとめ
プロラタ方式は、複数の金融機関からの借入返済を公平かつ効率的に行うための手法として、多くの企業で採用されています。この方式を適切に実施することで、各金融機関との信頼関係を維持しつつ、企業の財務健全性を高められます。
しかし、プロラタ方式の導入には、各金融機関との綿密な交渉や、正確な借入残高の把握など、慎重な準備が欠かせません。導入を検討する際は専門家の助言を仰ぎながら、計画的に進めていきましょう。


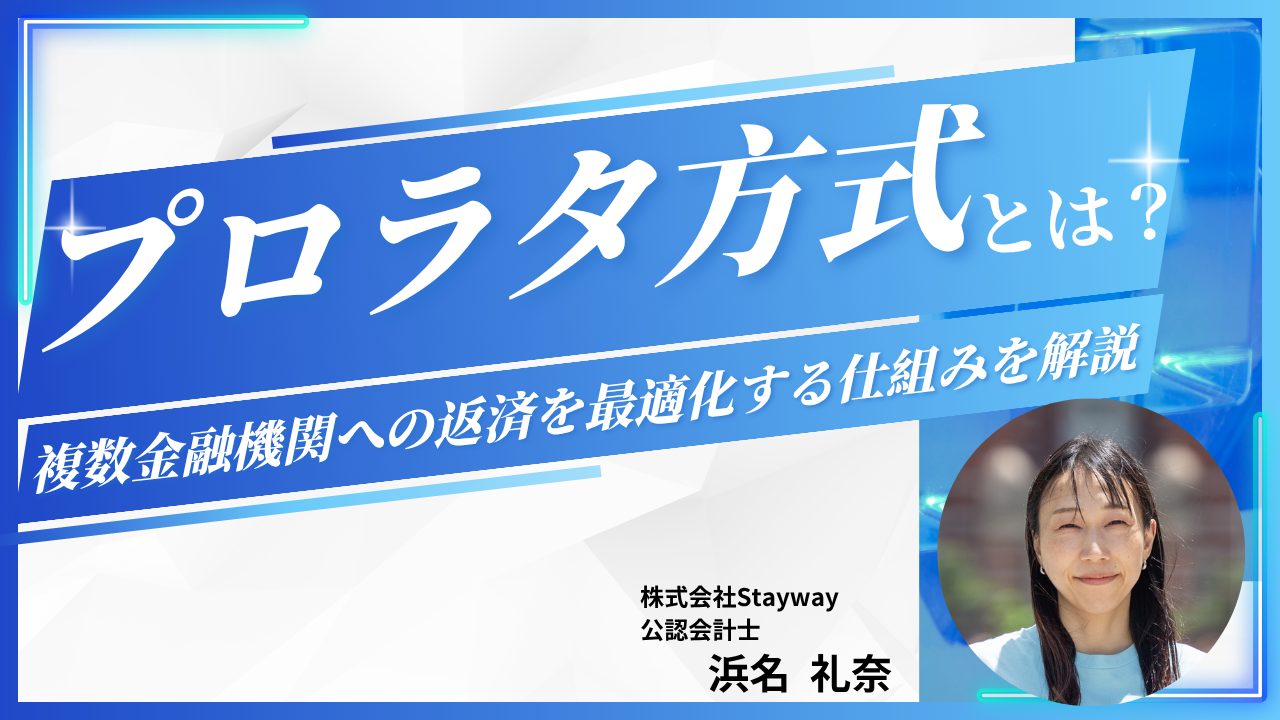




運営からのお知らせ