全国:令和7年度 持続的生産強化対策事業のうち養蜂等振興強化推進 (地域公募事業)
2024年2月12日
※本公募は、令和7年度政府予算案に基づくものであるため、成立後の予算の内容により、事業内容、予算額等に変更があり得ることをあらかじめ御了承の上、御応募ください。
また、本事業の活用を検討されている方は、地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局。以下同じ。)に必ず御相談ください。
-----
養蜂振興法(昭和 30 年法律第 180 号)の蜜源植物の保護増殖、蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等を目的として、蜜源植物の確保や植栽状況の実態把握等の取組への支援を行い、養蜂業の振興を図ることとします。
また、施設園芸における花粉交配用蜜蜂については、近年の自然災害等により需給が不安定な傾向にあり、園芸農家と養蜂家が連携した花粉交配用蜜蜂の安定調達の取組を支援することで、需給の安定を図ることとします。
さらに、花粉交配用昆虫として用いられるマルハナバチについては、セイヨウオオマルハナバチが特定外来生物に指定されていることから、在来種マルハナバチの利用拡大に必要な取組を支援し、セイヨウオオマルハナバチからの転換を図ることとします。
備品費、事業費、旅費、設備費、消耗品費、役務費、委託費、その他
1 蜂群配置調整適正化支援事業
事業実施主体は、蜂群配置調整の適正化等に向けた環境整備のため、次に掲げる取組を行うことができるものとします。ただし、(1)に掲げる取組は必ず行うものとします。
(1)検討会議の開催
各都道府県における蜂群の適正配置等を図るための蜜源植物の植裁・管理、実態把握等について、養蜂家(業として蜜蜂の飼育を行う者(都道府県単位の養蜂協会等の養蜂グループの代表者を含む。)をいう。以下同じ。)、都道府県、市町村、農林業者団体、学識経験者等による検討会議を開催する。
(2)蜜源植物の植栽・管理
新規・拡大地区での蜜源植物の植栽・管理(保護柵設置等)及び本事業を実施した既存地区での蜜源植物の管理を行う。
(3)蜜源植物の植栽状況等の実態把握
蜂群の位置情報や蜜源植物の植栽状況等、蜂群配置調整の適正化に資するデータ収集に向けた実態把握調査等を実施する。
(4)蜜源植物の保護・増殖推進のための普及啓発の取組
蜜源植物の保護・増殖推進に向け、養蜂の正しい知識や蜜蜂の農業生産への貢献等の普及啓発のためのパンフレットの作成等を行う。
(5)養蜂家と耕種農家の連携による蜜源植物の定着化
養蜂家と耕種農家が連携し、蜜源・緑肥作物として活用できるレンゲ等の定着化に向けた実証を行う。
2 花粉交配用蜜蜂の安定調達支援事業
花粉交配用蜜蜂の安定調達を図るため、次に掲げる取組を行うものとします。た
だし、(2)⑤のみ、及び(2)⑤と(3)のみに取り組む場合を除き、(1)に
掲げる取組は必ず行うものとします。
(1)協力プランの作成
園芸農家(園芸品目において農業を営む個人又は法人をいう。以下同じ。)や養蜂家等が参画して検討会を開催し、園芸農家と養蜂家が連携して花粉交配用蜜蜂の安定確保を図るための具体的な取組を記載した協力プラン(以下「協力プラン」という。)を作成する。作成に当たっては、園芸農家における花粉交配用蜜蜂の適切な管理の徹底に関する具体的な取組の記載を必須とする。また、必要に応じて情報収集のための先進地視察等を行う。
(2)花粉交配用蜜蜂の安定確保のための技術実証
協力プランに記載する①花粉交配用蜜蜂の効率的な増殖技術、②生物分解性プラスチック巣箱の利用、冬季の蜜蜂の消耗軽減等の蜜蜂の長寿命化に資する利用技術、③台風やダニ、スズメバチ等の被害防止のための技術、④園芸農家の適切な管理技術、⑤蜜蜂以外の花粉交配用昆虫を使った代替併用技術等の実証を行い、技術マニュアルの作成に必要なデータを収集する。
(3)マニュアルの作成、講習会の開催等
技術マニュアルの作成、園芸農家又は養蜂家向けの技術講習会の開催等、技術の普及のための取組を実施する。
3 在来種マルハナバチの利用拡大支援事業
事業実施主体は、在来種マルハナバチの利用拡大を図るため、次に掲げる取組を行うものとします。ただし、(1)及び(2)に掲げる取組は必ず行うものとします。
(1)検討会の開催
在来種マルハナバチの適切な利用方法、地域への定着や普及に向けた方策等を検討するための会議を開催する。
(2)利用技術の実証・展示
在来種マルハナバチの適切な利用技術の確立を図るため、利用技術の実証・展示ほ場を設置して、適切な利用方法等の検証等を行うとともに、利用技術マニュアルの作成に必要なデータを収集する。
(3)先進地視察、マニュアルの作成、講習会の開催等
情報収集のための先進地視察、利用技術マニュアルの作成、園芸農家向けの利用技術講習会の開催等、利用技術の普及のための取組を実施する。
2025/01/28
2025/02/26
応募主体は、協議会とし、以下の全ての要件を満たすものとします。
(1)協議会は、都道府県及び養蜂家に加え、市町村、植栽場所の提供者等の園芸農家、農業協同組合、試験研究機関等により構成されていること(都道府県及び養蜂家の参加は必須とする。)。
(2)事務手続を適正かつ効率的に行うため、協議会の代表者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした協議会の運営等に係る規約(以下「協議会規約」という。)が定められていること。
(3)協議会規約において、一つの手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。
(4)本事業の取組において、第3の1(2)に取り組む場合は、1本以上の樹木が植栽されること。
(5)養蜂家が法人にあっては、厚生年金保険及び健康保険に加入させること。
※本事業の活用を検討されている方は、地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局)に必ず相談してください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書類及び添付書類は、公募要領に従って提出先窓口に提出してください。
申請書類の提出は、原則として電子メール、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)とし、やむを得ない場合には持参も可とします。
なお、FAXによる提出は受け付けません。
農林水産省 住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表) 担当:農林水産省農産局
※本公募は、令和7年度政府予算案に基づくものであるため、成立後の予算の内容により、事業内容、予算額等に変更があり得ることをあらかじめ御了承の上、御応募ください。
また、本事業の活用を検討されている方は、地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局。以下同じ。)に必ず御相談ください。
—–
養蜂振興法(昭和 30 年法律第 180 号)の蜜源植物の保護増殖、蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等を目的として、蜜源植物の確保や植栽状況の実態把握等の取組への支援を行い、養蜂業の振興を図ることとします。
また、施設園芸における花粉交配用蜜蜂については、近年の自然災害等により需給が不安定な傾向にあり、園芸農家と養蜂家が連携した花粉交配用蜜蜂の安定調達の取組を支援することで、需給の安定を図ることとします。
さらに、花粉交配用昆虫として用いられるマルハナバチについては、セイヨウオオマルハナバチが特定外来生物に指定されていることから、在来種マルハナバチの利用拡大に必要な取組を支援し、セイヨウオオマルハナバチからの転換を図ることとします。



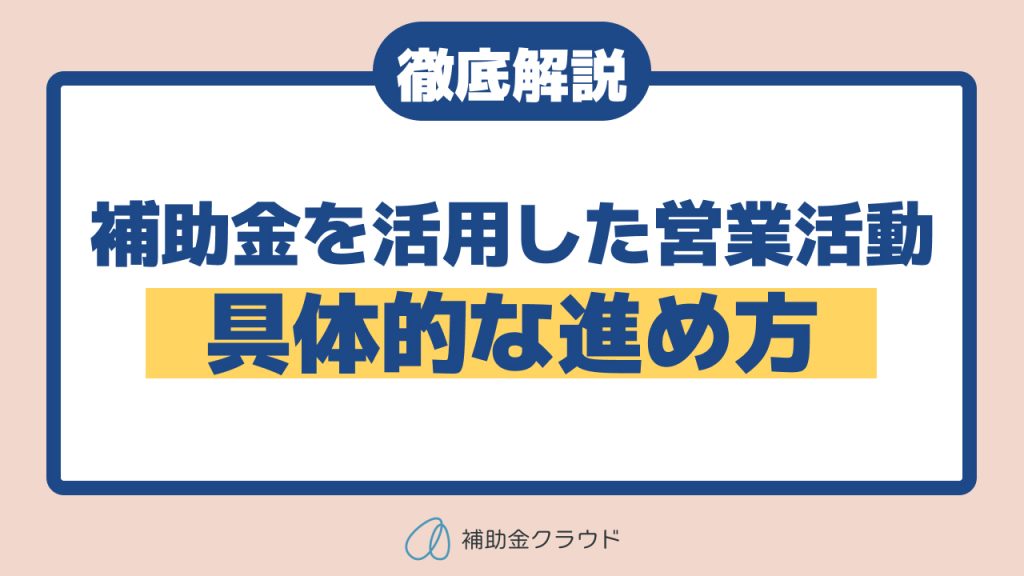
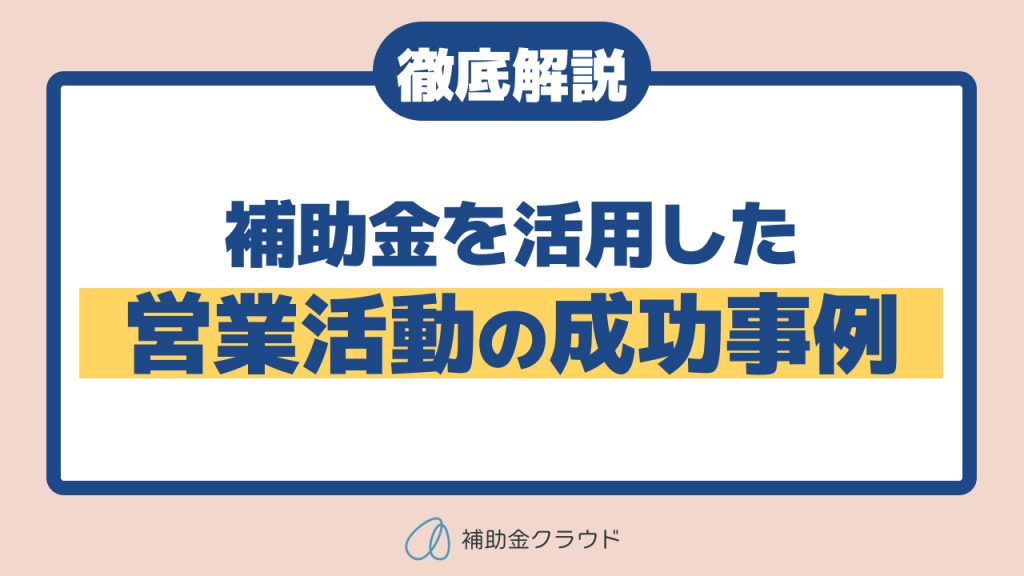
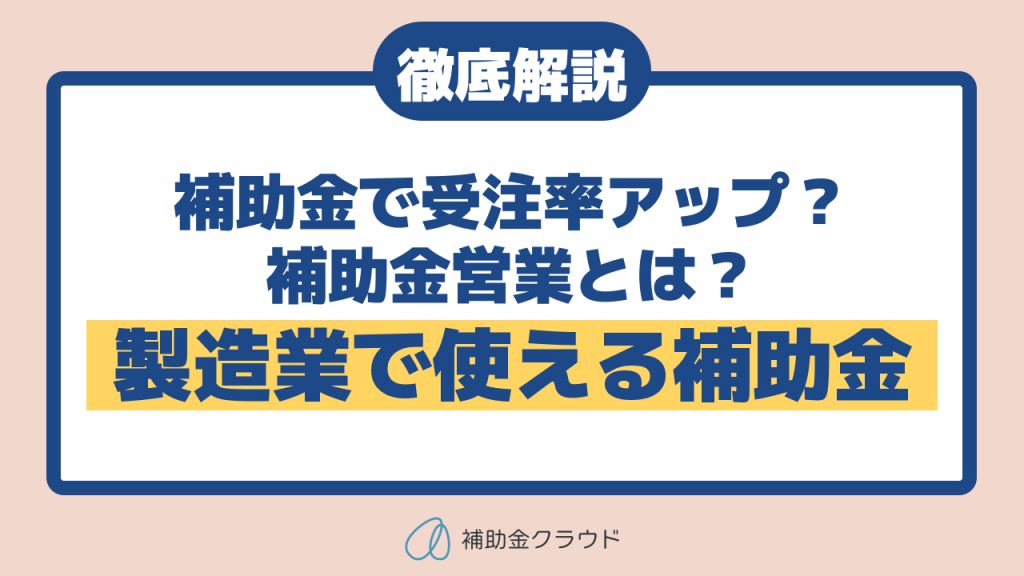
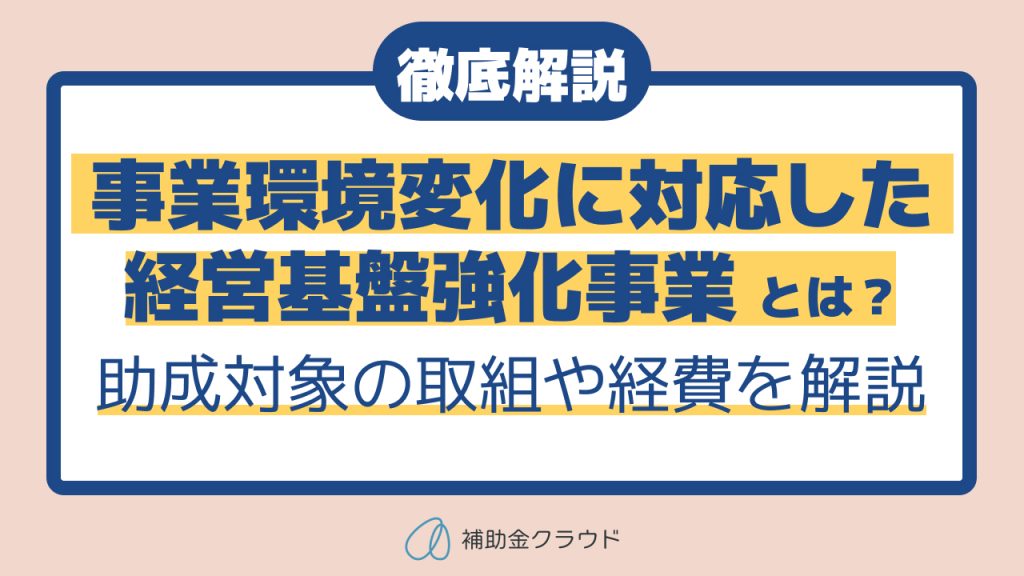
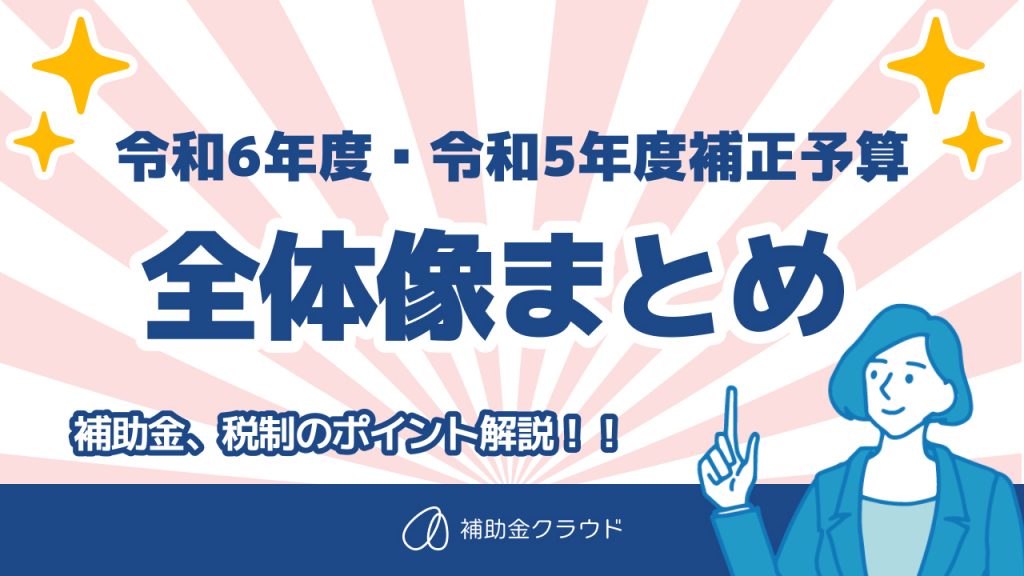
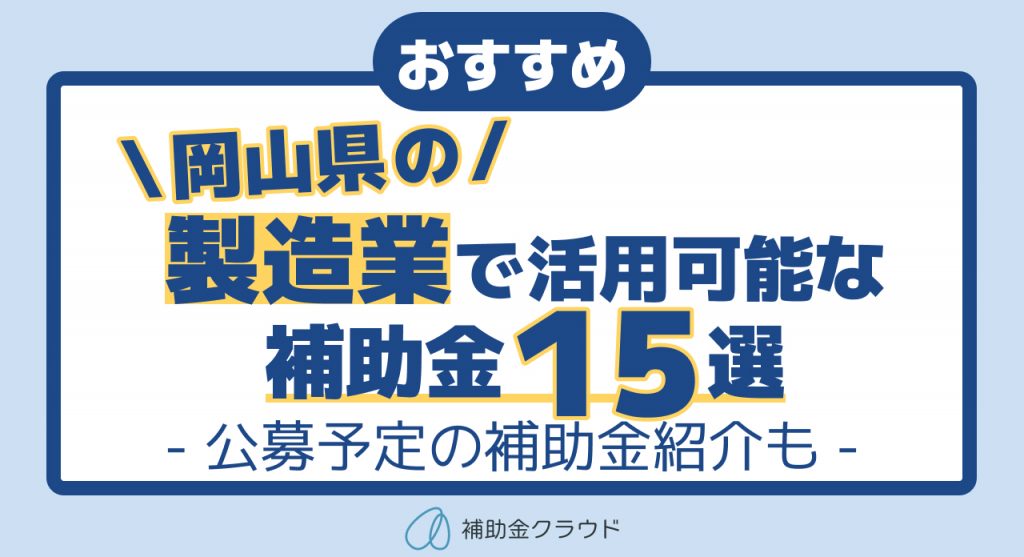


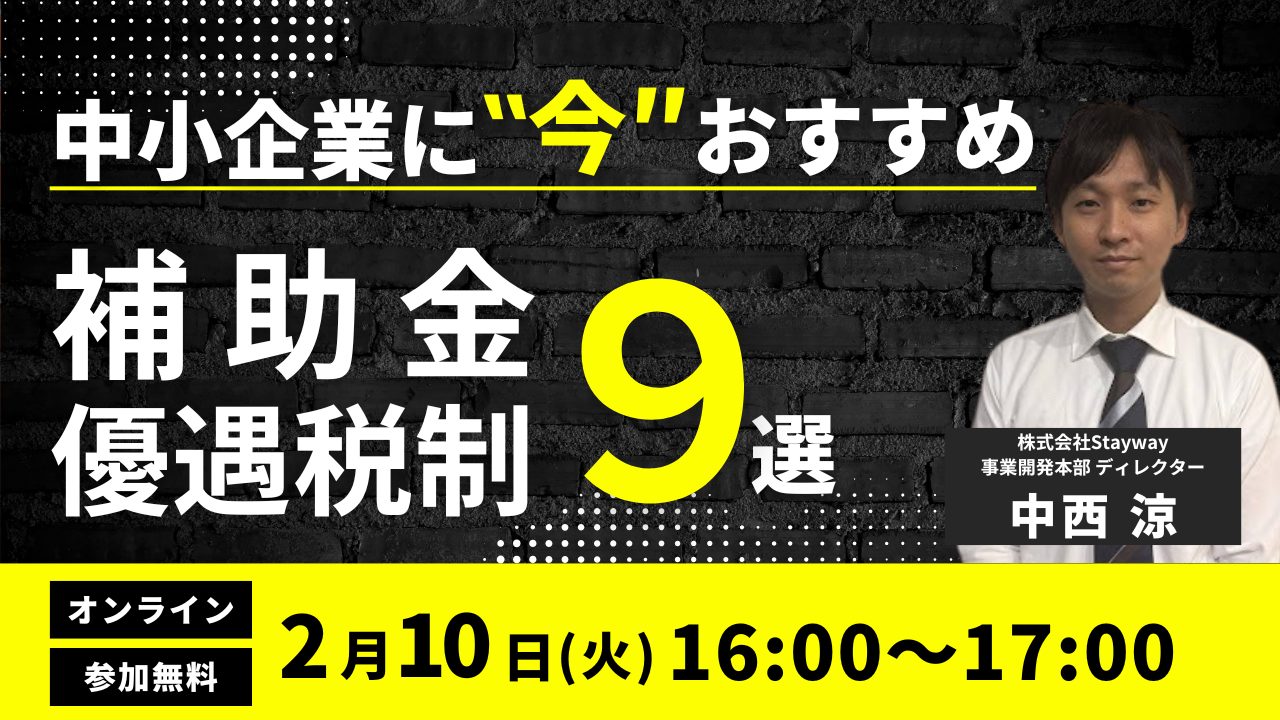


関連する補助金