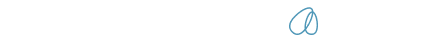中小企業のM&Aは、近年、事業を譲渡する側(売り手企業)にとって、事業承継問題を解決する重要な選択肢として注目を集めています。特に経営者の高齢化や労働人口の減少といった社会的背景が、売り手企業によるM&Aの活用を後押ししています。
また、事業承継に加え、財務改善や経営資源の有効活用など、企業が抱える様々な経営課題の解決手段としてM&Aが実施されており、その成功事例も増えています。
この記事では、主に売り手企業の視点から、中小企業M&Aの概要や背景などを、事例も交えて解説します。
中小企業M&Aの概要
中小企業のM&Aは、経営基盤を強化して持続可能な成長を目指すための手段のひとつとして近年注目されています。特に後継者不足や経営者の高齢化といった課題を抱える企業が、事業継承を目的にM&Aを選択するケースが増えてきているのです。
また、経済や市場環境の変化に対応するため、他社の経営資源を活用した成長戦略の一環としても有効です。そんなM&Aの成否は、両社の経営理念や事業方針の相性と適切な準備に左右されます。
まずは「中小企業」と「M&A」それぞれの定義についてご紹介します。
中小企業とは?
中小企業基本法によると、中小企業の定義は以下の通りです。資本金または従業員数のいずれかを満たせば中小企業とみなされます。
| 業種 | 中小企業者 | 小規模企業者 | |
|---|---|---|---|
| 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | 常時使用する従業員の数 | |
| ①製造業、建設業、運輸業 その他の業種(②〜④を除く) |
3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
| ②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| ③サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| ④小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
M&Aとは?
M&Aとは、「Mergers(合併)」と「Acquisitions(買収)」の略で、企業間の統合や経営権の移転を意味する言葉です。合併は複数の企業が一つに統合されること、買収はある企業が他の企業を買い取る行為を指します。
このM&Aによって、企業は事業規模の拡大や経営資源の活用を図れるでしょう。特に中小企業では、後継者問題や経営の効率化を背景にM&Aが積極的に行われています。
中小企業M&Aの増加について
中小企業のM&A(第三者承継)は近年増加傾向にあります。独立行政法人中小企業基盤整備機構の報告によれば、事業承継・引継ぎ支援センターがかかわった第三者承継の成約件数は、令和5年度に2,023件と過去最高を記録し、事業承継におけるM&Aの重要性が高まっている傾向がうかがえます。
平成23年度から令和5年度までの成約件数の推移は、下表のとおりです。
|
年度 |
成約件数(件) |
|
平成23年度 |
0 |
|
平成24年度 |
17 |
|
平成25年度 |
33 |
|
平成26年度 |
102 |
|
平成27年度 |
209 |
|
平成28年度 |
430 |
|
平成29年度 |
687 |
|
平成30年度 |
923 |
|
令和元年度 |
1,176 |
|
令和2年度 |
1,379 |
|
令和3年度 |
1,514 |
|
令和4年度 |
1,681 |
|
令和5年度 |
2,023 |
※以下参照先に掲載されている表をもとに、㈱Staywayにて再作成
中小企業M&Aが増加している背景
中小企業M&Aが増加している背景には、日本の社会的・経済的な課題が深く関係しており、特に経営者の高齢化や労働人口の減少などの問題がM&Aの増加につながっていると考えられています。
経営者の高齢化
日本の中小企業経営者の平均年齢は年々上昇しており、令和5年時点で約60歳に達しています。この傾向は今後も続くと予想され、多くの企業が早急に事業承継を検討する必要に迫られています。
しかし、後継者が不在の企業は全体の半数を超えるとされ、事業の存続が難しい企業も少なくありません。その結果、事業承継の選択肢としてM&Aを活用し、第三者への経営移譲を進める企業が増加しています。
労働人口の減少
日本では少子高齢化が進み、労働人口が減少しています。総務省の統計によれば、2023年の生産年齢人口(15歳〜64歳)は約7,400万人で、前の年より約26万人減少しています。
参照:総務省 人口推計 2023年(令和5年)10月1日現在
このような状況を背景に、多くの中小企業が人材確保の課題に直面していることから、必要な人材や技術を他企業から獲得する有効な手段のひとつとしてM&Aが注目されているのです。
中小企業M&Aの目的
中小企業のM&Aは、企業の成長や存続を図るための重要な手段として広く活用されています。ここでは、中小企業M&Aを行う4つの目的について解説します。
1. 事業承継
2. 成長戦略の実現
3. 経営効率化とコスト削減
4. 技術・ノウハウの獲得
事業承継
日本の中小企業では、前述のとおり経営者の高齢化に伴い後継者不足が深刻な問題です。
中小企業庁(経済産業省)の中小企業白書(2023年版)によれば、2022年の段階で57.2%の中小企業が後継者不在の状況に直面しています。
M&Aを活用した第三者への事業の譲渡により、事業の存続と発展が図れます。さらに、従業員の雇用維持や取引先との関係継続も期待できるでしょう。
参照:経済産業省 中小企業庁 2023年版「中小企業白書」 第1節 事業承継・M&A
成長戦略の実現
M&Aを活用すれば、企業は短期間で市場シェアの拡大を実現できます。既存の事業基盤や顧客ネットワークを持つ企業の買収によって、自社で一から事業を立ち上げるよりリスクを抑えつつ成長戦略を推進できます。
経営効率化とコスト削減
M&Aにより、重複する業務や部門を統合し、事業規模拡大による効果を活かせば、仕入れコストや物流費の削減が可能となります。例えば、同業他社との統合により、購買力が増し、原材料の大量購入による価格交渉力の向上が期待できるでしょう。
さらに、M&Aを通じて販売チャネルの共有や生産設備の最適化が実現し、業務プロセスの効率化が可能です。固定費の削減や生産性の向上が期待でき、全体的なコスト構造の改善につながります。
技術・ノウハウの獲得
M&Aは他社が持つ独自の技術やノウハウを、迅速に獲得する手段として有効です。特に研究開発に長い時間やコストを要する場合、企業間で既存の技術を吸収することにより、競争力の大幅な向上が図れます。
例として、新しい製品開発や製造プロセスの改善を目的とした専門技術を有する企業の買収が挙げられます。
財務改善と資金調達
M&Aは、事業や資産の一部の売却により、財務状況を改善する手段としても利用されています。具体的には、負債の削減や資金繰りの安定化を図ることができ、財務状況の改善を見込めます
また、新規事業の展開や大規模な設備投資に必要な資金を調達するためにもM&Aが活用されています。特に資金調達能力が限定される中小企業にとって、M&Aは事業の成長と安定を両立する手段といえるでしょう。
中小企業M&Aの方法
中小企業M&Aには、さまざまな方法があります。それぞれの方法には特徴があり、企業の状況や目的に応じた適切な選択が課題です。
ここでは、主要な方法として次の3つについて解説します。
1. 株式譲渡
2. 事業譲渡
3. 会社分割
株式譲渡
株式譲渡は、企業の株主が保有する株式を他者に売却し、経営権を移転する方法です。この方法では、会社の資産、負債、従業員、取引先との契約などの包括的な引き継ぎができます。
また、株式譲渡は売り手企業の事業や組織の一体性を保ちながら、円滑に経営権を移譲できる点が大きな特徴です。
ただし、買い手企業にとっては、売り手の負債やリスクも含めて引き継ぐので、慎重な検討が必要となります。
事業譲渡
事業譲渡は企業が特定の事業や資産、負債を別の企業に移転する手法です。この方法では、譲受企業が必要な事業だけに限定した承継ができます。
株式譲渡と比較して、柔軟性が高い点が特徴です。なお、譲渡手続きの実行には株主総会の承認が必要となります。
会社分割
会社分割は、企業が自社の一部を分割して新たな企業を設立したり、既存の他社に引き継がせたりする手法です。特定の事業の切り出しにより、経営資源の再編や効率化を図れます。
中小企業M&Aを成功させるためのポイント
中小企業M&Aを成功させるためには、主に次の4つのポイントがあります。各ポイントについて補足します。
1. M&Aの目的を明確化する
2. マッチングに強みを持つM&A仲介会社を選ぶ
3. 取引金融機関の理解と協力を得る
4. デューデリジェンスを徹底する
M&Aの目的を明確化する
新規市場への進出や事業規模の拡大、技術の獲得など、M&Aによって達成したい具体的なゴールの設定により、適切な戦略の立案ができます。
目的の明確化に伴い、M&Aを行う相手先の選定基準も明確化され、交渉や契約プロセスを効率的に進められるでしょう。
さらに、具体的なゴール設定によって、取引後の企業統合(PMI)も円滑に進みます。
マッチングに強みを持つM&A仲介会社を選ぶ
M&Aを成功させるには、適切な仲介会社の選定が重要です。仲介会社は豊富な企業情報を基に、買い手と売り手をマッチングします。
業界知識が豊富で幅広いネットワークを持つ仲介会社を選べば、自社にとって最適な相手先が見つかりやすくなるでしょう。
取引金融機関の理解と協力を得る
買い手企業がM&Aを実施する際、多くの場合、買収資金の調達が必要となります。そのため、金融機関との信頼関係を普段から構築しておくことが不可欠です。
金融機関は、買い手企業のM&A実施に際して資金調達支援だけでなく、財務面のアドバイスも提供します。また、金融庁も金融機関がM&A支援体制を強化しており、買い手企業と金融機関の連携がより重要になっています。
デューデリジェンスを徹底する
デューデリジェンス(適正評価手続あるいは買収監査)は、M&Aにおける重要なプロセスであり、対象企業の財務状況や法務リスクを精査する手続きです。
特に簿外債務や契約上の潜在リスクの調査で、取引後の不測の事態を防げます。
また、人事面での精査も重要です。組織構造や労働条件の課題の確認により、統合後のスムーズなマネジメントが可能となります。
中小企業M&Aの事例紹介
経済産業省が発表している資料をもとに、中小企業M&Aの成功事例を2つご紹介します。
債務超過であるにもかかわらず成立した事例
譲渡企業:卸売業のA社(売上高12億円、従業員30名、業歴50年)
譲受企業:同業のB社(売上高30億円)
A社は前代表の時代に約20億円の借入があり、大幅な債務超過に陥っていました。資金繰りが厳しく新規投資も困難な状況で、A社代表は弁護士に相談し、中小企業再生支援協議会の手続きを活用します。
また、弁護士の紹介でM&A専門業者に譲受先の探索を依頼しました。その結果、B社がA社の販路や地域での知名度を高く評価し、全事業を事業譲渡の形で譲り受けたのです。A社はM&Aにより、債務超過の解消と事業の継続を実現しました。
参照:経済産業省 中小M&Aの事例(18ページ)
後継者候補が承継を拒んだため中小M&Aに移行し成立した事例
譲渡企業:製造業のC社(売上高5億円、従業員50名、業歴60年)
譲受企業:同業のD社(売上高20億円)
C社代表は、当初、親族内承継を検討していましたが、後継者候補が承継を拒否したため、第三者への事業承継を考えるようになりました。そこで代表は事業承継・引継ぎ支援センターに相談します。
同センターから複数の譲受候補企業を紹介された中で、D社がC社の技術力と市場シェアを高く評価し、C社の全株式を取得して従業員の雇用も継続しました。C社の事業は引き続き発展し、D社も事業領域の拡大を実現したのです。
参照:経済産業省 中小M&Aの事例(19ページ)
まとめ
中小企業M&Aは、事業承継や成長戦略、経営効率化など、さまざまな目的で行われています。その成功のためには、目的を明確にし、適切な支援機関や仲介会社の活用が重要です。
また、債務超過や後継者不足といった困難な状況下でも、適切なプロセスを経てM&Aが成立した事例もあります。M&Aの適切な活用が、中小企業の持続可能な成長と経営課題の解決につながるでしょう。