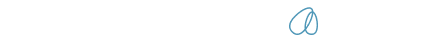中小企業のM&Aにおける売却価格は、単純な「定価」ではなく、買い手と売り手の個別条件から導かれる価格となります。これは、業種や財務内容だけでなく、将来性や交渉力も反映された結果です。
さらに、企業価値評価を土台にしつつ、最終的には当事者間の交渉で価格が調整されるため、同じような業態でも価格には大きな差が生じます。この記事では中小企業のM&Aにおいて、売却価格が決まる仕組みを解説します。
中小企業のM&Aに「決まった相場」は存在しない
中小企業のM&Aには、不動産のような画一的な相場が存在せず、企業ごとに評価額が大きく異なるのが実情です。売却価格は、各社が純資産や将来利益見込みなどを個別に評価した上で、独自に算定されています。
その結果、同業種でも条件や経営状況、業界トレンドによって価格レンジはさまざまであり、「相場」が特定できるものではありません。むしろ、個別評価の積み重ねが価格の決定要因となります。
売却価格は企業価値評価をベースとした「交渉」で決まる
企業価値評価(バリュエーション)は、コスト・インカム・マーケットの各アプローチを組み合わせて算定され、「時価純資産+将来利益予想(のれん)」といった基準が専門家により提示されます。
しかし最終価格はあくまで、買い手と売り手の交渉によって調整され、合意しなければ成立しません。すなわち、バリュエーションはあくまで交渉のスタート地点に過ぎず、価格そのものは交渉で決まるのです。
M&Aスキーム(株式譲渡か事業譲渡か)によっても価格は変動する
株式譲渡は企業全体を包括的に売却するスキームであり、資産・負債・契約・許認可などすべてが移転対象です。したがって、事業全部を対象とする分、一般的に売却価格は事業譲渡より高額になる傾向にあります。
一方、事業譲渡は特定の事業や資産を切り出して売る形式であり、範囲が限定されるため一般に売却価格は低く設定されがちです。また、株式譲渡に比べて法人税や手続き上の違いも影響し、価格差が生じます。
中小企業M&Aの売却価格の目安となる計算式
中小企業のM&Aでは、売却価格を算定するためにまず「時価純資産+営業権(のれん)」という基本的な計算式が使われます。このシンプルな式が、企業の現時点での価値と将来収益力を両立して評価する出発点になります。
基本の考え方:「時価純資産 + 営業権(のれん)」
売却価格の目安としてまず考慮すべきは、資産と負債を今の市場価値に見直した「時価純資産」です。これに「営業権(のれん)」を加えることで、企業が将来生み出す収益力を評価に含めることができます。
この合算式は、中小企業が持続的に利益を上げ続ける構造を反映しつつ、数値化しやすいため実務でも広く採用されています。ただし、将来利益の過度な期待を加えすぎると見積もりが膨らむリスクもあります。
「のれん」とは?
「のれん」とは、M&Aで支払う総額が時価純資産を上回る部分を指し、ブランド力や顧客基盤、技術力などの無形資産による超過収益力を表します。
日本の中小企業M&Aでは、こののれんを営業利益の数年分、一般的に2〜5年分として簡易的に見積もる年買法(年倍法)がよく使われています。
年買法では「営業利益×何年分」という形で数字が分かりやすく、シンプルなため交渉相手にも受け入れられやすいというのがメリットです。ただし、何年分をのれんとして評価するかは業界水準や交渉次第で左右され、理論的根拠が薄いという課題も存在します。
企業価値を詳細に算定する3つの専門的アプローチ
さらに精緻な評価を行いたい場合は、企業価値を算定するための代表的な3種の専門アプローチが適用されます。目的や状況に応じて複数の手法を組み合わせることで、評価の精度と妥当性を高めることが可能です。
① コストアプローチ:企業の純資産に着目する評価方法
コストアプローチは、貸借対照表に記載された資産と負債を時価に調整し、そこから純資産を求める方法です。資産評価に基づくため客観性に優れる一方、将来の収益力やブランドといった無形価値を反映しにくいという限界があります。
特に中小企業の場合、扱いやすく理解されやすい手法として多用され、簿価純資産法や時価純資産法、そしてこれらにのれんを加える手法(年買法)といった派生手法が使われます。ただし、業績や市場環境の変化を評価に含めにくい点には注意が必要です。
② マーケットアプローチ:類似企業や市場を参考にする評価方法
マーケットアプローチでは、類似業態の上場企業や実際のM&A事例(マルチプル法など)を参考にして相対的な企業価値を算出します。この手法は市場の評価が反映されやすく、客観的な比較ができる点がメリットです。
ただし、中小企業では類似の上場企業やM&A事例がそもそも少ないため、比較対象の不足によって評価が困難になるケースも多いです。また、市況に左右されやすいというデメリットも併存しています。
③ インカムアプローチ:将来の収益力に着目する評価方法
インカムアプローチは、将来予測されるフリーキャッシュフローを割引率で現在価値化するDCF法や収益還元法を用いて企業価値を算出します。この方法は成長性や将来収益力を直接評価できる理論的に精度の高い手法です。
しかし、中小企業では信頼性の高い事業計画や十分な財務資料を用意するのが難しく、予測に恣意が入りやすい点が課題となります。そのため、実務としてはコストアプローチやマーケットアプローチとの組み合わせが一般的です。
計算結果だけでは決まらない最終的な売却価格を左右する5つの重要要素
売却価格は単なる数式計算の結果ではなく、交渉過程で明らかになるさまざまな要因が反映されます。ここでは、特に価格に影響を与える5つの要素を見ていきましょう。
① 買い手にとってのシナジー効果
買い手が得られる販路や技術面での相乗効果が大きい場合、将来利益の増加が見込めるため、理論価値を超える価格を提示する傾向があります。特に販売チャネルの拡張やコスト削減による収益改善が明確であれば、高値成立の可能性が高まるでしょう。
実際、M&Aでコスト効率や売上増が期待できる場合、買い手は競合よりも高めの条件を提示しやすくなります。このため、売り手側は自社の強みとなるシナジーを交渉素材として明確に示すことが重要です。
② 技術力やブランドなどの「無形資産」の価値
特許やブランド、顧客関係などの無形資産は、財務諸表に現れにくいものの、収益力の源泉として高く評価されます。買い手がこれらを戦略的に活用できると判断すれば、その分譲渡価格は上昇しがちです。
日本企業では有形資産への依存が根強いものの、無形資産の見える化と開示が進む中、有用な特許やブランドが適正に評価される事例が増加しています。売り手がこれらを明確に提示できれば、価格交渉において有利に働く可能性があります。
③ 経営者の引継ぎや従業員の処遇
買収後も売り手企業の経営者が一定期間協力してくれる場合、買い手は企業統合のリスクを軽減でき、安心して高めの価格を支払う傾向があります。特に、キーパーソンとなる従業員が継続雇用される体制が整っていれば、統合後の事業継続がスムーズになるでしょう。
一方、引継ぎが不十分だと買い手側にとって文化摩擦や従業員の流出リスクが高まるため、価格交渉でも不利になります。したがって、明確な人材戦略と雇用維持の計画が交渉の評価材料となります。
④ 交渉の進め方(個別交渉かオークションか)
個別交渉では交渉相手が1社に限られるため、価格の上振れ余地が小さくなるのが一般的です。一方、オークション方式では複数の買い手候補が競い合う構図となり、結果的に価格が高騰しやすくなります。
特に中堅・中小企業ではオークション方式を採用することで、買い手の見積もり競争が起こり、売り手の有利な条件を引き出しやすくなります。また、候補を広く募ることで予想外の買い手を発掘できる点もメリットです。
⑤ M&Aのタイミングと業界動向
売却時に自社が業績好調であれば、買い手は自信をもって価格を提示しやすく、交渉も有利に進みます。また、特定業界で再編が活発な状況では、買い手企業が競争的に参入機会を探っており、有利な条件での売却が期待できます。
逆に、不景気や業界縮小期に売却を図ると、買い手の姿勢が慎重になり価格交渉は不利になるでしょう。そのため、タイミングと業界動向の観察は、戦略的に欠かせないポイントです。
まとめ
M&Aにおける最終的な売却価格は、数式による企業価値評価に加えてシナジー効果、無形資産評価、人的要素、交渉手法、タイミングといった複合的要因によって大きく左右されます。
売り手はこれらを理解し、戦略的に準備することで交渉を有利に進めることが可能です。各要素を整理し、買い手にとっての魅力を最大化して具体的に提示すれば、理論価格を超える高条件での成約が可能になります。
M&Aのご相談はこちら
M&A・事業承継のご相談ならBIG4出身のM&AアドバイザーのいるM&AHUBにご相談ください。最短翌営業日にご相談可能です。