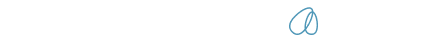事業売却(事業譲渡・カーブアウト等)は、不採算事業やノンコア事業を切り離し、主力事業に経営資源を再配分できる有力な選択肢です。売却で得た資金を負債圧縮や新規投資に充てることで、財務健全性と成長投資の両立も図れます。
さらに、後継者不在でも事業・雇用・技術を次世代へ承継でき、廃業による価値の毀損を避けることが可能です。一方で、手続きや人事・税務の論点は多岐にわたるため、制度の理解と計画的な準備が成功の鍵になります。
この記事では、事業売却の視点からM&Aのメリットとデメリットを見ていきましょう。
事業売却がもたらす5つの戦略的メリット
事業売却は「選択と集中」を加速し、売却対価で主力強化・負債返済・新規事業投資を同時に進められる戦略オプションです。会社全体を手放さずに一部のみを切り出せるため、残存事業の経営権と法人格を保ちながら再編できます。
主力事業への「選択と集中」による経営改革
不採算事業やノンコア事業を売却すれば、人材・資本といった経営資源を主力事業に再配分でき、全社の収益性と機動力を高めることにつながります。事業譲渡は、資産・負債・契約を個別に移す「特定承継」であるため、切り出す範囲の設計自由度が高く、狙い通りの事業再編が可能です。
その結果、買い手にとっても必要な部分だけを取得できるため、売り手は好条件を引き出しやすくなります。こうした「選択と集中」は、日本企業で増加しているカーブアウトの主目的としても位置づけられています。
創業者利益の確定と新規事業・負債返済への資金活用
事業売却で得たキャッシュは、借入金の圧縮や設備投資・研究開発・新規事業の立ち上げに再投資できます。株式の希薄化を伴わずに資金を確保できるため、財務戦略上の柔軟性が高まります。
大型企業の資産売却でも、再投資や財務体質の改善に充てる事例が相次いでいます。この「資金化→再配分」の循環が、成長投資とバランスシートの健全化を同時に進める原動力になります。
後継者不在問題の解決と事業・技術の承継
後継者がいなくても、第三者への承継(M&A)により事業・雇用・技術を次世代へつなぎ、廃業に伴う地域経済へのマイナスの影響を回避できます。中小企業庁も、事業承継やM&Aが企業の活力維持・発展に有効であると明示しています。
黒字でも後継者不在で廃業に至るリスクがあるため、早期に承継手段を検討する意義は大きいです。公的支援やガイドラインの整備も進み、適切な準備・相手選定・引継ぎが後押しされています。
会社法人格を維持し、残存事業の経営権を保持
事業譲渡は会社そのものではなく「事業」を移すため、売り手は法人格を維持し、経営権を手元に残せます。株式譲渡のように会社全体の支配権を手放すことなく、売却対象外の事業を引き続き自社で運営可能です。
この仕組みは、売却対価を残存事業の成長投資に充当しつつ、企業ブランドやガバナンスを保ったまま再編を進めることを可能にします。
従業員の雇用と取引先との関係を維持しながら再編可能
事業譲渡では、労働契約の承継に際して原則として従業員の個別同意が必要ですが、早期の丁寧な説明・協議により雇用の継続を図れます。一方、会社分割を用いる場合は労働契約承継法により契約が包括的に承継され、労働条件は原則的に維持されます。
いずれの手法でも、適切なプロセス管理と買い手選定により、従業員の生活と取引先との関係を守りながら再編を進めることが可能です。実務上の留意点(説明内容、協議の時期・方法)も厚生労働省の指針で整理されています。
事業売却で覚悟すべきデメリット
事業譲渡(アセットディール)は切り出しの自由度が高い一方、会社法上の決議や個別移転手続きが必要となり、株式譲渡(シェアディール)に比べて実務的な負担・期間・コストが増加する傾向にあります。
さらに、売却益への法人課税や資産ごとの消費税、競業避止義務、情報漏洩に伴う人材流出や取引先離反のリスクなど、意思決定前に理解しておくべき留意点が多岐にわたります。
手続きの煩雑さと長期化する可能性
事業譲渡では、移転する資産・負債・契約・許認可・人員を特定し、債権譲渡の対抗要件具備や取引先の個別同意など、一つひとつ個別に移転する手続きが必要になります。株式譲渡のように包括承継されないため、登記・契約更新・同意取得などが多岐にわたり、時間と費用を要します。
さらに、事業の全部または重要な一部の譲渡には株主総会の特別決議が必要で、社内のガバナンス手続きも並行して進める必要があります。結果として、スケジュール遅延や、クロージング後も残務が生じやすい点をデメリットとして認識すべきです。
売却益への課税と税務上の注意点
事業譲渡で得た売却対価は、譲渡資産の帳簿価額との差額が「譲渡益」として法人税の課税対象となります。加えて、資産の譲渡には原則として消費税が課税され(土地・有価証券等は非課税)、一括して価額が決められた場合は課税・非課税資産の時価で按分が必要です。
また、どの時点で売上として計上するか、といった会計・税務上のルールにも注意しなくてはなりません。株式譲渡とは課税主体・税目が異なるため、事前に繰越欠損金の活用や税制上の特例(圧縮記帳・買換え特例)の適用可否も検討すべきです。
「競業避止義務」による売却後の事業活動制限
会社法上、事業譲渡を行った売り手には競業避止義務が課され、同一市区町村および隣接市区町村で同種の事業を行うことが一定期間制限されます。期間は原則20年ですが、当事者の特約で最長30年まで延長可能です。これは買い手の事業価値を保護する観点から、実務上も契約書に盛り込まれるのが一般的です。
違反した場合は差止請求や損害賠償の対象となり得るため、地理的範囲・対象事業・期間を契約書で明確に定めておくことが不可欠です。
キーパーソン流出や従業員の動揺といった組織的リスク
M&Aに関する情報が不用意に漏れると、主要取引先の離反や従業員の退職を招き、M&A交渉そのものが頓挫するリスクがあります。情報管理は「最終契約締結後からクロージング後の適切なタイミングで開示する」ことを基本とし、守秘義務の徹底と関係者への段階的な説明が重要です。
トップ面談や現地視察の時期・方法も、信用不安や漏洩リスクを踏まえて、事前に買い手と合意の上で進めます。人材や顧客の維持を前提としたコミュニケーション計画とPMI(統合プロセス)の準備が、組織の不安を最小化することに直結します。
事業売却の7ステップ
事業売却(事業譲渡・カーブアウト等)の実務は、基本合意→デューデリジェンス→最終契約→クロージングという標準フローに沿って進みます。中小M&Aガイドラインや公的ハンドブックに準拠して進めることで、手戻りやリスクを抑えた実行が可能になります。
ステップ1:売却事業の選定とM&A戦略の策定
どの事業を、何の目的(選択と集中/資金調達/後継者対策等)で売却するかを社内で明確化し、意思決定体制とスケジュールを定めます。重要事業の譲渡には特別決議が必要となる場合があるため、株主構成や社内ガバナンスも同時に点検します。
想定されるスキーム(事業譲渡・会社分割等)ごとの税務・法務論点を洗い出し、事前に整理・集約を進めます。
ステップ2:専門家(M&A仲介会社)の選定と準備資料の作成
信頼できるアドバイザーを選定し、ティーザー(匿名概要書)からIM(企業概要書)への開示プロセスを設計します。財務資料・契約一覧・人事・許認可・知的財産などの関連資料を整理し、データルームを準備して質疑応答(Q&A)に備えます。
中小企業では帳簿や規程が未整備なことも多いため、早期から整備を進め、開示情報の質を高めることが重要です。
ステップ3:買い手候補の探索(ロングリスト・ショートリスト)と打診
アドバイザーのネットワーク等を活用し、戦略的な適合性・資金力・PMI能力等の観点で買い手候補のリスト(ロングリスト)を作成します。ティーザーに関心を示した相手と秘密保持契約(NDA)を締結し、IMを段階的に開示しながら理解を深めてもらいます。
候補を絞り込み(ショートリスト)、初期条件のすり合わせやトップ面談の準備を進めていきます。
ステップ4:トップ面談と基本合意書の締結
経営者同士がビジョン・企業文化・人材方針などを確認し、価格レンジ・スケジュール・独占交渉権といった主要条件を擦り合わせます。その上で、法的拘束力は限定的ながら、取引の大枠を定める基本合意書(LOI/MOU)を締結します。
基本合意には独占交渉権や重要事項の遵守義務などが盛り込まれるのが一般的です。
ステップ5:デューデリジェンス(買収監査)の受け入れ
買い手は財務・税務・法務・ビジネス・人事・ITなど多角的なデューデリジェンス(DD)を実施し、買収対象の価値とリスクを精査します。売り手は誠実に協力し、指摘事項への対応や、表明保証の設計に反映させていきます。
情報管理に留意しつつ、プロセス全体の透明性を確保することが求められます。
ステップ6:最終条件交渉と事業譲渡契約書の締結
DDの結果を踏まえ、最終的な譲渡価格・価格調整条項・表明保証・前提条件などを交渉し、最終契約書に盛り込みます。法的効力のある事業譲渡契約(最終契約)を締結し、必要に応じて価格調整やアーンアウトといった仕組みも設計します。
ステップ7:資産・負債・契約等の移転手続きとクロージング
最終契約に基づき、資産・従業員・契約・許認可等を個別に移転し、対価の授受をもってクロージング(取引の完了)を迎えます。不動産が含まれる場合は、登記手続きも速やかに行います。
クロージングの前提条件が全て満たされていることを確認し、PMIへ円滑に移行できるよう準備します。
売り手が陥りがちな注意点と成功のポイント
事業売却は価格や契約条件だけでなく、その後の事業承継や統合の成否にも直結する総合的なプロジェクトです。失敗事例では、情報開示や準備不足、相手先選定の甘さが破談や統合不全の原因となるケースが目立ちます。
【注意点】情報隠蔽、準備不足、価格への固執が招く破談
買い手はデューデリジェンスでリスクを徹底的に調査するため、不利な情報を隠すと信頼を損ない、交渉の中止につながります。財務や契約関係の整理不足も、調査段階での指摘増加につながり、条件悪化や破談の要因となり得ます。
さらに、市場相場を無視して高値に固執すれば、買い手候補が離れてしまいます。透明性のある情報開示と現実的な価格設定が成功の前提です。
【成功の秘訣】M&Aを「目的」ではなく「次への手段」と捉える戦略的視点
M&Aそのものをゴールにしてしまうと、売却後の事業戦略や経営者自身のキャリアプランが不十分になりがちです。売却は、会社や経営者が次のステージに進むための「手段」として捉える必要があります。
自社の将来的な成長戦略や社会的使命を見据えた上で、最適な相手やタイミングを判断するという長期的な視点が、価格以上の価値を生み出します。
【成功の秘訣】PMI(統合プロセス)まで見据えた買い手選びと円満な引継ぎ
契約締結後のPMIが成功するかは、事前の相手選びと引継ぎへの姿勢に大きく依存します。企業文化や経営方針の相性が良ければ、従業員や顧客もスムーズな統合が期待できます。
売却後も誠実に引継ぎに協力することで、買い手との信頼関係を維持でき、結果として、事業価値の維持・向上につながります。
まとめ
事業売却は、メリットとデメリットを正しく理解し、タイミングと準備を整えることで、成功の確率を大きく高めることができます。自社の内部要因と市場などの外部要因の両面を見極めた戦略的な判断が求められます。
価格や条件だけでなく、売却後の事業承継・統合の成否も視野に入れることが重要です。最終的には、経営者と会社の未来を描いたうえでの意思決定が、より良い成果へとつながるでしょう。