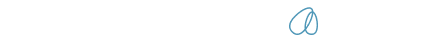会社を売却すると、多額の譲渡所得が発生し、それに対して所得税・住民税などの課税が生じます。特に、個人株主の場合の税率や計算方法を正しく理解しないと、想定以上の税負担に悩まされることもあります。
譲渡所得の仕組みと利用可能な節税策をしっかり把握することが、手取り額の最大化と安心したM&Aの実現に繋がります。この記事では、会社を売却する場合の税金や譲渡所得、節税の基本を解説します。
会社売却の税金を理解する第一歩|課税対象は「譲渡所得」
会社売却による利益は「譲渡所得」として課税対象となり、その金額の把握が最初のステップです。譲渡所得が正確に理解できていれば、税額の予測や節税対策も具体的に立てやすくなるでしょう。
会社売却の利益「譲渡所得」とは?
会社(株式)を売却して得た利益は「譲渡所得」と呼ばれ、譲渡価額から取得費や譲渡費用を差し引いた金額です。この譲渡所得に対して税金が課されます。個人株主が得た利益には「申告分離課税」が適用され、給与所得などとは合算せずに所得額にかかわらず税率が一律になります。
法人株主とは扱いが異なり、個人では概算取得費の特例も利用可能です。税率は合計で約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)となります。
譲渡所得の計算式:売却価格-(取得費+譲渡費用)
譲渡所得は、譲渡価額(株式の売却金額)から、「取得費」と「譲渡費用」を差し引いて計算されます。取得費には株式取得時に支払った払込金や名義書換料などが含まれ、譲渡費用にはM&A仲介の成功報酬やアドバイザリー手数料が該当します。
申告時にはこれらの金額を正確に把握しておくことが重要です。
取得費が不明な場合の対処法:「概算取得費の特例」
創業から時間が経っているなどの理由で株式の取得費が不明な場合、または実際の取得費が譲渡価額の5%を下回る場合には、譲渡価額の5%を取得費として計算できる「概算取得費の特例」を選択できます。譲渡所得が圧縮計算され、結果的に納税額を抑えられる可能性があります。
非上場株式でも広く認められており、特にオーナー社長が創業時から保有してきた株式に有効です。ただし、特定口座内での上場株式では適用不可とされるケースもあるため注意が必要です。
株式譲渡による会社売却の税金(個人株主の場合)
中小企業のM&Aで最も一般的な「株式譲渡」は、売却する株主が個人の場合、譲渡所得に対して一定の税率が課されます。申告分離課税により他の所得と合算せず、税率が一律である点が特徴です。
実際の税率や制度は国税庁のWebサイト等で最新情報を確認するか、税理士などの専門家に相談する必要があります。
株主個人にかかる税金の種類と税率:合計20.315%の内訳
個人株主が株式譲渡で得た譲渡所得には、所得税15.315%(復興特別所得税0.315%含む)と住民税5%が課されます。合計すると税率は20.315%となり、これは申告分離課税として他の所得とは合算されない一律課税です。
したがって、所得額にかかわらず同じ税率が適用され、計算がシンプルになります。(注:2025年8月現在、株式譲渡所得の税率は所得額にかかわらず一律です。将来的な税制改正で変更される可能性はあります。)
申告と納税の時期:確定申告はいつまで?
株式譲渡による譲渡所得については、売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告が必要です。所得税の納付は3月15日までに行い、その後、住民税はお住まいの自治体から6月頃に納税通知書が届くのが通常です。
確定申告・納税の準備を早めに行うことで、納税資金の不足やスケジュールの混乱を避けられます。納税資金を事前に確保することが重要です。
【比較】事業譲渡による会社売却の税金
事業譲渡では、株式譲渡とは異なり、売却の主体が会社(法人)となり、法人が保有する資産を売却する形式であるため、税務の扱いも大きく変わります。課税主体や税率・課税方式が異なるため、自社の状況に応じて適切な形式を選ぶ必要があります。
会社(法人)にかかる税金の種類
事業譲渡においては、売却益に対して法人税・法人事業税・法人住民税などを含む法人税等実効税率(約30~34%)が課されます。さらに、譲渡対象が課税資産(建物、機械設備、ソフトウェア、営業権(のれん)など)である場合には、それらの売却代金に対して10%の消費税も課税されます。
土地や有価証券などの非課税資産が含まれる場合には、消費税はかかりません。
事業譲渡における税額計算の仕組み
事業譲渡では、譲渡益が法人の他の損益と通算される「総合課税」が適用されます。売却益と本業の利益や損失を合算した法人全体の所得上で、実効税率を乗じて課税されるのです。
そのため、法人に繰越欠損金などがあれば、税額が調整される一方、売却益が大きい場合には高額な法人税が発生します。年度を通じた全体利益の把握が不可欠です。
注意点:売却代金を経営者個人が受け取る際の「二重課税」リスク
事業譲渡によって法人が売却利益を得た後、経営者がその資金を役員報酬や配当・退職金などを介して個人に移転させると、個人所得にも再度所得税が課されます。
つまり、【1】法人段階での法人税課税、【2】個人への資金移転段階での所得税課税という「二重課税」のリスクが発生します。資金の移転方法に応じて税負担が変わるため、戦略的な税務プランニングが重要となります。
株式譲渡or事業譲渡どちらが有利?税金面から比較
税負担や最終的な手取り額を最大化する観点から、株式譲渡と事業譲渡には明確な違いがあります。各手法の特徴を把握して、自社に最適な選択をすることが重要です。
|
比較項目 |
株式譲渡(個人株主の場合) |
事業譲渡 |
|
売却の主体 |
株主(個人) |
会社(法人) |
|
課税対象者 |
株主(個人) |
会社(法人) |
|
課税される利益 |
譲渡所得(売却価格 – 取得費 – 譲渡費用) |
譲渡益(譲渡資産の時価 – 簿価) |
|
適用される税金 |
所得税・住民税 |
法人税等、消費税 |
|
税率(目安) |
約20.315%(申告分離課税) |
約30~34%(総合課税)<br>+個人への資金移転時に所得税 |
|
二重課税リスク |
なし |
あり(法人課税 → 個人課税) |
|
手続き |
比較的簡便(包括承継) |
煩雑(個別承継) |
|
買い手のメリット |
限定的 |
のれんの損金算入による節税効果 |
税率の比較:個人株主の株式譲渡が有利な理由
株式譲渡による譲渡所得に対する税率は、所得税・復興特別所得税・住民税を合算して約20.315%となります。事業譲渡の場合、法人税等による課税(実効税率30%前後)と、さらに個人への資金移転時にかかる所得税があり、いわゆる二重課税構造となります。
したがって、個人株主が最終的に受け取る手取り額を最大化するには、一般的に株式譲渡の方が税務上有利です。金額が大きくなるほど、株式譲渡の税負担の軽さが際立ちます。
手続きの比較:包括承継と特定承継の違い
株式譲渡は会社そのものを移転する「包括承継」にあたり、契約や許認可、雇用関係なども原則としてそのまま承継されます。そのため、手続きが比較的簡略であるというがメリットです。
一方、事業譲渡は個別の資産・契約を選んで引き継ぐ「特定承継」であり、従業員の再雇用手続きや、取引先との契約書を新たに締結するなど煩雑な手続きを伴います。結果として、事務コスト・時間・労力が株式譲渡よりも大きくなる傾向があります。
買い手側(譲受側)のメリットの違い:税務とリスク管理の観点から
買い手にとって、どのスキームで会社を買収するかは、税務上のメリットだけでなく、将来的なリスクをどう管理するかという点でも重要です。特に事業譲渡は、株式譲渡にはない独自のメリットを持っています。
事業譲渡における買い手のメリット
- 1. のれんの損金算入による節税効果
事業譲渡では、買収価格が譲り受けた資産の時価を上回る部分が「のれん」として資産計上され、税務上5年間で均等に償却できます。その償却費を損金として計上することで法人税を圧縮できるため、買い手にとっては直接的な節税効果が期待できます。
2. 潜在的リスクの遮断
事業譲渡は、必要な資産・負債を個別に選択して引き継ぐ「特定承継」です。そのため、売り手企業が抱える可能性のある簿外債務や未払税金、訴訟リスクといった潜在的なリスク(偶発債務)を引き継ぐ心配がありません。買い手は、買収対象の事業に関連する健全な資産だけを選んで取得できるため、リスクを限定したクリーンなスタートが可能です。
株式譲渡のデメリットと事業譲渡の優位性
一方、株式譲渡は会社を丸ごと引き継ぐ「包括承継」であるため、買い手は売り手企業の権利義務のすべてを承継します。これには、帳簿上には見えない潜在的なリスクも含まれます。
この「潜在的リスクを引き継いでしまう」という点が、株式譲渡における買い手側の最大のデメリットです。デューデリジェンス(買収監査)でリスクを洗い出しますが、すべてを発見できるとは限りません。
この観点から見ると、事業譲渡は「株式譲渡のデメリットを回避できる」という点で、買い手にとって非常に有利な手法と言えます。これらの税務・リスク面のメリットは、M&Aの交渉において、買い手が事業譲渡を希望する動機となり、売却価格や条件にも影響を与える重要なポイントです。
会社売却で使える節税対策
会社売却においては、税負担を軽減できるスキームを事前に検討することが重要です。各手法にはメリットと注意点があるため、専門家と相談しながら計画的に進める必要があります。
役員退職金を活用して税負担を軽減する
M&Aの際、譲渡対価の一部を役員退職金として受け取ることで、譲渡所得よりも税率の低い退職所得として課税され、税負担を抑えられます。退職金は「功績倍率方式」などに基づいて適正額を設定する必要があり、高額過ぎると税務上否認されるリスクがあります。
法人側では株式譲渡の年に退職金を支給すれば、会社の利益と退職金を損益相殺でき、法人税の所得圧縮にもつながるでしょう。結果的に、経営者の手取り額が最大化される効果があります。
会社分割で不要な資産を切り離す
売却対象から不要な資産(例えば経営者の親族が住む社宅、事業と関係のない不動産、不要設備など)を会社分割で切り離すことで、譲渡対象の企業価値をスリム化し、その分譲渡価格を下げて税負担を軽減することができます。
会社分割を適切に活用すれば、買収側に必要な資産だけを引き継ぎ、効率的なスキーム構築が可能です。税務上の適格組織再編の要件を満たせば、資産の移転に伴う譲渡益の課税を繰り延べる効果も期待できます。
第三者割当増資で経営権を移転する
株式譲渡ではなく、第三者割当増資により新株を発行して経営権を移転すると、オーナー経営者は株式を売却しないため、譲渡所得が発生しません。ただし、この方法はオーナー個人の手元に売却代金が入るわけではなく、増資の引受代金は会社の資本となる点に注意が必要です。会社の成長資金を確保しつつ、経営権を移譲する手法と言えます。
増資による既存株主の持ち株比率希薄化や、新株発行時の条件設定には慎重さが求められます。
事業譲渡の利益を他の経費と相殺する
事業売却益は本業の損益と合算されて課税対象となるため、他の損失や経費で売却益を相殺することで課税所得を圧縮できます。例えば、特別損失の計上、設備投資による経費増加などが有効です。
ただし、損益相殺にはタイミングや制度要件があり、無理な節税はかえって逆効果となる可能性があります。
まとめ
会社売却時の節税対策としては、役員退職金の活用、会社分割、第三者割当増資、事業譲渡における損益相殺の4つが代表的です。
各手法には制度上の条件とリスクがあるため、M&Aのスキームや企業状況に応じて最適な組み合わせを検討することが重要です。計画的な節税施策と専門家の助言があれば、売却後の手取り最大化につながります。