資金調達には「返済義務の有無」「スピード」「経営権への影響」など、多様な要素が絡みます。近年ではクラウドファンディングやアセットファイナンスなど、新たな手法も急成長中です。
自社のフェーズや資金ニーズに応じた最適な選択が、事業の成否を分けます。この記事では、最新の制度や活用ポイントを整理してご紹介します。
資金調達の主要な5つの分類
資金調達は大きく5つのカテゴリーに分類され、目的やリスク構造、導入ハードルが異なります。まずはそれぞれの特徴を簡潔に把握し、自社に合った手段を選ぶ視点を養いましょう。
負債を増やす「デットファイナンス」(融資)
金融機関から借り入れる方法で、元本と利息の返済義務がありますが、経営権は維持できます。利息は損金扱いとなるため節税効果が期待でき、信用力も高められます。
公的融資・制度融資・ビジネスローン・社債など選択肢が幅広く、自社状況に応じて柔軟に使い分けられます。一方、返済が滞ると信用情報に影響が出たり、キャッシュフローが圧迫されるリスクもあります。
資本を増やす「エクイティファイナンス」(出資)
株式を発行し、投資家から資金を調達する方法で、返済義務はありません。資本比率が高まり財務体質が強化されやすく、赤字や実績不足企業でも調達が可能です。
また、VCなどからは経営ノウハウやネットワークの提供による支援が得られるケースがあります。ただし株式を発行することで経営権が希薄化し、株主による経営介入の可能性もあります。
資産を現金化する「アセットファイナンス」
売掛債権や不動産などを担保にして現金化する手法で、借入ではない即時の資金調達が可能です。具体的にはファクタリングやリースバックを利用し、キャッシュフローを迅速に改善できます。
借入負債が増えず、資本構成を崩さない点もメリットですが、資産を手放すコストや契約条件には注意が必要です。将来的な資産活用や売却の柔軟性に影響を与え得るため、戦略的な検討が求められます。
返済不要の「補助金・助成金」
国や自治体が政策目的で給付する返済不要の資金で、特に中小・創業期企業に有効です。ただし原則後払いであるため、先行して資金を支出できる体力が必要で、申請の手間や審査を伴います。
販路開拓、設備投資、IT化といった事業成長を目的とする「補助金」と、雇用の安定や人材育成を目的とする「助成金」に大別されます。事業計画や使途要件に合致していなければ採択されないため、緻密な書類整備と戦略が重要です。
共感を資金に変える「クラウドファンディング」
インターネット経由で不特定多数から資金を集める方法で、返済義務は基本的にありません。支援者にリターン(製品・体験・サービス)を提供しつつ、初期マーケティングやファン獲得の効果も期待できます。
プラットフォーム手数料が発生し、配信や広報のための工数と準備が必要です。成功すればブランド認知を高め、事業検証にもつながるため、早期段階での活用価値が高い手法です。
【比較】主要な資金調達方法10選のメリット・デメリット
資金調達方法を多様な切り口から比較することで、自社の状況に最適な手段を選びやすくなります。金利や条件、導入のしやすさなどの観点で特徴を整理しました。
短期・長期、返済義務の有無、経営関与の影響なども含め、包括的に比較します。ここでは代表的な10の手法を見やすく解説します。
|
分類 |
調達方法 |
調達可能額 |
スピード |
コスト |
返済義務 |
経営への影響 |
審査難易度 |
|
融資 |
日本政策金融公庫 |
中〜高 |
中 |
低 |
あり |
なし |
低 |
|
制度融資・銀行融資 |
中〜高 |
中 |
低〜中 |
あり |
なし |
中〜高 |
|
|
ビジネスローン |
低〜中 |
高 |
高 |
あり |
なし |
低 |
|
|
出資 |
VC・エンジェル投資家 |
高 |
低 |
株式譲渡 |
なし |
あり |
高 |
|
資産 |
ファクタリング |
低〜中 |
高 |
中〜高 |
なし |
なし |
低 |
|
資産売却・リースバック |
中〜高 |
中 |
中 |
なし |
なし |
低 |
|
|
補助金・助成金 |
補助金・助成金 |
低~高 |
低(後払) |
手間 |
なし |
なし |
低~高 |
|
CF |
購入型クラウドファンディング |
低〜中 |
中 |
中 |
なし |
なし |
中(魅力次第) |
【融資】日本政策金融公庫(JFC)
創業者やスタートアップに対して無担保・無保証人の融資制度を提供しています。政府系金融機関ならではの低金利で、最大7,200万円までの融資枠が利用可能です。
創業後の達成目標に応じてさらに金利が0.2%引き下がる制度も導入されており、有利な条件設定が可能です。民間銀行よりも相談しやすく、創業期の最初の資金調達手段として最適です。
【融資】制度融資・銀行融資
信用保証協会が保証する「保証付き融資」と、銀行が自社リスクで貸す「プロパー融資」があります。保証付きは審査が比較的緩く、保証料がかかる一方、プロパー融資は保証料不要で限度額の縛りもありません。
ただしプロパーの場合は銀行との取引実績と決算内容が審査のカギとなり、審査難易度は高いです。まずは保証付き融資で実績を積み、将来的にプロパー融資へ移行する流れが望ましいとされています。
【融資】ビジネスローン|スピード重視の短期的な資金確保
ノンバンク系のビジネスローンは審査・手続きが速く、最短即日振込が可能です。一方で金利は高く、通常融資に比して15〜18%と高めの水準で設定されることが多いです。
緊急性の高い資金ニーズには有効ですが、利息負担が大きく長期利用には不向きです。あくまで短期的・一時的な資金調達として位置付け、使い分けが重要です。
【出資】ベンチャーキャピタル(VC)・エンジェル投資家
IPOやM&Aを見据えるスタートアップにとって有力な資金調達手段です。返済不要で数千万円〜数十億円規模の資金を一度にもらえる可能性があります。
VCからは資金だけでなく、経営支援・ネットワーク提供・人材支援などの価値も得られます。ただし株式希薄化が進み、VCの経営関与やExit戦略への対応が必要になります。
【資産】ファクタリング|売掛金を即日現金化
売掛債権をファクタリング会社に売却して現金化する仕組みです。赤字決算・税金滞納でも、売掛先の信用力が評価されれば利用可能で、金融機関融資より通りやすい特性があります。
審査や契約条件が簡素で、即日資金化が可能なサービスも増加しており、10分〜当日中に入金されるケースもあります。ただし売掛金の買取手数料がかかるため、コスト面では注意が必要です。
【資産】資産売却・リースバック
使用しない不動産や機器を売却しつつ、そのまま継続的に利用するリースバックが有効な手段です。資産を現金に変えながら事業場や設備をそのまま使えるメリットがあります。
事業所など固定資産を保有したまま資金調達でき、キャッシュフロー改善にも寄与します。
ただし売却に伴う譲渡契約の条件や将来の賃貸費用負担など、ライフプランに与える影響を検討する必要があります。
【補助金・助成金】事業投資や雇用を支援する返済不要資金
国や地方自治体が、政策上の目的(事業拡大、生産性向上、DX推進、雇用促進など)を達成するために、事業者の取り組みを支援する返済不要の資金です。
販路開拓の広告費、新たな設備投資、ITツールの導入費用などを支援する「補助金」と、従業員の雇用維持や人材育成にかかる費用を支援する「助成金」が主なものです。
返済不要という大きなメリットがある一方、原則として事業実施後の後払いであるため、一時的な立て替え資金(つなぎ資金)が必要になる点には注意が必要です。また、公募期間内に事業計画書などを準備して申請する必要があり、手間と時間がかかりますが、要件に合致すれば非常に有力な資金調達手段となります。制度は頻繁に新設・変更されるため、自社の事業計画に合うものがないか、定期的に情報を確認することが重要です。
【CF】購入型クラウドファンディング
支援者が製品やサービスを購入する形で資金提供される形式で、最も一般的なクラウドファンディングです。資金調達だけでなく、市場ニーズの確認やテストマーケティングとしての効果もあります。
リターン準備や広報が必要で、プラットフォーム手数料がかかるため、準備コストを考慮する必要があります。成功すれば、資金以外にもファン獲得やブランド認知といった副次的な効果が得られる点が魅力です。
自社に最適な方法は?4つの軸で選ぶ資金調達の「見極め方」
資金調達を考える際には、「金額」「スピード」「事業経験」「コスト・手間」の4つの軸で選ぶことが重要です。これらの観点から最適な方法を見極め、効率的かつ戦略的な調達を実現しましょう。
必要な「金額」で選ぶ
必要な資金額の規模が小さい場合は、補助金やクラウドファンディングで手軽に調達できるケースが多いです。逆に数百万円以上、大きな投資が必要な場合には、公的融資や銀行融資、さらにVCなどの出資が候補になります。
開業時の資金目安は500〜1,200万円程度で、自己資金+融資でまかなうのが一般的とされています。金額に応じた手段の選別が、調達成功の第一歩となります。
必要な「タイミング・スピード」で選ぶ
急な資金ショートやキャッシュフロー不安時には、ファクタリングやビジネスローンのような迅速調達が有効です。ただし、計画に売上根拠や経費漏れがある場合、銀行融資や創業融資では審査落ちリスクが高まります。
スピード重視の手段を選ぶ際は、必要な書類や見通しの正確性も重要な判断材料です。短期資金の対処だけでなく、中長期の計画も見据えて選ぶことが求められます。
「事業フェーズ」で選ぶ
起業・創業期には創業融資や補助金など、審査基準が緩やかな公的制度が活用しやすい時期です。一方、経験が乏しい分野で起業する場合、事業経験不足が審査の障害になりやすいため、計画に具体性と実行力を盛り込む必要があります。
事業が成長期に入ると、銀行融資やVC出資など、信用力をもとにした資金調達が有利になります。フェーズごとの特性をふまえて、適切なタイミングで適切な手段を選択しましょう。
「コスト・手間」で選ぶ
調達手段には金利や手数料など「直接コスト」が存在するほか、書類作成や面談対応といった「間接コスト」も無視できません。例えば、公的融資は低金利ですが、申請書類の作成や審査に時間と労力がかかる場合があります。
対して、ビジネスローンやファクタリングは即日調達可能ですが、金利・手数料が高く、長期利用ではコストが膨らみやすいです。自社の成長度合いや時間軸を考慮し、コストと手間のバランスを見ながら選ぶことが重要です。
面談での準備不足と受け答え
審査面談では、利率・手数料といった直接コストだけでなく、書類整備や説明準備といった間接的な手間も審査官に評価されます。提出する事業計画書には、自己資金比率や収支根拠、マーケット分析といった説得材料を具体的に盛り込む必要があります。
甘い計画では審査落ちのリスクが高まり、面談での受け答えの質がまさに資金獲得の鍵となります。面談準備のコストも踏まえ、総合的に資金調達手段を選ぶ視点が欠かせません。
【状況別】おすすめの資金調達方法と組み合わせ戦略
各ケースに応じた、資金調達方法を組み合わせ戦略とともに見ていきましょう。
ケース1:これから起業する・創業して間もない場合
信用力が低い創業期は、自己資金をベースに公的融資と補助金を併用する王道戦略が有効です。自己資金が一定以上あれば、日本政策金融公庫の「新規開業資金」を無担保・無保証人で利用でき、金利優遇もあります。
さらに販路開拓などを支援する補助金と創業融資の併用により、販路開拓や運転資金の両立が可能です。創業期に特化したこの戦略は、資金に余裕を持たせた事業開始と初期成長の加速に最適です。
ケース2:事業は順調で、さらなる成長・拡大を目指す場合
事業実績がある場合、まずは銀行融資を活用して堅実な成長を図る選択が理にかなっています。一方、より急速な拡大を狙うなら、VCやエンジェル投資家から出資を受け、大規模な資金とともに経営的支援を得る方法も有効です。
両者は性質が異なるため、成長戦略と経営者の意思に合わせた選択が求められます。
ケース3:急な資金ショート!緊急で資金が必要な場合
コストよりスピードを優先する場合は、売掛金があれば即日現金化可能なファクタリングが第一選択です。売掛金がない場合は、ビジネスローンも選択肢になりますが、金利が高めのため、短期的な利用に留める必要があります。
両者を併用することで、短期資金ニーズに対応しつつ、将来的な返済計画や資金補充の戦略を併せて考えることが重要です。
ケース4:赤字決算だが、事業を立て直したい場合
赤字でも利用しやすい資金調達手段として、ファクタリングが特に有効です。審査基準は売掛先の信用力に置かれるため、赤字でも調達可能です。また、公的融資やセーフティネット保証制度などでは、経営改善計画を提出することで赤字企業でも融資を受けられるケースがあります。
まずは短期的なキャッシュを確保しつつ、黒字化を示す計画書を整備することで、中期的な改善に繋げる戦略が重要です。
ケース5:担保や保証人なしで資金調達したい場合
経営者への負担を避けるなら、日本政策金融公庫が提供する無担保・無保証人の創業融資がおすすめです。また、信用保証協会の制度と「経営者保証免除特例制度」を併用することで、保証人なし融資が可能となります。
保証人を要さず合法的かつ安心な融資を受けたい場合、このような選択肢を活用するのが効果的です。
まとめ|自社に合った資金調達で、事業を次のステージへ
資金調達は「事業フェーズ」「資金規模」「緊急度」「信用条件」に応じて複数手段を組み合わせることで最大効果を発揮します。公的融資や補助金は創業期や安定成長期に有効であり、成長期には銀行融資とエクイティファイナンスを併用するのが理想的です。
緊急時や赤字経営下では、ファクタリングや経営改善計画と融合した戦略が有効となります。総合的な視点で戦略を設計し、自社に最も適した資金調達プランを実行することが、事業の次ステージへの架け橋になります。
資金調達のご相談は下記からお問い合わせください。
補助金・融資・出資の選択肢から貴社に最適な方法をご提案!最短3営業日内にご相談可能です。お気軽にお問い合わせください。


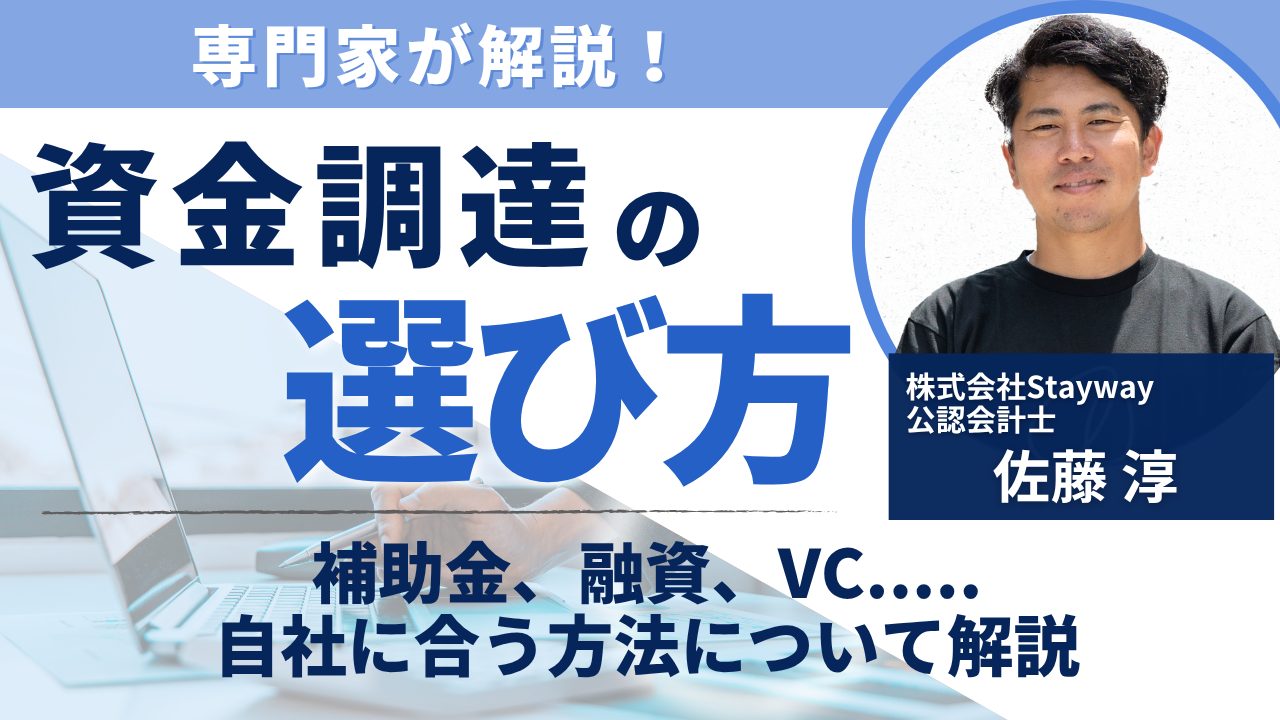




運営からのお知らせ