法人(会社)が事業を行う際には、さまざまな税金を納める必要があります。その中には、今回取り上げる消費税も含まれます。
法人としては、自社の商品やサービスに対してどのように消費税が課され、納付すれば良いのかを把握する必要があります。
法人が消費税を納付する仕組みについて詳しく解説します。
法人の消費税とは
消費税とは、言うまでもなく商品やサービスなどの取引に対して加算される税であり、支払いを行うのは消費者でありながら、実際の課税義務者は商品やサービスを提供した側であるため、間接税の一つに区分されています。
日本では、課税年度売上高が1,000万円を超える法人(事業者)に適用され、該当しない場合は非課税扱いのため納付の必要はありません。ただし一時的に売上が1,000万円を超えた場合は、当該年度に消費税を計算して納付する必要があります。
日本では、2019年10月1日に従来8%だった消費税が10%に引き上げられ、緩和のための軽減税率も適用されたため、算出に手間がかかるようになっています。
法人の場合、例えば帳簿に販売履歴を記録する際には、税率を8%と10%に区分し、小計を出してから全体の消費税を算出する必要があります。このため、消費税計算に戸惑う経営者も多数いるのが現状です。
消費税計算に対応するため、各種の法人向け会計システムなどが利用されていますが、税理士や公認会計士など、専門家のアドバイスを受ける経営者も多いのが現状です。
法人に消費税がかかる取引区分
法人に対して消費税がかかる取引の区分について解説します。
消費行動に対して課税
消費税は、上述のとおり商品購入やサービス利用といった「消費行動」に対して課されます。
このため消費税は、消費行動を伴わないもの、また、社会的な観点から課税が妥当でないと判断されたものに対しても適用されません。
消費税はまた、日本国内の消費行動が対象となるため、海外での消費行動は対象外です。
課税対象と対象外の例
課税対象と対象外について、事例を挙げて解説します。
課税対象
法人の場合、商品の仕入などに際して、仕入額の中に予(あらかじ)め消費税が含まれています。また、自社で提供している商品やサービスの売上にも消費税が加算されます。 例えば、事務手数料などは「サービス」として事務作業を提供する際にかかる手数料なので、消費税対象となります。
課税対象外
一方、課税対象外(非課税)となるのは次の3項目です。
- 非課税取引
- 不課税取引
- 免税取引
それぞれについて確認します。
非課税取引
消費税の対象であっても、社会通念上消費税に適さないと判断される取引は非課税取引に分類されます。主な項目は次のとおりです。
- 保険料の受取り
- 小切手・プリペイドカード等購入費用
- 土地の売却
不課税取引
消費税を課税するための条件に当てはまらない取引を「不課税取引」と呼び、非課税取引とは区別されます。下記のような項目が挙げられます。
- 社員への給与、賃金支払い
- 損害賠償金などの受取り
- 保険料受取り
免税取引
国外での取引は免税となります。例えば、車を米国に輸出して得た利益は国外での消費行動のため、免税取引となり、消費税は発生しません。
場合により課税される取引
課税されない取引であっても消費税対象となる場合があります。 例えば、賃貸の違約金は不課税取引となり、通常は課税されませんが、物件の明け渡しに時間がかかったことなどが原因で発生した違約金は消費税の対象となります。
この事例以外にも、条件によっては消費行動に類するものと認められ、課税される可能性もあります。
消費税の計算方法と留意点
法人が消費税を納付する際の計算方法と留意点について解説します。
計算方法
計算方法の基本は「売上にかかった消費税-仕入にかかった消費税」となります。
法人は、商品やサービスを提供する際、外部から資材を調達しますが、資材を購入した時点で既に消費税込みの対価を支払っています。
例えば、マグカップを3個1,000円で販売、外部から900円で調達している場合、消費税を考慮すると、実際の販売価格は1,100円、外部からの調達額は990円となります。 消費税を納付する際には、販売額に追加された100円の消費税をそのまま納めてしまうと、仕入の際すでに払った消費税90円が加味されていないため、過剰に税金を支払っていることになります。 これを調整し、支払った90円を引いた額(100円-90円=10円)だけを納めることとなります。
すなわち、売上総額にかかった消費税から仕入総額にかかった消費税を引けば、実際に納付すべき消費税となります。
留意点
消費税額の計算方法は簡単にみえますが、計算に必要な指標の出し方が複雑なため、しっかりと理解する必要があります。
課税売上額など、計算時の各項目に注意
課税売上高
消費税額を計算する際、まずは課税売上高を算出する必要があります。
課税売上高を算出する際は、「損益計算書内の売上高=課税売上高」とならない点に注意する必要があります。 課税売上高には、例えば課税資産の譲渡など、損益計算書内の売上高に含まれない項目も追加する必要があるので、損益計算書内の売上高を課税売上高と混同しないことが大切です。
課税仕入高
同時に、課税仕入高の算出も必要です。
非課税や不課税の取引を除いた正確な課税仕入高を算出します。
課税額を計算するため、課税取引、非課税取引、不課税取引、免税取引と、取引を分類する必要があります。
一見不課税に見えても課税取引にあたる取引なども存在するため、取引が発生した状況も含めて正確に判断することが重要です。
最終計算
最後に、下記の数式によって、実際に納付する消費税額を計算します。
(課税売上高が10%のもの合計)×10%+(課税売上高が8%のもの合計)×8%-(課税仕入高が10%のもの合計)×10%+(課税仕入高が8%のもの合計)×8%
法人が消費税の免除を受ける要件
次に、法人が消費税の免除を受ける要件について解説します。
資本金1,000万円未満であること
消費税免除対象となる第一の要件として「資本金1,000万円未満」であることが挙げられます。資本金が1,000万円未満であれば、創業1期目の消費税が免除となります。
自己資産が2,000万円でも、例えば999万円を資本金に計上し、残りの1,001万円を会社への貸し付けとして借入金という形を取れば、資本金を1,000万円未満に抑制可能です。
さらに、出資金の半分までを資本準備金とすることができるため、出資金の一部を資本準備金に充当して資本金を抑えることも可能です。具体的には、出資金の半分までは資本金に組み込みいれない(資本準備金にする)ことが可能と会社法で定められています。
このことから、制度的には999万円を資本金、999万円を資本準備金とし、1,998万円を出資金とすることも可能です。
なお、起業時に資本金が1,000万円未満であっても、2期の開始前に増資して資本金が1,000万円を超えた場合には、2期目から消費税納付が必要となります。
2期目も消費税が免除となる条件
創業2期目は、資本金が1,000万円未満で、以下の条件のどれかを満たす場合のみ、消費税が免除となります。
特定期間の課税売上高が1,000万円以下
特定期間の売上額が1,000万円以下の場合は、2期目も免税の対象となります。
特定期間についての詳細は下記をご確認ください。
参照:国税庁(特定期間)
特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下の場合
社員への給与が1,000万円以下の場合でも免税の要件に該当します。売上を調整するのは難しい反面、給与の調整で1,000万円以下と出来る場合があります。
給与・賞与支払い時期の対応
給与支払額の計算は、発生したものではなく、実際に支払ったもので行います。このため「月末締め・翌月払い」とすることで、例えば1月から6月までの給与として、実質は5カ月分の給与が計算額となります。
賞与も同様、給与の計算に含まれますが、給与が特定期間に1,000万円以下の支払いであるため、例えば上期分給与を下期に支払えれば、節税効果があります。
業務務委託を活用
創業後2年間は、可能な限り人件費を抑制することで、社員への給与支払額を1,000万円未満に抑えることが可能です。ただし、業務上やむを得ず人手が必要な場合には、業務委託を活用するのが効果的です。業務委託であれば、給与ではなく外注費として支払えます。
設立1期目が7ケ月以下
特定期間に売上が1,000万円、給与支払額1,000万円を上回る規模の会社を創業する場合は、会社設立の時期を工夫することがポイントです。
法人の場合、設立1期目が7ケ月以下であれば、特定期間の条件に該当しません。このため、1期目が7ケ月以下となるように設立日を調整することによって、売上高や給与支払額に関係なく、2期間分(最高で1年7ケ月)の消費税が免除されます。
課税対象を選択
起業してから数年は、高額な設備投資や大きな仕入れをする会社も多い状況です。自社が支払った消費税が受け取った消費税よりも多い場合は、その差額が還付されます。
このため、消費税の免税対象とするのではなく、自ら課税対象を選択し、還付を受けた方が得になる場合もあります。設備投資や仕入れと売上のどちらが多くなるのかを計算し、還付金の受給と、消費税免除のどちらが有利かについて検討することが重要です。
まとめ
起業した際、様々な工夫を重ねることで事業開始以降最大2年間は法人消費税が免除されます。
起業後2年間の消費税免除は事業推進に当たって大きな意味があるので、各種要件に当てはまるよう、しっかりと検討いただきたいものです。


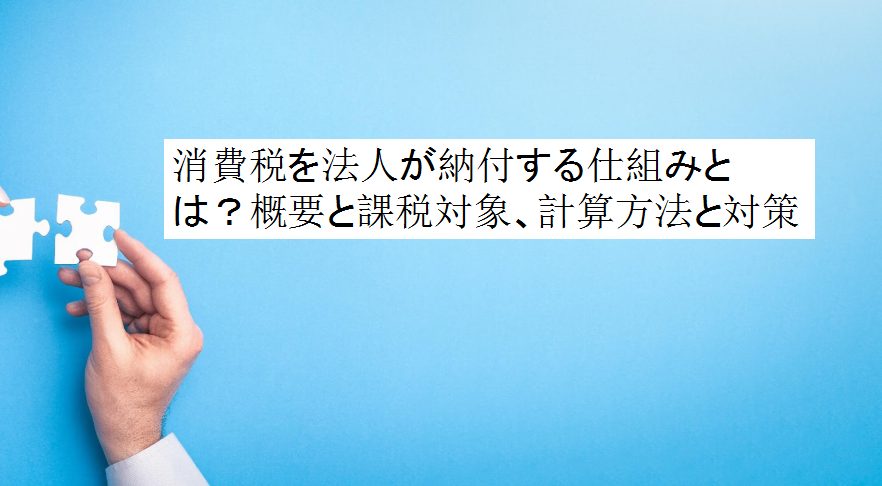




運営からのお知らせ